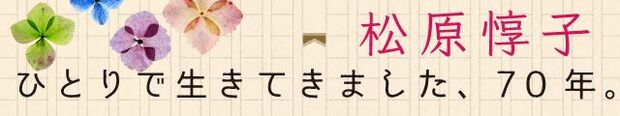1986年『女が家を買うとき』(文藝春秋)での作家デビューから、70歳に至る現在まで、一貫して「ひとりの生き方」を書き続けてきた松原惇子さんが、これから来る“老後ひとりぼっち時代”の生き方を問う不定期連載です。

第4回「ひとり身の人がぶち当たる『身元保証人』という壁」
若いときのひとりと、老いてからのひとりでは、暮らしは変わらなくても、社会の扱いが変わることに気づいたのは、恥ずかしながら60代になってからだ。30代のころは、結婚の2文字に振り回され、鳴門の渦の中だったが、40代の大台に突入した途端にふっきれたというか、シングルは気楽でいいと心から思えるようになり、青空が広がるようになった。
強がるわけではないが、結婚の幸せもあるが、家族に煩わされないひとりの人生は、自由で決して悪くない。ところが、この青空の下の自由が謳歌(おうか)できないときが来るとは、そのときは知るよしもなかった。
待機児童問題に疎かったわたしが「保育園落ちた日本死ね!!!」のニュースを見るまで、その問題の深刻さに気づかなかったように、身元保証人の壁でひとりの人が困っていることに、自分が体験するまで気づいていなかった。
例えば、住まいを借りるとき、入院するとき、手術するとき、介護施設に入るとき、いくら本人に財産があろうが、持ち家であろうが、「身元保証人」を要求される。病院の場合は、身内がいない場合は友達でもいいというところもあるが、それは少ない。ほとんどのところで、身内の身元保証人をたてさせられるのが一般的だ。
身内? どうして身内なのか? 既婚者の方は、あまり疑問を持たずに家族の名前を書くことができるだろうが、未婚、特にひとり身の高齢者にとり、これはとても厳しい要求だ。
わたしの場合だが、子供はいない。今のところ4つ年下の弟、といってもおっさんだが、いることはいるので頼むことはできる。しかし、わたしが長生きしたら、サインができる人はいなくなる。猫に頼むという手もある(笑)。
ひとり暮らしの高齢者が多くなる日本社会にあり、未婚でなくても子供のいない人は多くなる。きょうだいはいても、家庭を持ったらきょうだいとはいえ別所帯。ひとりの人の中には、きょうだいには頼みたくない、頼めない人も大勢いる。
世の中には、いろいろな人がいるのに、身内の身元保証人を当たり前のように要求するのはいかがなものか。