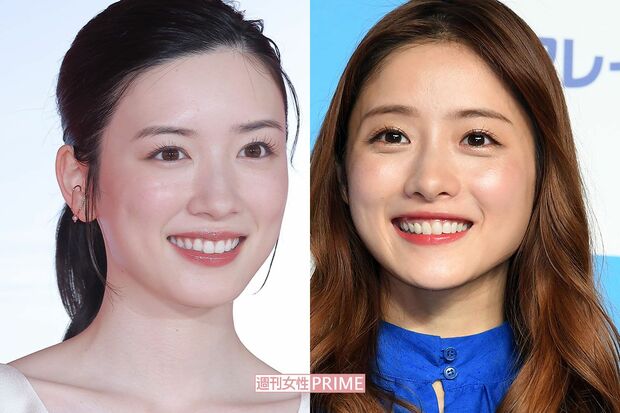高校では谷崎潤一郎、梶井基次郎、志賀直哉などを読破し、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』や、カフカの『変身』などの海外文学にも親しむようになった。東京で芸人修業を始めた後も、文学から離れることはなかったとか。
「三鷹に住んでいたころは、近所にある古本屋を1軒残らず歩いて回って、すべての背表紙をチェック。欲しい本がどこにいくらで売っているかを全部記憶し、いちばん安い店で買う、というようなことを毎日のようにしていました。最近では、あまり見ないような“文学オタク”ですよね」(又吉の知人)
長髪にルーズで地味な色のファッションがトレードマークと、見た目もどんどん文豪風になってきている。エッセーは以前から書いていたので、文章を書くことには慣れていた。それでも、なぜ小説を書こうと思ったのか。
「’11 年に文学フリマの会場で文藝春秋社の女性編集者が声をかけ、’12 年に『別冊文藝春秋』で自伝的な短編を書いたことがきっかけ。これを読んだ女性編集者がすっかりファンになり、その縁で同じ出版社の文芸誌である『文學界』で執筆することになったようですね。芸人の仕事をしながら、わずか3か月で原稿用紙230枚を書き上げたというのは、かなりの早さです」(文芸担当編集者)
仕事を終えた深夜から執筆を始めて、朝まで書く。仮眠をとって仕事に行き、また夜になると小説を書くという毎日。
普段は同じ事務所の芸人であるパンサーの向井慧、ジューシーズの児玉智洋と3人でルームシェアをしているが、原稿を書くときは別の場所にある仕事部屋に行っていた。
「仕事部屋と言っても、実態は風呂なしのアパート。机とパソコンだけしか置いていない殺風景な部屋です。なぜそこを選んだのかというと、若いころに味わった情けなさを思い出すためなんですって。精神的に一番キツかったころに住んでいた街にあえて身を置くことで、自分を追い込んでいるんです」(放送作家)
彼のストイックなエピソードはこれだけではない。
「今でこそ執筆にパソコンを使っていますけど、3年くらい前まではまともに使えなかったみたいで、ケータイでカチカチと音を立てながら文章を作っていたんですよ。彼は文学界で唯一の“親指が腱鞘炎になった”という人物じゃないですかね(笑い)」(前出・又吉の知人)
文藝春秋社のウェブサイトには、作品についてのコメントをこのように寄せていた。
《僕は、人間を深く掘り下げた小説に何度も救われてきました。『火花』は自分なりに人間を見つめて書いた作品です。小説好きの方はもちろん、普段読まない方にも漫才だと思って読んでいただけると嬉しいです》
小説家として華々しいデビューを飾ったわけだが、これからも書き続けていくのだろうか。ベストセラー作家なのだから、出版社からのオファーが殺到する可能性もある。
「芥川賞だって夢ではありませんよ。作品のクオリティーも大事なんですが、小説が売れない中、出版業界は次のスターを求めていますからね」(書店関係者)