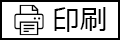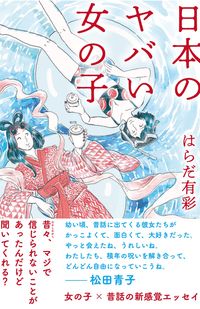ふっくら、ぽってりとした頬に、タレ目と下がり眉。低くて丸い鼻と黒い垂髪(すいはつ)がトレードマークの女の子、「おかめ」。正月遊びのひとつ「福笑い」や、某お好み焼き用ソースのアイコンでおなじみの彼女だが、その半生をご存知の方はどれくらいいるだろうか。
実はこのおかめ、「献身的」なんて言葉では生ぬるい、“超超超・尽くす女”なのである。夫への慕情ありあまってか、彼女は「ええええ、う、嘘でしょ!?」とツッコまずにはいられない理由で突如、自らの手で人生に幕を下ろす。
いったい何が彼女をそうさせたのか、優しげなニコニコ顔の裏にどんな思いをかかえていたのかを京都に伝わる「おかめ伝説」から読み解くのは、『日本のヤバい女の子』(柏書房)の著者、はらだ有彩さん。
本書ではおかめの他にも、相手を老人に変えてしまう玉手箱をなんの説明もなく贈る「浦島太郎」の乙姫、惚れた男の周りをウロつき続け、憑(と)り殺してしまう「怪談 牡丹灯籠」のお露など、昔話に登場するエキセントリックな女の子20人がクローズアップされている。
一見、突拍子もない言動にはしる彼女たちの真意はどこにあったのか? はらださんは、まるで友達とおしゃべりするかのように、それぞれの生き様に思いをめぐらせ涙を流し、怒り、時には拍手と賛辞を送りながら、疑問を解き明かしていく。そして彼女たちの、あり得たかもしれない未来や、もうひとつの人生を思い描く。
はらださんが織りなす、“ヤバい女の子”たちとの愛ある対話の中から、前述のおかめに関するエピソードを紹介したい。
(以下、はらだ有彩著『日本のヤバい女の子』より)
献身とヤバい女の子・おかめ
彼女はいつもにこにこ笑っている。目も眉もハの字に垂れ下がり、ふくよかな頬はばら色に染まる。みんな彼女を見ると幸せな気分になる。でも、彼女自身は幸せだったのだろうか。
長井飛騨守高次(ながいひだのかみたかつぐ)は困り果てていた。高次はベテランの大工である。京都・大報恩寺の本堂の工事を任され、張り切っていた。
しかし、自分でもなぜそんなミスを犯したのかわからないのだが、柱を作るための木材を誤った寸法で切断してしまった。それもただの木材ではない。この日のために信者から奉納された特別な木だ。
(これはもう、命をもって償うしかない……)
思いつめた高次を妻のおかめが見ていた。彼女は今にも消えてしまいそうな夫を励まし、静かに自分の考えを話す。
「まずは落ち着いて。ここは思い切って、他の正しいサイズの木材も、間違って短くしてしまったものと同じ長さに揃えましょう。そして切った木片を四角く組んで枡組(ますぐみ)を作り、寸足らずになった部分をおぎなってはどう?」
結果的に、彼女が考えた方法はとてもうまくいった。高次が大変な失敗をしたと思う者は誰もいなかった。本堂を見た者はみな美しく凝った意匠に感動した。
上棟式の前日、高次はピンチを救ってくれたおかめに改めてお礼を言おうと思った。しかし、朝からずっと姿が見えない。
ようやく探し当てたとき、妻は人目につかないところでひっそりと自害していた。
女である自分に窮地を助けられて仕事を成功させたということが世間に知られたら、夫の名誉に傷がつく。そう思い、彼女は自ら死を選んだのだった。
悲しみのなかで上棟式が執り行われた。高次は御幣をつけたおかめの面を本堂に飾り、彼女を偲んだ。
ーーう、う、嘘だと言ってほしい。
この物語を読み終えたときの私の驚きといったらなかった。死ぬ!? 死ぬ必要ある!? とりわけ「女の助言で仕事を成功させたことが夫の不名誉になる」という世界観を理解しようとすると、全身から混乱の汗が吹き出る。すんなり納得するには私は現代に暮らしすぎている。
え、これって、美談なの?
鎌倉時代の夫婦の逸話をもとにしたという「おかめ伝説」は、現在も京都の大報恩寺に伝わり、内助の功、ひいては夫婦円満の美談として受け継がれている。確かに二人の間に強い絆があることはわかる。
ただ、これは本当に完璧な美談なのか? という疑問がどうしてもぬぐえない。おかめと高次は夫婦という関係のロールモデルになり得るのだろうか。
彼女の死には言いようのない違和感がある。なにかが決定的にわからないような、どこかが圧倒的におかしいような気がする。他人の死についてあれこれ詮索するのはとても下品だ。だけど私は彼女の死を想像し、この違和感の正体を突き止めたい。
死が生きている人間全てに訪れるものだということはもちろん理解できる。人は自ら命を絶つことがあるということも、受け入れがたい気持ちをよそへ置けば理解できる。名誉や尊厳のために命を使ったり、愛する人のために自分を犠牲にするということだって、自分の身に置き換えて考えるとありえないとは言いきれない。
こんな風に、おかめの死をひとつひとつ分解していくと、なるほど、そのパーツは理解できる。それでも、このじりじりとせり上がる違和感はなんなのだろう。
たぶん、彼女にとって、自分の死には根拠があった。だけど彼女が信じた死の根拠は、現代に生きる私たちにとっては跡形もなく破綻してしまっている。その甲斐のなさが本棚の後ろへ落としてしまった小さな紙のように、見えないけれど確実に存在していて、私はどうにも落ち着かないのだ。
おそらくこの物語を読んだ誰もが(死ななくたって良いじゃん! 黙ってれば良いじゃん!)と思っただろう。二人だけの秘密にして、黙っていれば丸く収まるではないか。しかしおかめは夫の名誉を守るためにはそれでは済まされないと判断した。
大工なのだから、完成した建築物が素晴らしければチーム内でどのメンバーの意見を採用しようとプロジェクトの成功に変わりはないはずだ。それで夫の名誉が傷つくとは思えない。
おかめ自害の謎を解く
では、おかめはなぜ死んだのだろう。高次(と彼の名誉)にとって、おかめが生きていたら困ることが何かあっただろうか。八百年前の社会に思いを馳せつつ、サスペンスドラマよろしくおかめの死の真相を推理してみよう。
まず、高次本人がおかめに助けられたことに後ろめたさを感じていたとすれば、口封じのためにおかめを殺す……という展開があるかもしれない。助けられたという屈辱に耐えられなくなり、殺してしまったというストーリーだ。
あるいは、いかにも高次が犯人と思わせておいて、夫の苦悩を汲んだおかめが(自分があなたを裏切ることはない)と証明するために死んでみせた……というオチもありうる。
いや、おかめ自身が、誰かにうっかり話してしまう可能性を危惧したということも考えられる。もしかしたら自分だって正しく評価されたいと思って告発してしまうかもしれない。
はたまた、事実自体を消したかったのかも。おかめは腕の良い大工である夫を愛していた。夫の失敗という事実を許せず、それを知っている人物、つまり自分自身を消すことにしたのかも……。
と、ここまで考えて気が滅入ってきた。そもそも、おかめが高次を助けたことが「全く恥ずかしくない出来事」であればいま考えたようなサスペンスは成立しない。
どれだけ推理を重ねても、「女にアドバイスを受けたこと=恥」という背景が全ての原因だ。女は男より秀でてはいけない。男は女に助けられてはいけない。
おかめに、高次に、重くのしかかっていた暗黙の設定は彼女たちの時代には覆せないものだった。だからおかめにとって自分の死は大きな意味と必然性があったのだ。だけど数百年という時間が流れ、暗黙の設定が変化していくなかで、その意味と必然性は薄れていった。
ただし、薄れたとはいえ、暗黙の設定はいまの私たちにも作用している。冒頭で「現代に暮らす私はおかめの死に納得できないし、彼女の不自由さ、生きづらさが理解できない」と書いたけれど、その一方で、わかるとも思う。わかる。少しわかる。とてもわかる。
女性にのしかかかる抑圧の壁
インターネットに、本屋に、ハリウッド・スターのスピーチに。ニュートラルで現代的で勇気づけられる言葉は私たちの周りにたくさんある。それらはいつもエンパワメントをもたらし、新鮮な共感に満ちている。
私たちにできないことは何もないし、言えないことも何もない。誰もが適切なタイミングで怒ることができるし、意見を主張することもできる、はずである。はずではあるが、一方、暮らしの中ではときどき、驚くほど馬鹿馬鹿しいシチュエーションにぶちあたる。
例えば、仕事場にいる気のいいおじさんが世間話のはずみに「早く帰ってごはん作らないと」とか「仕事熱心なのはいいけど、彼氏、怒らないの?」と言う。同期入社の男の子に転職の相談をすると「女の子は好きな仕事しといた方がいいよ」とアドバイスを受ける。
自分で選んで取り入れる情報ではない、ふと遭遇するこれらの言葉に対して(ちょっと変な感じだな)と思ったとして、そして自分の感覚が間違ってないと確信できたとして、情や諦めやその他の面倒な気持ちによって、さっと流してしまうことが、毎日の暮らしでは頻繁に起こるのだ。
こんな気さくな抑圧は時代に合わせて少しずつマシになり、将来的にはなくなっていくかもしれない。だけど、おかめは時代が変わるのを待たずに亡くなった。
結局、おかめが死に至ったことで、彼女の働きは現代にまで伝わることとなった。伝わっているということは、誰か――真実を知っている誰か――が人に話し、残したということだ。みんなに知られてしまったら、おかめの死の意味はなくなってしまう。それでも高次は人々に知ってほしかった。妻の存在をなかったものにしたくなかった。
おかめ、幸せになって
私は「アイデアを出したおかめ自身が評価され、夫と一緒に建築家として成功する」という結末がなかったことが心から残念でならない。せめて彼女が満足していればいい、とはどうしても思えない。だって、彼女の人生はどうなるというのだ。
おかめは男のピンチに出現して、都合のいいアイテムやフラグを与えてくれる美味しいキャラクターだったのか? 彼女の幸福が夫の幸福そのものだったら、それで報われたと言えるのだろうか。
死んでしまったら、もう会えないのだ。人生の道のりのどこかで、必ずもうこれ以上一冊の本も読めなくなる瞬間、これ以上一曲の音楽も聴けなくなる瞬間、一枚の絵も描けなくなる瞬間がある。
だからそのときまでは誰にも邪魔されず、できるだけ多く読んだり、聴いたり、描いたりしてほしい。自由に話して、自由に考えて、自由に働いて、あなたの心からの人生を一秒でも長く続けてほしい。そう思うのは私の勝手な希望だ。
「そんなことどうだっていいよ、放っておいてよ、余計なお世話だよ」「彼のために死ぬことが私の望みなの」。そう言われてしまうと私にはもう何も言えない。結局、まあ、そうなのだ。彼女の命なのだから。
だけど私はほんとうに悲しい。悲しいとあなたに伝えられない関係が悲しい。私、あなたと友達だったらよかったのに。
――女だから、自分の存在を消すことが最もよい選択だから、私もそれで納得しているから。私、ほんとに全然後悔していないの。これから先どんな価値観の時代になろうと、何の後悔もないの。
もしも友達だったらそうやって笑うあなたを張り倒し、「うっせーバカ! アホ! ステーキ食ってカラオケ行くぞ!」とキレることができたのに。ステーキ食って、カラオケ行って、そのまま夜行バスで眠って、起きたら電車を乗り継いで、飛行機にも乗ったりして。
あなたが満ち足りた気持ちでいられて、誰もそれを悪く思わない場所まで行ってしまえたのに。もちろん、あなたの功績を残してどこかへ移動しなければならないことに私は忸怩(じくじ)たる思いを感じるけれど、それでも、何でもいいから生きていてほしかった。
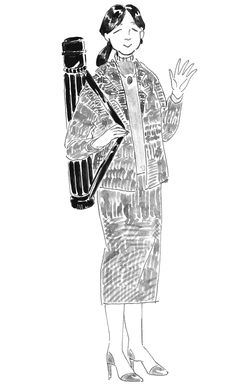
物語の舞台となった京都の千本釈迦堂・大報恩寺には現在、おかめの墓塔と像が建てられている。かたわらには「おかめ桜」と呼ばれる木が育っている。巨大な枝垂桜(しだれざくら)は三月の終わりになるとぶわっと噴き出すように花をつけ、うねうねと曲がった枝が重く下がる。
彼女が現代に生まれ変わったら、どんな人生を歩むだろう。夫の仕事ぶりを横目で見ているうちに頭の中にアイデアが溢れてきて、今度こそ建築家になるかもしれない。桜の枝の曲線のように自由な形のビルを設計するおかめを想像してみる。
斬新な発想で新しい造形を生み出す建築家として評価されているおかめを。そんなおかめをサポートしつつ、同じくバリバリ活躍している高次を。アイリーン・グレイ、ザハ・ハディッド、おかめ、と名前が並んでいるWikipediaの一ページを。
プロフィール欄に一枚の写真が掲載されている。少し丸顔で目尻が柔らかく垂れ下がった、彼女の顔がにこにこと笑っている。
〈著者PROFILE〉
はらだ有彩
はらだ・ありさ 関西出身。テキスト、テキスタイル、イラストレーションを作るテキストレーター。デモニッシュな女の子のた めのファッションブランド《mon.you.moyo》代表。 これまでに、「アパートメント」「リノスタ」「She is」にエッセイやマンガを寄稿。 Twitter:@hurry1116 / Instagram:@arisa_harada
〈イベント情報〉
◎『日本のヤバイ女の子』出版イベントin大阪 ~私たちが昔話になる日を夢見て~
6月23日(土)13時30分開演、前売り2000円(※要1オーダー500円以上 )
出演:はらだ有彩
ゲスト:三宅香帆(大学院生/書評家)、小松和彦(文化人類学者)
会場:ロフトプラスワンウエスト(大阪市中央区)
詳細・予約はhttp://www.loft-prj.co.jp/schedule/west/89873にて
◎日本のヤバい女の子「天国飯と地獄耳」刊行記念トークイベント
~日常の中の非日常の見つけ方~
7月1日(日)19時開演、前売り1500円
出演:はらだ有彩・岡田育
会場:Readin' Writin' BOOK STORE(東京都台東区)
予約はお名前、人数、ご連絡先を明記のうえ、info@readinwritin.netまで