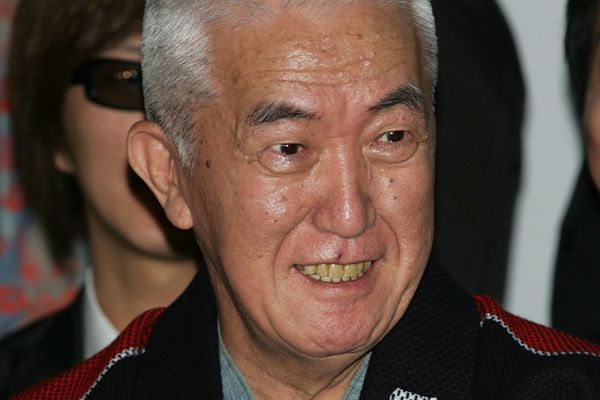
「三回忌は六輔の命日にあたる7月7日に、身内だけでやる予定です。父の実家は浅草のお寺ですので、四十九日、一周忌と、折々、集まってお経をあげております」
6月下旬、永六輔さん(享年83)の長女・千絵さんは、週刊女性の取材に“2年がたった今も、父が帰ってくるような気がする”と言って、ひとつひとつを思い返すように話し始めた。
「あちこち全国を旅して歩いていた人なので、日ごろから家にいなかったんですね。だから2年たってもまだ長い留守番をしているような感覚で、今回はちょっと長いねっていうくらいです。本当に帰ってきたら怖いですけど(笑)」
永さんが亡くなったのは、’16年の7月7日。6月27日にTBSラジオの冠番組『六輔七転八倒九十分』の最終回が放送された直後である。作詞家、エッセイスト、ラジオパーソナリティーなどのさまざまな顔を持ち、すべてをやりきった“大往生”だった。
「遺(のこ)された者としては片づけをするのが大変なんですよ。書斎の中には、書き散らかした原稿や書類、メモのようなものが山積みに置いてあります。2年間、ずっと当時のままなんです。記念館を作りませんかというお話もいただいたんですが、この量の遺品を管理するのは大仕事ですよ」(千絵さん、以下同)
仕事があまりにも多岐にわたっていたので、資料もひとつにまとまらない。
「作詞に関してはJASRACの『古賀政男音楽博物館』に展示していただいていますが、テレビの台本は別の組織の管轄です。国や行政は何もしてくれないんですよ。作家や映画監督の方など、みなさん困っていますね。今のトップの方々は、文化を財産だと思っていないんです……」
父が何げなく言ってきたことが、遺言だったんじゃないかな
千絵さんは妹の麻理さんと相談し、実家の寺に歌碑を建てたそうだ。
「去年の4月10日、父の誕生日にできました。普通の四角いお墓よりもいいんじゃないかということで、『上を向いて歩こう』の歌詞が彫ってあります。本人は大げさなことが嫌いなので、“こんなもの作っちゃって”と思っているかもしれませんが」

とはいえ、永さんの遺志がどうだったのかはわからない。遺言書が見つかっていないからだ。
「父からは“書いた”と聞いていたのですが、なにしろ部屋がひどい状態ですから、まだ出てこないんです(笑)。見つからないのか、そもそもあるのかどうかもわかりません。まぁ、今まで父が私と妹に何げなく言ってきたことが、遺言だったんじゃないかなと思っています。孝雄くんだったらこうなったはずだということで納得しました。遺ったものが納得すればいいというのが、孝雄くんのいちばんの望みだと思います」
“孝雄くん”というのは、永さんの本名。永家では、父親を“孝雄くん”、母親を“昌子さん”と呼んでいた。
「孫が生まれるかなり前から、うちではそうでしたね。だから、孫も同じように呼んでいました。父は自分のことを一家の“長”であるとは思っていなかったし、“俺がいちばん偉い”みたいなことは1度も言わなかった。母のことをとても大事にしていましたね。母が元気なころは手をつないで歩いていましたし、イメージとしては“昭和の厳格な親父”ではなかったんですよ」
外山アナが感心した永さんの話芸
家族だけでなく、仕事仲間にも偉そうに接することはなかった。TBSラジオの番組『永六輔その新世界』と『六輔七転八倒九十分』で、16年にわたってアシスタントを務めたアナウンサーの外山惠理は、1度も怖い思いをしたことはないと話す。
「この世界で有名になると、どうしても“威張っているオーラ”が出てくるんです。自分だけが頑張ってきたような顔をする人もいましたが、永さんは違いました。本当に何でも知っていて何でも答えてくれましたが、知らないことに関してはバカにしたりしない方でしたね。“何でも知っていますね”と伝えたら、“僕が知っているんじゃなくて、いろんな人から教えてもらったことを言っているだけ”と言うんです。この方はすごいなと思いました」

彼女が感心したのは、永さんの話芸だった。
「毎週、ラジオでもプライベートでも会っていましたが、同じことを何度話しても面白いんですよ。同じ話をいろいろな人にすると、いらないところが削(そ)ぎ落とされて半分ぐらいになるんだと話していました。今までにいろいろな方と会ってきた中でも永さんは別格の方ですね。番組でも4時間半の間、1度も退屈したことがなかったんです」(外山アナ)
放送作家としてテレビの草創期に活躍したが、大好きなのはラジオだった。だから、千絵さんは最近のラジオについて悲しく思うことがある。
「一方通行な方が多いなと思います。父は聞いてくださっている先に行って、そこで見聞きした話をもう1回持って帰ってきて、自分の話として出すという手間を惜しまない人でしたね。東京のスタジオでしゃべるだけでは納得がいかなかったんだと思います。知ったかぶりをすることをすごく嫌がる人でした。でも、私が映画の話をすると、きちんと聞いてくるんです。年は関係なく、自分が知らないことに関しては“そうなんだ”と、すごく興味を持って話を聞こうとする人でしたね」
外山アナも、永さんの知りたがりっぷりを見ている。
「怠けるということをしない人でしたよね。ちょっとでも時間が空くと映画を見に行ったり、展示会に行ったり。電車の中でも一般の人の話をよく聞いていたから、カップラーメンが1ついくらとか細かいことを知っていました。最後まで手書きだったし、携帯も持たないからスマホを見せると、“便利だね”なんて言っていましたが、辞書を引いて図書館に行くことにこだわっていましたね」
’10 年にパーキンソン病であることがわかり、翌年には自宅で転倒して大腿骨(だいたいこつ)を骨折。入院するものの、病室でラジオ番組を収録した。前立腺がんも発症して闘病が続いたが、仕事に対する意欲は衰えなかったと千絵さんは話す。
「がんがわかった後もずっとひとりで暮らしていて、自分のことは自分でやっていました。私が介護をするようになったのは、亡くなる1年半くらい前からですね。大腿骨を骨折したときもリハビリを頑張りまして、杖(つえ)をつきながらも出かけることができるようになりました。比較的ギリギリまで元気だったという気がします。亡くなる半年前までは仕事もしていましたし、台所にも立っていましたよ」
永さんと会わなかったら、違う人生に
永さんがラジオに出演していて、だんだんろれつが回らなくなってくるのを、外山アナは感じていた。
「私はわかるんですが、リスナーにはわかりませんよね。そのうち、私に目で訴えれば代わりに話してくれると思っているんだろうなということを感じられるようになったんです。しまいには首を振ってるだけ。ラジオなんだからそれじゃあ伝わらないじゃないですかと。でも、リスナーの方は永さんが話さなくても聴いてくださるという、恩返しをしてくれてもいましたね」

死から2年がたったが、彼女は、今もよく永さんのことを思い出す。
「一緒に来たな、一緒に歩いたなという場所がいっぱいありすぎるんです。必ず1日に1回は心の中で“永さん”と言っているし、もう三回忌なんだ、という感じですね。本当に大きな損失です。こういうときに永さんだったらどうするかと考えるのが、普通になっていますね。ただ、会えたことが本当によかったなと思います。永さんと会っていなかったら全然、違う人生だったと思います」
亡くなった後も、千絵さんはテレビで流される永さんの映像を見ることがある。
「やっぱり有名人だったんだこの人はって思いましたね。有名人の娘なんだなということを思い知らされました。今でもテレビの中で会えて“こんなこともあったな”ってふと思い出させられる。それはつらいわけではないんだけど、不思議なことですね。でも、私にとっての父は、みなさんの知っている“六輔”ではなく、本名の“孝雄”なんです」
そう言うと、外を見ながらニコリと笑うのだった。


