東京・亀戸にある創業215年の和菓子店「船橋屋」。JR東日本のお土産グランプリを受賞するほど人気のくず餅を昔と変わらぬ製法で、自然素材にこだわって作り続けている。そんな地元に密着した老舗が、実は就職希望者が殺到する超人気企業になった。8代目社長の行った自身と組織の意識改革とは?

新卒就職希望者が1万7000人
暖冬の影響で梅の花がいち早く咲いた2月中旬の東京・亀戸天神。コロナウイルス感染拡大の暗い世相をまるで感じさせない穏やかな空気が流れる中、参拝客数人がすぐ隣にある老舗ののれんをくぐっていく。創業1805年の船橋屋・亀戸天神前本店である。
「いらっしゃいませ」
定番のくず餅やあんみつなどがズラリと並ぶショーケースの前で丁寧に接客していたのは若い男性。奥の女性スタッフも笑顔で注文を受けている。『三国志』『私本太平記』などで知られる文豪・吉川英治の手による「船橋屋」の大看板が掲げられた喫茶ルームでは、幅広い世代のお客さんがゆったりとした時間を楽しんでいた。
「こんにちは。わざわざ足を運んでいただきまして、ありがとうございます」
爽やかな笑顔で現れた船橋屋社長の渡辺雅司は、スマートな印象。2月16日に56歳の誕生日を迎えたというが、若々しい風貌からはアラカンの仲間入りとは全く思えない。
「僕は健康オタクでね。1年に2度は伊豆の山の中にある断食道場に行っているんですよ。胃腸と脳をリセットすることで心身ともにスッキリしますし。おかげさまで病気になったことは1度もないです」と気さくに語る様子は、老舗の社長のイメージとはかけ離れていた。
そこに社員数人が集まってきて、「社長、サプライズバースデーです」といきなりケーキを差し出した。渡辺のそっくりさん人形までのっているケーキを差し出され、「え~、取材中におかしいでしょ、こんなの」と苦笑いしつつも喜びをにじませる。アットホームなムードから会社の風通しのよさがうかがえた。

「今でこそ、こんなふうに和気あいあいとした感じですけど、僕が入社してから20年弱は紆余曲折の連続でした。社員との言い合いは数えきれないし、テーブルをひっくり返したこともある。本当にうまくいかないことばかりだった」と渡辺は苦笑する。
本人の言う「紆余曲折」とは一体、どのようなものだったのか。そして船橋屋はいかにして新卒就職希望者が1万7000人も押し寄せる人気企業になったのか。ひとりの経営者と老舗くず餅店の物語が今、幕を開ける。
★ ★ ★
渡辺が生まれたのは1964年。前回の東京五輪開幕を8か月後に控え、日本中が熱気に包まれていたころだった。2年後に妹も生まれ、4人家族が暮らしたのは千葉県船橋市の中山競馬場の近く。田園風景の広がる一帯で、雅司少年は外を駆け回る幼少期を過ごした。
「夏はセミの大合唱が聞こえる環境で、カエルやヘビ、ザリガニを捕まえるような好奇心旺盛な少年でしたね。泥だらけになるまで毎日遊んでました」
そんな息子を7代目当主で現会長の父・渡辺孝至さんは温かい目で見守っていた。
「小学校のころはケンカをすることもしばしば。ヤンチャな一面は確かにありましたが、泣いている同級生を保健室に運んで励ますような正義感も垣間見えましたね。私自身も、『人様に迷惑をかけない程度のいたずらなら、目をつぶろう』という考えだったので、本人も、のびのびできたのではないかと思います」
常に頭の片隅にあった「自分は8代目」
自由を満喫していた小学校時代から一転して、卒業後は一家で都内へ引っ越す。長男である渡辺は千代田区・麹町中学校に進むことになった。同中は名門私立中学校に入れるくらい学力優秀な子どもが集まる。学校も広々とした400mトラックのある船橋時代とは打って変わって、150mのコンクリートのトラックしかない。環境の激変に少年は戸惑うばかりだった。

「中1の中間テストの成績が学年331人中306番。当時は全員の順位が廊下に貼り出され、自分も『このままだとヤバい』という気持ちになりました。担任の先生から『落ちこぼれに半分足を突っ込んでます』とまで言われました。親父はもともと僕の勉強には熱心でしたが、『このままじゃ大変なことになる』と考えたのか、家に帰るとほぼ毎日、自ら家庭教師に。
一方的に勉強を押しつけられるのは嫌でたまらなかったけど、実際に成績は悪いし、やるしかない。嫌々でもやれば成績は上がっていき、褒められてうれしいことはうれしかった。でも、やりたくて始めたことではなかったので、僕自身としてはどこか納得がいかなかったですね」
最終的には学年で20番台まで成績を上げ、立教高校に合格。両親はとても喜んでくれた。だが、無理強いされる理不尽さに違和感を覚え続けた中学3年間だった。
立教高校時代は学生生活を大いに楽しんだ。週末になると六本木の人気のディスコに繰り出しては羽目をはずしていた。当時からの親友で現在は会社を経営する土屋毅さん(56)は、こんなエピソードを披露する。

「雅司とは高2からの付き合い。ウチの高校は中小企業の経営者の息子が多くて、同じような境遇ということで意気投合したんです。よく遊びに出かけましたね。雅司は松田聖子の大ファン。コンサートも最前列を確保するほどの熱の入れよう(笑)。そこで撮った生写真を自慢げによく見せてくれました。高校卒業直前には一緒に教習所に通って、18歳でスカイラインに乗ってましたけど、興味があるものは貪欲に取りに行く。その姿勢は今も変わっていないと思います」
立教大学時代もテニスサークルに入り、青春を謳歌していた。ただ、頭の片隅には「自分は船橋屋の8代目。いつかは家業を継ぐんだろうな」という思いがあり、経済学部で学ぶ傍ら、専門学校に通って簿記の資格を取得した。老舗で育った彼には「お金の流れを制する者はすべてを制する。会計に強ければビジネスマンとして必ず成功する」という信念があり、それを実行に移したのである。
進路はその延長線上にあった金融を選択。'86年春、三和銀行(現三菱UFJ銀行)に入行する。前年の'85年のプラザ合意の影響で、円高ドル安が一気に進み、投機などが活発化したこともあり、本人はディーリングを手がけたいという夢を描いていた。最初の配属先は日比谷支店。最初の2年間は融資、次の3年はディーリングを担当したが、「とにかく貸せ」というイケイケ時代の行員としてエネルギッシュに働いた。
そして'91年春には銀座支店へ異動。赴任した当初は並木通りに絵画ギャラリーがまだズラリと並ぶような華やかさだったが、徐々に状況は変わりつつあった。カネ余り状態から株価が下落し、地価も急降下。これまで高級店で接待してくれていたような取引先の経営に黄信号が灯り始めた。
渡辺は急激な環境の変化に戸惑った。
「それまで『貸せ貸せ』と言っていた会社が、本部に3年いる間に『貸金を回収せよ』と方針転換したんです。これには驚きました。指示どおり、銀座の取引先に出向くと『急にそんなこと言うんですか』『手のひらを返すんですか』と反論され、泣きつかれましたね。半年前までお金を湯水のように使っていたオーナーが、経営が苦しくなってきて家を抵当に入れ、奥さんに三下り半を突きつけられたあげく、倒産して一文無しになるというケースも目の当たりにしました。
バブル崩壊を乗り越えた取引先の経営者が『お金が紙に見えたとき、人間はいちばん傲(おご)っているんだ』とつぶやいた言葉は、今も脳裏に焼きついて離れません」
出社直後の床掃除からスタート
まさに、ドラマ『半沢直樹』の世界だ。いわゆる「貸しはがし」を容赦なく求める銀行の体質に、渡辺はついていけなくなってきた。そんな'92年夏、6代目の祖父・達三さんが病に倒れ余命1年と宣告された。祖父には幼いころから可愛がってもらっただけに恩返しをしなければいけないという思いはあった。それを機に「家業に携わりたい」という気持ちが強まり、彼は父に決意を打ち明けた。孝至さんはそれを耳にしたときの感情を克明に覚えている。
「生まれたときからいつか跡を継がせたいという思いがあったので、息子の申し出をとてもうれしく感じました」

こうして'93年3月いっぱいで銀行を辞め、船橋屋の一員として再出発することを決めた。それに当たって、彼はひとつの覚悟を胸に刻みつけたという。
「景気の変化に左右されて落ちていく経営者には絶対にならない。常に利益を上げ続けなくてはダメなんだ」と。
前述のとおり、船橋屋の創業は1805年。徳川幕府11代将軍・家斉の時代だ。明治から昭和にかけて芥川龍之介や永井荷風、西郷隆盛も訪れたというが、215年もの長い間には苦境に瀕したときもある。最大の危機といわれるのが、1945年(昭和20年)3月10日の東京大空襲。米軍のB29戦闘機が10万発以上の焼夷弾を落とし、東京は焼け野原になり、船橋屋も工場・家屋のすべてを焼失したのだ。しかし5代目・房太郎の妻・みえが、戦火のなか、くず餅の原料である発酵小麦でんぷんの樽を地下に埋めて守ったことで、その後も商売が継続でき、発展した。
入社した渡辺は、まず工場でくず餅の作り方を学んだ。出社直後の床掃除が、将来の8代目となる専務取締役の第一歩であった。
くず餅というのは、小麦粉を練って水洗いし、必要なでんぷん質だけを沈殿させ、発酵させたもの。でんぷん質を木の貯蔵槽に入れて450日間じっくりと熟成。貯蔵槽に付着した乳酸菌による発酵によって独特な歯ごたえと風味が生まれる。これを蒸し上げ、食べやすいサイズに切るのだが、蒸し方や切り方によって味わいが変わるし、くず餅にかける黒蜜やきな粉の製造にも繊細さが求められる。しかも無添加であるため、450日熟成させたものなのに消費期限はわずか2日。彼らは「刹那の口福」と称しているが、高度な職人技が凝縮された工程を渡辺は学んでいった。
反論する職人を次々と……
こうした中、違和感を覚える点がいくつもあった。最たるものが職人たちの姿だ。
茶髪のみならず、パンチパーマやアイパーという清潔感のない髪型や服装をしている者が多く、地元では、ヤンキー風の人間が歩いていると「あれは船橋屋の人間だ」と言われるほど。どんなときもスーツでパリッと決めてきた元銀行員にはとうてい受け入れられなかった。
当時、工場で働いていた現仕入受注管理部部長・小野寺隆侍さん(50)は当時の実情を語る。
「現社長が来られたころの船橋屋は工場で10数人が働く程度の小規模の会社でした。職人たちには『いいものを作るんだ』『俺たちが会社を支えてる』という気概はありましたが、昼休みになれば麻雀大会は当たり前。午後も仕事が早く終われば日の高いうちから飲みに行くのが普通で、20代だった自分も『こんなのでいいのかな』と感じることがありました。現社長は年齢の近い私に『職人さんは何を考えてるのかな』『雰囲気はどう』と聞いてくることもありましたけど、最初はじっと黙って様子を見ている感じでした」

自分なりに会社の現状を把握した渡辺は2年目から改革に着手する。長年の付き合いのある銀行との取引を見直し、言い値で材料を買っていた仕入れ先にも値下げ交渉を申し入れた。相手が納得しなければ容赦なく切り捨てる。その冷徹さは数字至上主義の銀行マンらしい考え方だが、高度経済成長期の「いいものを作れば黙っていても売れる」「コストダウンなんか必要ない」という時代の空気が染みついている社員や職人たちは納得しない。ぶつかり合うこともしばしばだった。
前出の小野寺さんが話を続ける。
「材料の価格が多少高くても『売れているんだからそれでいい』という感覚を持っていた人が多かったんでしょう。でも経営の本質を知る現社長は納得できなかった。反論してくる職人を次々と切り始めて、徐々に殺伐とした雰囲気になっていきました。先輩職人が怒って辞めていく姿を見て、『ここまでやるのか』と感じたこともありましたね」
壁にぶつかる渡辺を支えていたのが、家族の存在だ。三和銀行時代の同僚だった妻・麻里さんは船橋屋に入る直前の'93年6月に結婚し、夫の浮き沈みを近くで見続けてきた。長男・大起さん(21)から見ても「母は細かいことに気を配れる思いやりあふれる人柄。父や僕ら子どもたちを力強くサポートしてくれる」と語るほど重要な役割を担ってきた。
その妻が、このころ最寄り駅まで夫を送る車中でふと、「このままじゃ、死ぬな」と感じたという。
渡辺は、後に妻にそう思っていたと言われて絶句したと話す。
「自分の強引なやり方で、気づいてみたら8割の人間が辞めてました。『俺って人望ないな』という自分への失望感が強くて、妻にしてみれば僕が毎日すごい顔をしているように見えたんでしょう。当時の自分は確かに『暴君』だった。『クズ』『だから、お前らはダメなんだ』と社員を罵倒することもしょっちゅうで、今、考えると自分自身が病んでいたんですよね」
他者も自らも傷つけて自分流を推し進める息子を、「後継者に据える」と覚悟を決めた父・孝至さんは黙って見守っていた。だが、2000年を過ぎたころ、「ISO9001(品質マネジメントシステムの国際規格)を取得する」と言い出した際は、さすがに大反対した。
そもそもISO9001というのは、信用力の高い第三者機関から受ける「この会社は恒常的に高い品質の商品を提供するシステムが構築できている」という事実認定だ。品質管理が可視化され、イメージアップにもつながる。ただし、取得へのハードルは非常に高い。くず餅の製造過程を例に取ると、小麦粉の練り方、水洗いの仕方、檜の貯蔵庫で450日熟成させるのに最適な温度、蒸し上げる時間、温度、切り方などさまざまな工程がある。
「俺ってダメな経営者だな」と感じた瞬間
職人たちは長年、これらすべてを『カン』でやっていたが、常に高いクオリティーの商品作りを目指すなら製造過程をマニュアル化し、『目に見える基準』が必要になる。そのためには、職人は1度も触ったことのないパソコン作業を覚えなければならず、データ入力作業の負担ものしかかる。「古い職人社会の船橋屋にそれを導入しても、社員はついてこない」と孝至さんが考えるのもムリのないことだったのだ。
「それでも雅司は『絶対にやる』と一歩も引きませんでした。入社して7~8年間は私の言うことを聞き入れてきた息子が反発したのはあのときが初めて。親子の冷戦は何週間も続きましたが、そこまでしてもやり遂げようとする本気度がわかってきて、私も折れた。『じゃあ、やってみろ』と言ったんです」
7代目は説き伏せたが、古参社員は黙っているはずがない。彼らの反発は凄まじかったという。
「余計な仕事を増やして!」
「長年の職人の仕事をバカにするな」
捨てゼリフを吐いて去った者は1人や2人ではない。船橋屋はまさに嵐の中にいた。
渡辺は神妙な面持ちで振り返る。
「僕なりに会社のためを思って提案したことでした。辞めていった人もいたけど、父が一緒に勉強を始めてから、ついてきてくれた社員もいて、彼らの涙ぐましい努力の結果、2003年にISO取得が叶いました。会社としては一体感を持てたし、品質面でも大きな成果を得られましたが、まだ何かが足りない。そんな感情が拭えませんでした」

企業体質の改善のため、強い意志で改革を進めていたが、渡辺の高圧的な管理は社員を萎縮させ、社員自ら考えて動くことができない組織となっていた。昔からいる職人が新人と口をきかないような古い体質に、トップダウンで対抗している状態だった。
この現実に渡辺自身も迷い苦しんでいたとき、欠けたピースに気づかせてくれる出会いがあった。株式会社アッシュ・マネジメント・コンサルティングの代表・小川晴寿さん(50)である。
小川さんは、初対面の様子をハッキリと記憶している。
「2007年2月に船橋屋を訪ねて、専務だった渡辺さんとお会いしました。電話対応をされている間、ソファで待っていましたが、終わった瞬間、『ところで、キミは何ができるの?』といきなり言われて驚いた。『上から目線』の発言が強烈な印象に残っています」
この日は数時間、話して打ち解け、4月からの契約が決定。小川さんは店長会議に参加する機会を得た。
「会議での高圧的な態度も引っ掛かりました。ベテラン女性店長が問いかけに反応できなかったのを例に挙げ、『あいつら何もできないでしょ』と専務室で言うので、私は『ひとつ申し上げてもいいですか。いい会社を作ろうと思うなら、社員に〈あんたら〉とか〈あいつら〉とか言うのはやめたほうがいいです』と忌憚(きたん)なく申し上げました」
コンサルなんて口ばっかりだろうと思っていた渡辺は衝撃を受けた。
「穏やかな口調で、『会社を動かしているのはあなたですか? 今のポジションはご自分で獲得したわけじゃないでしょう? そんな言い方をしているうちは会社はよくなりません』と言われて、本当にそうだなと思いました。銀行員時代に倒産していく企業を見てきた結果、『いい会社を作らなきゃ』『利益を上げなきゃ』とばかり考えて、周りが見えていなかったんでしょうね」
渡辺はふと中学生時代の自分を思い出した。将来を心配した親に強いられ、「成績を上げなきゃ」「期待に応えなきゃ」という義務感で押しつぶされそうになった経験があったのに、経営者になった今の自分はそうやって社員に大きなプレッシャーをかけている……。
「俺ってダメな経営者だな。欲の塊だ」
それを強く感じた瞬間だった。
意識改革のはじまり
渡辺は小川さんのひと言を機に「剛腕で統率力あるリーダー」をやめ「みんなと一緒に幸せになるんだ」「自分も社員も笑顔でワクワクしながら働ける会社にしよう」と意識改革を行う。同時に明確な目標も掲げた。
ひとつは、『日本でいちばん大切にしたい会社』の著者である法政大学・坂本光司教授に取り上げてもらえる理想の組織を作ること。もうひとつは、テレビ東京の番組『カンブリア宮殿』に出ること。それくらい社会的に意味がある会社にしたい。それを伝えると、小川さんは「願わなければ叶わないものですが、きちんと意識していれば、十分叶いますよ」と太鼓判を押した。社会にとって有益で社員全員がハッピーになれる会社を作るために、渡辺は突き進み始めた。

2008年の社長就任前後から、名経営者の書物を片っ端から読みあさり、禅や瞑想も体験。外部研修にも精力的に通うようになった。小野寺さんもその変化に驚かされたひとりだ。
「自己啓発や管理職セミナー、コスト管理の勉強会など『これはプラスになる』と思ったものは自ら参加して、確信を持ったものは、金に糸目をつけずに、われわれ社員にもすすめてくれました。私自身もいくつか行きましたけど、部下のまとめ方やいい組織作りに関して新たな気づきを得ました。『みんなでいい方向に進もう』と励ましあいながら乗り越えるような空気も生まれてきました」
高校時代から定期的に会っていた土屋さんも、親友からグチが消えたことに気づいた。
「僕も雅司と同じころ、似たような悩みを抱いていたんです。『社員が働かない』といった不満はお互いによく言い合ってました。それが社長になったころから考え方が変わってきた。『みんなの生活をよくしたいから頑張る』と前向きになったんです。その変化を間近で見て、僕自身もウチの社員に自分から『よく頑張ってるね』『残業してくれてありがとう』と歩み寄るようになった。それだけで会社の空気ってガラリと変わるんです。僕は雅司に大事なことを教えてもらいました」
渡辺の次なる一手は「新卒採用」の強化だ。かつての船橋屋は紹介で職人を雇い、技術を叩き込むという昔ながらのやり方だったが、若い力を借りてよりモダンな組織に飛躍しなければならない。そう考えて、大手就活サイトで社員を募集し、会社説明会を実施するようにした。
そういう形で入社した1人が、現執行役員の佐藤恭子さん(38)だ。2004年に入った彼女は、就活生時代に船橋屋全店舗を回って緻密なレポートを持参してきた伝説の人である。
「大学時代にバスケットボールに邁進していた私は大学への就職を考えていたんです。でもケガで断念せざるをえなくなった。就職先を考えたときに、私は歴史好きだったので『戦争を乗り越えた老舗で、地元の人に慕われている会社に入りたい』と考え、いくつかにコンタクトしました。
でも、会社説明会に松葉杖姿で参加する私を見て『そういう状態なら事前に知らせてくださいよ』と怒鳴られたりした。そんなとき、当時専務だった渡辺だけが『学生時代に頑張った証だね』と言ってくれたんです。就職氷河期のなか、『この人の下でどうしても働きたい』と思った私は、松葉杖で船橋屋の全店舗を回り、調査レポートを作って最終面接に臨みました。採用に至り、本当にうれしかったですね」
けれども、佐藤さんの入社当時は社内の組織に古い体質が残っていた。新人の彼女自身も靴がなくなる、あからさまに悪口や陰口を言われるといった昼ドラのような嫌がらせを受けたという。
「入社した4月のうちに、会社を辞めたいと思ったんです。でも、私が嫌がらせを受けていると知った社長が、夕礼で『新人をいじめるなんて、どんな会社だ!』と注意してくれたと知って、組織が変わっていくことを信じて残ることにしました」
“リーダーズ総選挙”での変化
雰囲気が明確に変わり始めたのは、佐藤さんも参加した「組織活性化プロジェクト」が発足した2007年ごろ。新卒採用の際に、現場の部課長クラスを面接官にすることで、「自分が選んだ子が採用されてうれしいし、新人を大事にしなきゃいけない」という意識が生まれたという。居心地のいい会社へと進化を遂げたことが学生にも広まり、近年は数名の採用枠に1万7000人ものエントリーが来るようになった。今や勤務するのは、パートも含め200人超。渡辺が船橋屋に入ったころに比べると3倍近い規模に拡大している。
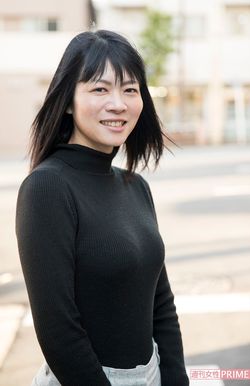
佐藤さんが執行役員に選ばれた2015年の「リーダーズ総選挙」も革命的な試みだ。すべてを社長が指示するトップダウン型組織ではなく、社長が掲げたビジョンをみんなが共有して働く組織にするために、あえて踏み切ったのだ。
正社員と勤続5年以上のパートに匿名で投票してもらった結果、組織のナンバー2のポジションに選ばれたのは、33歳の若い女性。これにはショックを受けた年配男性社員もいた。小野寺さんは彼らの思いを代弁する。
「佐藤がズバ抜けて優秀なのは入社前からわかっていたので、たくさんの票が集まったことは納得したと思います。ただ、古参の社員は『自分にはこれしか票が入らなかったのか……』とガッカリした。多少難しい空気が流れたのも確かです」
一方で、佐藤さんがナンバー2になったことで、「女性が働きやすい会社にしたい」という機運が高まった。産休・育休を取得して復職する社員も出てきた。「努力次第で自分の考えが反映される」という希望を持って働くスタッフも目に見えて増えた。彼女の抜擢が古い体質が残っていた船橋屋に新たな風を吹かせたのは間違いない。そこも渡辺の狙いどおりだった。
「僕の考えをしっかり理解してくれている佐藤が、リーダーとしてみんなを引っ張り、新しい取り組みや人事・組織運営・そして商品開発など多彩なジャンルで活躍してくれています。5代目の妻だった曾祖母が戦火から守ってくれた『くず餅乳酸菌』を抽出してサプリメントや化粧水なども開発していますが、それも佐藤主導で進めてくれている。僕が強引に引っ張らなくても、会社は回る。それが今の船橋屋なんです」
★ ★ ★
こうした改革と努力の結果は商品にも表れ、船橋屋は2018年8月にはJR東日本おみやげグランプリで「元祖くず餅 カップくず餅」が総合グランプリに輝くに至った。「亀戸天神の船橋屋」から「東京の名物を売る名店」へと変貌を遂げたことが広く認められたのだ。「くず餅プリン」などの新商品もヒットし、店舗も25まで拡大している。この10年で経常利益6倍という急成長ぶりに目をつけたテレビ東京は渡辺を『カンブリア宮殿』のゲストに抜擢。2018年11月に念願の出演が叶った。
渡辺が尊敬する坂本教授も、直々に船橋屋を訪れて調査を行ったという。「優れた会社と認めないと先生は来られません。そういう意味でも認められた証拠だと思います」と小川さんも力を込めた。これを機に坂本教授との親交が深まり、一緒に講演会も開催したというから、本人もうれしい限りだろう。
渡辺の2つの夢は実現したと言っていい。
そうやって会社を劇的に変えた父の姿を長男・大起さんは頼もしく感じている。
「父の経営者としての葛藤を子どもながらに感じることは多々ありました。以前は公私ともにうまくいかなくなると感情を露わにしたり、何かに当たることが結構ありましたが、経営者の集まりや研修会に参加することで『今までの自分を抑えて前向きになろう』と努力した。そうやって会社を大きくしたのは本当にすごい。215年の長い歴史と伝統を引き継ぎ、今の時代に合わせた改革をするのはそう簡単なことじゃない。僕も将来、家業を任せてもらえるような経営者を目指します」

船橋屋9代目を目指す大起さんが脳裏に刻みつけている父の口癖がある。
「経営者の身体は自分だけのものではない」
渡辺は今回の取材の最初に「健康オタクなんです」と冗談まじりに語ったが、それは単なる趣味ではなかったのである。
「今まで高野山の禅やインドのチェンナイでの瞑想などいろんなトライをしながら心身両面の健康を保ち、仕事に全力を注いできました。そんな僕を見て、妻があるとき、『パパの生き方がカッコよくなかったら、大起が跡を継ぎたいなんて言い出さないんじゃない?』と言った。自分は妻に仕事を認めてもらうのがいちばん大変だなと思っているので、その言葉はうれしかったですね。いずれは9代目を目指す息子にうまくバトンタッチしたい。親バカかもしれないですけど、息子は僕より経営者の資質があると思うので、期待したいです」
父の顔をのぞかせた渡辺は、後継者である息子が老舗を引き継ぎ、もっとワクワクするような店に発展させてくれることを心から祈っている。そんな日が訪れるまで、彼は日本中のくず餅ファンをアッと驚かせる斬新な取り組みを続けていくつもりだ。
取材・文/元川悦子(もとかわえつこ) 1967年、松本市生まれ。サッカーなどのスポーツを軸に、人物に焦点を当てた取材を手がける。著書に『僕らがサッカーボーイズだった頃1~4』(カンゼン)など。

