「私は生まれてきては困る存在だったんです」生後すぐに児童養護施設に預けられ、3歳で引き取られた先では養父のひどい暴力とギャンブル依存症でどん底の貧乏生活を送った。だが、そんなつらい境遇にこそ、「お客さまに喜んでもらうこと」に徹底的にこだわる経営者の原点があった。

某日の、昼12時半──。
名古屋市中区栄の宗次ホールで、観客たちが家路につこうとしていた。『いつまでも聴きたいギターの調べ』と銘打たれたランチタイムコンサートが、ちょうど終了したところなのだ。
「よくぞ人間に生んでくれた。それだけで幸せです」
宗次ホールは、『くらしの中にクラシック』を理念とするクラシック専門の音楽ホール。玄関には、観客ひとりひとりに「ありがとうございました」と丁寧に声をかける、きまじめそうな初老の男性が。
同ホールでは年間400回ものコンサートが開催されるが、ほぼ毎回、「いらっしゃいませ」と観客を迎え、「ありがとうございました」と言って見送る。
その様子を見ていたわれわれ取材陣に、この男性の秘書を務めている中村由美さんが、いたずらっぽい顔で語りかけた。
「宗次を知らないお客さまのほとんどは、ホールのスタッフと思うようです(笑)」
男性の名は宗次徳二(むねつぐ とくじ/72)。※「徳」は正しくは心の上に一が入ります
全国におよそ1300店舗を有し、店舗数が世界一として“世界でもっとも大きいカレーレストランチェーン”とギネス世界記録にも認定された『カレーハウスCoCo壱番屋』の創業者。経営を引退したのち、この宗次ホールを創設してオーナーとなった人物である──。
店舗数世界一のカレーチェーン網を作った男性の人生は、1948年、逆境のもとで始まった。石川県で生まれた直後に、当時は孤児院と呼ばれていた兵庫県尼崎市の児童養護施設に託されたのだ。
宗次さんが語り始める。
「私は、私生児として生まれました。この世に出てきてもらっては困る存在だったんです。だからよく言うんですよ。“よくぞ人間に生んでくれた。それだけで幸せです”と。私の人生はそこからのスタートでした」
3歳のとき、尼崎で雑貨商と貸家業を営んでいた養父母のもとに養子として引き取られた。裕福で幸せそうな一家の写真がいまも残っている。
「だから孤児院は“幸せな子だな”と送り出してくれたんだと思うんだけれども、養父が競輪に狂ってしまって。そこからが食べることにも事欠く、私の本当のどん底生活の始まりでした」
一家の大黒柱が収入のすべてを競輪につぎ込んだからたまらない。宗次家はみるみるうちに財産を失っていき、夜逃げ同然で岡山県玉野市に移り住むことになってしまった。
宗次さんは養父に手を引いて連れて行かれた同地の競輪場で、“車券拾い”をしたことをいまも覚えている。
競輪に負けた人たちが、ヤケになって車券を投げ捨てる。それを拾っては、当たり車券がまじっていないか確かめるのだ。
養母は魚の行商で必死になって家計を支えた。だが、手元に200円もあれば、夫はそれを握りしめ、競輪場へと向かってしまう。
1955年、宗次さん小学校1年のある日の夕暮れ、養父から棒でひどく殴られている養母を目の当たりにした。
「その日を境に母が家を出て行ってしまったんです」
父子ふたりだけの、極貧生活の始まりだった。
「電気代が払えないから、電気がなくてロウソクの暮らし。お米もないから自分で小麦粉を水で溶いて、塩で味つけし、焼いて食べたり。時には、食用になる雑草を食べましたね」
CoCo壱番屋興隆の原点
妻に出て行かれても、養父の競輪狂いと暴力は変わらなかった。ロウソクが照らす4畳半には質草にする家財道具すらもなく、リンゴ箱がテーブル代わりの生活だった。
やがて“シケモク拾い”が宗次さんの日課となった。
3キロほど離れたパチンコ屋さんに行き、床に捨てられたタバコの吸い殻を大人の足をかき分けて拾い、持って帰ってリンゴ箱の上に並べておく。養父がそれをほぐして、キセルに詰めて吸うのである。

「日が長い季節には、ついつい遊びに夢中になって(シケモク拾いを)忘れてしまったりする。そうすると叱られましたねえ。
素っ裸にされホウキの竹の柄で、ビシビシとミミズ腫れができるぐらい」
それでも養父を憎んだことはなかったという。
「父が唯一の家族だったことと、気が小さかったからか……。そうとしか思えない」
普段は不機嫌この上ない人が、息子が拾ってきたシケモクを吸うときばかりは満面の笑みを見せた。
そのうれしそうな表情、自分が提供したもので人に満ち足りてもらう喜び──。
「“この父親が喜ぶことを一生懸命にやろう! ”と。喜ばれたいという気持ちが強かったですね」
この人を喜ばせたいという思いがのちに開花し、CoCo壱番屋興隆の原点となっていく。
母の屋台を手伝う小学生
1957年、宗次さん8歳のとき、うれしい事実が判明した。2年ほど前に出奔した養母が名古屋で元気に暮らしていることがわかったのだ。
養父はこれ幸いと復縁。父子で岡山から養母が住んでいた名古屋の4畳半一間のアパートに転がり込んだ。
だが、ここでも養父のギャンブル依存は収まらない。養母は再び家を出て、サラリーマン相手の屋台を始めた。宗次さんは屋台の手伝いを決意する。
「土曜日の昼に小学校が終わると、バス代20円だか30円をもらって母親の元に行って、夕方一緒に屋台をひいて。母親とのふれあいがうれしくて、毎週(通って)ね……。深夜2時ごろ、屋台を片づけ、日曜日の昼にはカレーや善哉を食べさせてくれました。小学5年くらいまでかな、毎週手伝いを続けましたね」
中学時代も養父の競輪狂いが止まらずに家賃を滞納。そのたびにアパートを追い出されてしまい、名古屋市内を転々とした。
アルバイトを始めたのもこのころのことである。中学1年生の冬休みには米屋に泊まり込み、朝の6時から正月用の餅つきをして働いていたという。
高校は夜間高校を志望していたが、先生に言われるまま受けた愛知県立小牧高等学校商業科に合格。本人の意思に反して、全日制高校に通う身となった。
だが高校入学の手続きの段階で、衝撃の事実を知る。
学校に提出するために戸籍謄本を取り寄せたところ、それまで実の両親だと思い続けていたが、『養父・養母』との記載があった。そればかりか、誕生日が違い、それまで基陽と呼ばれていた名前までもが本名ではないことがわかったのだ。
「戸籍謄本を見て3つの発見をした人生でした。それも15歳でね」
それでも、養子であることが虐待の原因と思ったり、養父を恨んだりはしなかった。
「なにも思わなかった。ホントになんにも思わなかったですね。(名前や誕生日も)“あ、違っていたんだ”ぐらい」
宗次さん高校入学の直前に、養父の胃がんが発覚。わずか2か月後、57歳の若さで逝去する。死の直前まで病室のまくら元に競輪選手名鑑を持ち込んでは宗次さんに読み上げさせ、それを幸せそのものの表情で聴き入っていた。
ギャンブル依存からついぞ抜け出すことができなかったこの養父に、どれほど苦労させられたことか。
だが裸一貫から事業を立ち上げて株式を店頭公開するまでに至るその根本には、養父との生活で身につけた“つらさを克服すること”と“喜ばれることを一生懸命にやる”という精神が、間違いなく存在するのだ。
5千円で手にした宝物
高校入学直前、養母との暮らしが始まった。養父を失った宗次さんは、入れ替わるようにもうひとつ、心打たれる出会いがあった。クラシック音楽である。
「養母はとある会社の社員寮で賄いさんをしていてね。そんな母と同居するようになって初めて電灯のもとでの生活が始まりました。そんな高校1年の6月のことです」
入学以来、毎朝登校前に働いていた豆腐屋さんのバイト代で、同級生からテープレコーダーを買い取ったのだ。月々千円払いの5千円で手にした初めての宝物だった。
その日は部活後、飛ぶようにして帰宅、歌謡曲でもやっていないかと養母が手に入れた中古テレビをつけたがやっていない。NHKをつけてみると、教育テレビでNHK交響楽団が演奏していた。
「それを録音して寝て。翌朝、目が覚めるとすぐに再生ボタンを押して、2曲目に流れたのがメンデルスゾーンの『ヴァイオリン協奏曲ホ短調』。いまでもね、しばしば冒頭から涙が出てきますよ。
あのとき、テープレコーダーを買わなかったら。あるいは録音したとき、流れていたのが歌謡曲だったりメンデルスゾーンでなかったら。絶対、クラシックとは縁がなかったと思いますよ」
翌日から、全楽章を聴いてから当校するのが日課となっていた。
1967年、高校卒業後は、新聞の求人広告で見つけた不動産仲介会社に入社した。
コツコツとシケモクならぬ不動産情報を集め、“喜んでもらえることを一生懸命にやる”姿勢が功を奏したのか、毎月上位の営業成績を収めるほどに。入社3年もたったころには、土地を買ってくださったお客さまに、マイホームの平面プランを描いてあげたいと思うようになった。
「それで建築を学びたいと、大和ハウス工業名古屋支店に転職することにしたんです」
不動産業から夫婦で喫茶店経営へ
「私、会社に早く行っていたんです。狭い部屋でゆっくりしていられなかったから。そこにいた営業部隊をまとめる唯一の女性事務員。それが後に妻となる直美でした」
“コピーを取って”だの、“タバコを買ってきて”やらの雑用にも気持ちよく応じてくれる笑顔が魅力的な紅一点。
「気立てがよくて、元気で明るくて。2か月後に交際を申し込んだ。本人は相当嫌だったみたいですけど、強引でした、私(笑)」
“コツコツと一生懸命”という宗次さんの姿勢は、恋愛でも変わらない。
直美さんの誕生日には、大好きなヴィバルディの『四季』のレコードに“これは僕のいちばん大好きなレコードです。春になったらドライブしましょう”と書いてプレゼント、交際が始まったという。

「デートの帰り、家に送り届ける車中で“別れよう”と言われたことがありましてね。ここで降ろしたら終わってしまうと思って、彼女の家のまわりを車でぐるぐるまわって解放しなかった(笑)」
直美さんからの結婚の条件は、100万円の貯金をすること。それをわずか半年でクリアした。1972年、大卒初任給が5万円の時代の100万円である。
同年11月、宗次さん24歳、直美さん22歳のとき、めでたく結婚。直美さんは結婚を境に退職、翌年10月には宗次さんも独立して不動産仲介会社『岩倉沿線土地』を開業し、25歳にして経営者となった。
昭和40年代といえば空前の土地ブーム。事業はスタートから順調だったという。
「1棟750万円の小さな建売住宅を、4棟売りました。4棟で3000万円、粗利は2割5分ぐらいだったから750万円。いい商売でした、売れれば、ね」
だが、物心ついてから必死に生きてきた宗次さんには、お客さまが来店するまでの暇な時間がもったいない。
「それで妻に、“喫茶店でもやって日銭が入る商売をやってみない? 不動産と喫茶店の両輪でいこう”。そう話をしたら即座に“喫茶店、やりたいわ! ”と。じゃあと知り合いの不動産屋さんに電話して、2つと見ないで“ここでいいです”と決めて、喫茶店『バッカス』を始めたんです。1973年10月1日のことでした」
名古屋市西区郊外の、住宅と工場がまじり合った地区にあるマンションの1階、17坪の喫茶店。
成功への歯車が、ゆっくりと回り始めた。
「この商売にかけよう」と決意
『バッカス』は開店初日から終日満席のフル回転。1日の来店数は300名に上った。1杯のドリンクを楽しむために、お客さまがわざわざ自分の店までやってきてくれる。そのうれしさ、その活気。
スーツ姿で店頭に立ち、お客さまに「いらっしゃいませ!」と声をかけ続けていた宗次さんが、不動産業とは180度異なる、コーヒー1杯150円の客商売の魅力に気がついたのは、このオープン当日であったという。
「(開店祝いの)お花だけ持って帰る人もいましたけど、それでもうれしかったし、楽しかった。それと同時に不動産屋はどうでもよくなって、廃業しよう、この商売にかけようと、そう思ったんです」

翌日には、ポロシャツ姿でカウンターに立っていた。
お客さまを「いらっしゃいませ! 」と笑顔で迎え、サンドイッチの注文には辛子の有無までひとりひとり確認。最後のひと口まで具材がのっている、その気配り。
さらには専用カップを用意、マイカップでコーヒーを出すサービスも開始。傍らには、笑顔できびきびと働く、直美さんの姿。
そんな店が評判にならないわけがない。若夫婦がいきいきと切り盛りするバッカスの売り上げは徐々に右肩上がりに。
「帰り道くたくたになって踏切の遮断機前で夫婦2人して一瞬眠ってしまったり。お風呂は外釜で沸かすスタイルだったんですがお湯が沸騰する音で目を覚ましたり(笑)」
睡眠不足になるほどの激務ではあったが、1年後、宗次さんはさらなる展開に踏み出す。コーヒー専門店『浮野亭』の開店である。
開店資金1100万円の調達は、“私に任せて”の声とともに、妻・直美さんの担当に。以来、CoCo壱番屋の時代に至るまで、アイデアは宗次さん、資金調達は“金融機関からNOと言われたことがない”直美さんという、ツートップ体制になっていく。
「ところがねえ、この店がそれはヒマでねえ……(笑)。1年近くは資金繰りがものすごく大変でした」
CoCo壱番屋創業のヒントを得たのも、実はこの浮野亭だったと宗次さん。
「世の中には家から出られない人もいる。そういう人に喜んでいただこうと出前サービスを始めましたが、ライスメニューがなかった。それでカレーとチャーハンを用意したんです」
直美さんが作る、そのカレーが大評判に。気をよくした宗次さんが直美さんに3号店はカレーの専門店にしたいと告げると、間髪をいれず“いいじゃない! ”との返事。
「でも、カレーだけじゃ飽きられる。まだ見たことも食べたこともなかったけれど、吉野屋という店の牛丼が話題になっていた。だったらカレーと牛丼C&Gでいこうと。それで東京にリサーチに行ったんです」

「ここのカレーが1番や! 」
東京で真っ先に足を運んだのが、神田のガード下にあったカレーと牛丼の店舗S。
「ドアを開けた瞬間に目に飛び込んできたのは、おじさんたちがカウンターで丼を抱えている姿。“ああ、牛丼ってそういうものなんだ”と。しっくりこなくて、牛丼という選択肢が消えたんです」
その後も名門ホテルの3000円のカレーやら、10軒ほど食べ歩いたが、どんな有名店のカレーより、妻が作るカレーのほうが美味しかった。
「それで帰りの新幹線の中で、“カレーなら、ここ(うちの)が1番や、カレーハウスCoCo壱番屋”と、屋号がすんなり決まりました」
1978年1月、宗次さん29歳の年、バッカスから車で10分ほどの愛知県清須市(現在)西枇杷島町の田んぼに囲まれた一角に、カウンター20席のみのカレー専門店CoCo壱番屋(以下、ココイチ)第1号店をオープンさせた。
ところが“ここのカレーが1番! ”という自信のもとオープンしたはずのこの1号店、3日目からは閑古鳥が鳴き出した。
忙しさにかまけて、ぬるいままのカレールーを提供したり、ライス不足で時間がない昼休みのお客さまを待たせてしまったり。味とスピードが勝負のカレー専門店にあるまじき失態の数々が原因だった。
宗次さんは原点である“喜んでもらうのが第一”に立ち返ることを決意する。
サーモスタット付きのフライヤーや自動食器洗い機を銀行ローンで導入、接客に集中できる体制を整えた。
夫婦で“サクラ”をやったのもこのころの話だ。
「私は毎晩、妻は週に2~3回。店の前に車を着けて、店の入り口に2人で、次のお客さまが来店するまでずっと座って。そのまま閉店間近までいたこともありましたね」
だが、希望をなくしたことは1度もなかった。
「帰りの車中での会話は決まって“いずれ絶対によくなる”。いつ食べても美味しいし、店長も私の言うこと聞いて一生懸命サービスをしてくれていて。“このままやり続ければ大丈夫! ”。そんな自信だけは、なぜかありましたね」
自信を裏付けるかのように、気がつくとガラガラだった店内が6~7割方埋まるようになっていった。当時の目標は、月25日営業で月商150万円を達成したら2号店。
10か月後にはその目標を楽々クリア。翌年には2、3号店。さらに年末には自宅(2・3階)と店舗兼セントラルキッチン、そして本部を兼ねた4号店を出店した。
「4号店出店の前段階で喫茶店を売却、ココイチを10店舗出す目標を決めた」
あれから40年以上を経た今、宗次さんがこれまでの苦労を振り返り、笑いながらこんなエピソードを話す。
「300号店出店のその日、直美に“ママ、よくまあここまでやってこれたなあ。二人三脚でこれたからこそ。まあ五分と五分だったな”と。そうしたら、すかさず“なに言ってんの! アンタなんか2割でしょ! ”といきなり返されて。それ以来、妻が9の私1と言っているんです(笑)」
前出の秘書・中村さんも大きく頷く。
「直美らしい表現かも(笑)。でも、実のところ決定権を握っているのは直美ではありません。“パパの言うとおりにしなさい”って。本当にあうんの呼吸で仲よし夫婦だと思います(笑)」
宗次さんを“師匠”と仰ぎ、夫妻とは30年以上の付き合いという作家の志賀内泰弘さん(61)も、
「一見、はきはきと明るくて社交的な直美さんが引っ張っているように見えて、主導権を握っているのは宗次さんでしょうね。私生活ではお互いをからかい合う“夫婦漫才師のような夫婦”ですよ」
お客さま第一へのこだわり
家に帰れば、“漫才夫婦のボケ役”、そんな宗次さんの経営者としての一面を証言する人がいる。19歳でココイチ1号店に従事し、後に同社の社長を務め、現在は取締役会長である浜島俊哉さん(62)だ。
「(サービスでも売り上げでも)自分のこだわりを部下が理解し、実践しないと気がすまない。自分の考えが100%で、それ以外は全部排除。唯我独尊どころの話じゃない。代表権を持っていたころはそんな感じです。働く社員たちへの責任を感じていればこそ、だと思いますが」
中村さんも、現役時代の宗次さんの自覚と責任感をこんなふうに言う。
「お客さまのアンケートハガキを読んでいてこれは捨て置けないというコメントを読むと、“出かけてくる”と店に行きかける。10分後に来客の予定が入っていても、です。アンケートハガキを読んでいるとワナワナして、店への怒りが伝わってくる。お客さま第一へのこだわりがすごいんです」
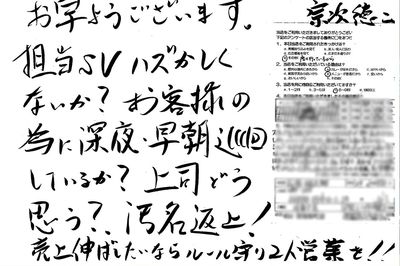
顧客第一、そして店へのこだわりは妥協を許さない。
その厳しさは社員だけでなく、自分自身にも向けられている。
毎朝3時55分に起床して、1日も休まず本部の周りを掃除。指導に出かけた店の駐車場にゴミでもあれば、指示より先に自分で拾う。社長みずからのゴミ拾いに、店長が真っ青な顔で慌てて飛び出してくることも珍しくなかったという。
現在の穏やかな佇まいからは想像もできない、仕事の鬼──。
それもまた、まぎれもない宗次さんの一面であった。
「量と辛さはお好みで」が大反響
さて、ココイチ成功の秘密を語るとき、画期的だった“ライスと辛さはお好みで”というカスタマイズ制ははずせない。子ども向けの甘口から“口中ボーボー、3口でシャックリが始まる”という1辛、超激辛の10辛まで選べる自由度である。

ほかにも話題を集めた名企画があった。標準量の4皿以上、1300グラムのジャンボカレーを20分以内で食べきったら、お代はタダというものだ。
これが口コミで大評判となり、挑戦者ばかりかマスコミまでが大挙して押しかけ大いに宣伝効果を発揮した。
こうした追い風を背景に、4号店出店とほぼ当時にフランチャイズ制を導入。翌1981年には独立志望の人たちを社員として迎え、店長として最短2年間の経験を積んでもらった後に独立開業を後押しする『ブルームシステム』をスタート。
この“のれん分け制度”によって、多くの人たちが独立、全国にココイチチェーン網を構築する原動力となる。
創業20年目にあたる1998年には500店舗を達成。同時に直美さんが社長となり、宗次さんは会長となる。その勢いのもと、2000年にはジャスダックでの株式公開を果たした。
困窮している人を助けるエンジェル
ところが2002年5月31日、宗次さんは驚きの行動に出る。
当時、53歳。経営者として脂がのりきる年代だというのに、なんとこの日を限りに役員を引退してしまったのだ。
「後継社長(前出・浜島さん)がよかった、知らぬ間に育ってくれていた。それ以外ありません。(辞めることに)未練も執着もなかった」
引退後、ある知人社長に“やり尽くしたんですね”と言われ、“ああ、そのとおりだな”と思ったという。
飲食業を志す人をはじめ、功成り名を遂げた名士として、宗次さんに憧れる人は少なくない。だがその陰には、経営の座を未練なく捨てられるほど、働き詰めの日々があったのである。
まさに、“やり尽くした”がゆえの引退。いまは株式も手放し、NPO法人『イエロー・エンジェル』の活動に明け暮れているという。

現在の宗次さんを、浜島会長は「現役時代と変わった」と話す。
「やわらかくなったというか丸くなったというか、なんていい人なんだと(笑)。僕らが一緒に働いていたころの宗次徳二とは全然違う。現役時代はピリピリとして、人を寄せつけませんでしたから」
NPO法人の目的を、宗次さんは助けを求める人々の支援とともに、前出の宗次ホールを舞台にしたクラシック音楽の普及活動であると語っている。
「(株式を)店頭公開してお金が入金された通帳を見たときに、“これは自分のお金じゃない。社会からの一時預かりとして社会に還元しよう”そう思った。それで、NPO活動を通して、いろいろなことに一生懸命な人、奨学金を求めている人、起業しようとしている人、困窮している人を助けるエンジェルになろうと思ったんです」
そんなエンジェルとしての活動のひとつが、著名演奏家への楽器の提供だ。
楽器の選定を一任されているというヴァイオリン修復家の中澤宗幸さん(80)が言う。
「特定の人に貸与というわけでなく、音楽を目指す人たちすべての人に、できる限り貸与してあげたいという姿勢です。音楽家にとって、料理人の包丁に当たるものが楽器。楽器が違うと音楽が違ってきます。宗次さんもそれがわかっていて、そんなやさしさからの行為だと思います」
日本が誇る名ヴァイオリニスト・神尾真由子、木嶋真優、辻彩奈などが使用するヴァイオリンも宗次さんからの貸与。ちなみに中澤さんによると、ヴァイオリンのお値段は「ピンからキリで、何十万から10数億円」だそうである。
こうした楽器提供は、一流演奏家以外にも。
宗次ホール1階の事務所奥には、愛知・岐阜・三重3県の中学高校の名前が記されたファイルがズラリと並ぶ。延べ1000校ほどの吹奏楽部に楽器を寄贈しているのだ。そのほか、東京都内の音楽大学にホールの寄贈も行っている。
また、宗次ホール前には黄色い花が植えられたプランターが並んでいるが、花がら摘みやここの掃除も宗次さんの仕事。毎朝3時55分に起床、1日も欠かさず、2時間かけて清掃活動を行う。

昼食には炊き込みご飯やカレーを作り、スタッフに振る舞うこともしばしばだ。
個人で行っているというこんなエピソードを前出の作家、志賀内さんが明かす。
「街でホームレスを見かけると、コンビニでおにぎりと温かい飲み物を買い、“大丈夫ですか?”と手渡すんです。袋の中に数千円入れてね。冬になるとマイナス10℃まで大丈夫という寝袋も、相当数配っています。ホームレスの人の名前までご存じですよ」
浜島会長が言う。
「人を寄せつけなかった宗次徳二と今の宗次、どちらが本当の宗次と聞かれれば、おそらく後者じゃないですか? 現役時代は作っていたんじゃないでしょうか、やっぱり」
経営者としての現役は引退したが、クラシック音楽普及も人助けも、お金持ちの道楽では決してない。
志賀内さんがこう続ける。
「リタイア後の片手間どころか、フル回転の毎日ですよ。取材を含め、講演は断らないし、宗次ホールでの年間400回のコンサートでは毎回、“いらっしゃいませ”と迎え、演奏を聴いて“ありがとうございました”と送り出す。毎朝3時55分に起きて、掃除を2時間して、それからですよ。現役時代と変わらず、毎日バリバリと働いています」
宗次ホールの役割を、宗次さんはこんなふうに言う。
「クラシックを広めたい。聴くとやさしい気持ちになるしね。年に1回か2回でもいいからクラシックを聴いてほしい。クラシックを愛好する人に悪い人は絶対いない。社会がやさしくなると思うんです」
10辛のカレーのごとくスパイシーだった前半生と、ライスのように、純粋な後半生。
カレーと同じく人生も、何ともいえない味わいを醸し出すのは、その絶妙のハーモニー──。
ライター。神奈川県出身。企業広告のコピーライティング出身で、ドキュメントから料理関係、実用まで幅広い分野を手がける。著書に『ダイバーシティとマーケティング』『幸せ企業のひみつ』(共に共著)
《撮影/伊藤和幸》

