
11月27日、滋賀県ひこね市文化プラザ。ステージには、大黒摩季率いるバンドメンバー。観客は総立ちで色とりどりのサイリウムを左右に振る。笑顔で歌うのは、あの名曲『ら・ら・ら』だった。
「聴くと元気になれる」名曲を次々と生み出した半生
この日は、全国47都道府県を巡る大黒摩季30周年記念ツアー『SPARKLE』のSeason IIの最終日。これまで訪れたのは34都道府県6公演、そして'23年1月14日からデビュー記念日となる5月27日まで残り13都府県(発表されているSeason IIIは24公演)を回ることになる。
大黒摩季といえば、'90年代初頭のミュージックシーンに忽然と現れ、『DA・KA・RA』、アニメ『スラムダンク』のエンディングテーマ『あなただけ見つめてる』、ドラマ『味いちもんめ』の主題歌『ら・ら・ら』などが大ヒット。
'95年7月に発売したアルバム『LA・LA・LA』は161万枚、同年12月に発売された初のベストアルバム『BACK BEATs #1』は、286万枚という驚異的なビッグセールスを記録した。
「聴くと元気になれる」
「自分を応援してくれる」
熱烈なファンも多い、まさに'90年代を代表するシンガーソングライターである。
デビュー30周年を迎えた大黒摩季。その半生とはどのようなものだったのか。
独立して15年、デビュー当時の事務所に戻ったワケ
東京・六本木にある大黒所属のレコード会社・ビーイング――。
笑顔で現れた彼女は、ものすごく気さくな人だった。話すのは苦手、と言いながらも、音楽への思いを熱く語る言葉は止まらない。彼女の口からまず出たのは、ニューアルバムについてだった。
「燃え尽きました。もう出し切っちゃって、ミイラみたいです。今回は、いつも以上に最初からマスタリングまですべての工程に自分が立ち合っているから、耳にタコができるくらい聴きました。ほかの誰にも聴こえないような音にまでこだわりましたからね」
大黒は'92年、ビーイングからデビューを果たし、多くの楽曲を発表したが、2001年にビーイングから独立。その後、2010年から病気療養のため活動を休止するも、2015年に楽曲提供を再開し、16年にはビーイングでの再出発を発表した。
「出戻ったビーイングには、'90年代を共にした精鋭たちがまだ残っているわけですよ、長戸プロデューサー(ビーイング創設者・長戸大幸氏)率いる野武士軍団みたいな人たちがね(笑)。
私は独立してからジプシーのようにいろんなメーカーさんと付き合ってきたんだけど、作品作りのクリエイティブに関しては、やっぱりビーイングが一番!!しつこくて厳しくて、引き出しがいっぱいある。うちのスタッフには、無謀な言い出しっぺの私にどこまでも付き合ってくれる持久力があるんですよね」
当初、30周年のツアーが終わって、このアルバムをリリースしたら、唄い手としての大黒摩季は隠居して、作家に専念するつもりだったと彼女は告白した。
「だから、歌も本気で最高峰を狙ったし、作家としても、『大黒摩季』に歌わせるのだったら、ここまでやらせようという作品を作った。『大黒摩季』にもうちょっと頑張らせる曲をわざと作家の私は作るわけです。
よくステージのMCでも、“私は死に損ないのゾンビ”って言うんですけど(笑)、“死ぬ気で生きる、って苦くて辛いじゃないですか?でも、“一度死んだ気で生きる”と全てが有難くて、そもそも歌えるだけで幸せ♪で楽しいわよ”と言ってるんです」
死んだ気――。そう、実は大黒は1度死んでしまうかもしれない状況に陥ったことがあったのだ――。
事務所の仲間とともに、かつての仲間のために作った新曲
ビーイングは、音楽制作会社・レコード会社およびアーティストマネージメントオフィスである。'80年代、LOUDNESS、TUBE、B'zがデビュー。'90年代初期からは、ZARD、WANDS、DEEN、T-BORAN、そして大黒摩季らが次々とデビューして大ヒットを記録した。
所属アーティストが“ビーイング系”などと呼ばれたこともあった。そんな古巣に戻ってきた大黒は、改めて音楽作りに没頭したと語る。
「戻ってきてすぐは少々気を使っていたんだけど、5、6年経ったら30年ずっといたような気になっちゃって(苦笑)。音楽がデジタル主流の世界になり、この業界に入る若い人が少なくなっています。
私には、クリエーターにお金を使えなくなったらクリエイティブは死ぬ、みたいな昭和の心情があって、どうしても“ここはやらねばならぬ”ということを曲げられない。だから最後の最後まで、ギリギリまで全神経使って作り上げる。
もはや“リスクは自分で取りますから”もう縮めるばかりは止めましょう!という感じで取り組みました(笑)」

大黒がデビューしてからの30年、音楽業界を取り囲む環境は大きく変わった。現在では完全なデジタルに移りつつある。
「しかもサブスクをスマホで聴くようになったでしょ?実際問題、音源の再現領域が広がったというのは確かにある。データの処理も早くなったしね。ならば郷に入っては郷に従うべきではあるけれど、でも只それだけだとプライドが許しませんと。
これまでの作品も、まるで出来上がったケーキにチョコレートをかけ直したようなのじゃ嫌なんですよ。だから、それはそれで平たいデジタル音にアナログ時代の音像を加えるにはどうしたら良いか?!とかエンジニアと研究開発したりと今回ほど制作にのめり込んだことはないと思いますね」
新曲の中に『君に届け』というタイトルの曲がある。
「New Songs盤は、いろんなタイプの楽曲を入れてバラエティに仕上がった。けれど、何かも一つ手応えが足りないんじゃないのと思った。そこで、この曲を最後の最後に急遽書き下ろしたんですね。
ビーイングによるビーイングらしい曲にしようと、ビーイングの、昔ながらの精鋭たちで作りました。私がもし30周年で死んじゃっても後悔がないようにね(笑)。
そして、ZARDの泉水ちゃんが生きていたら歌って欲しいなと。昔、彼女が「いつか私が詞を書いて、摩季ちゃんが曲書いて、二人で歌うライブやりたいね!」と言ってた約束。遅くなったけど守りたくて。
だから彼女に楽曲提供するつもりで作った曲。彼女が歌ったら、もっと甘酸っぱい感じになったと思うんだけど、私なのでちょっと塩辛くなったところがあるけど(苦笑)」
ZARDは、大黒と同時期に活躍したボーカルの坂井泉水を中心にしたユニットだ。『負けないで』や『揺れる想い』、『マイフレンド』などの大ヒットで知られる。坂井は、2000年以降、子宮筋腫などの病気を患っていたが、闘病中の2007年にこの世を去った。
大黒は、『揺れる想い』『負けないで』はじめ多くの曲にコーラスで参加。坂井とも親しく、坂井の音楽葬で大黒が人目を憚らず号泣したほどだった。
実像が見えない、昭和の「初音ミク」
大黒は、「謎のカリスマ歌姫」というような形容をされることが多い。デビューしてから数年は大ヒットを連発しながら、メディアなどへの露出はほとんどなく、ライブ活動もなかったためだ。
そのため、「大黒は1人じゃない。歌手担当、写真で顔を出すモデル担当、作詞・作曲担当とそれぞれ3人いる」とか「大黒摩季はコンピュータで作られたもので実在しない」などという都市伝説がまことしやかに語られたのだ。本人が爆笑しながら言う。
「考えてみれば初音ミクの走りみたいものかもね(笑)。ボーカロイド。昭和の初音ミク(笑)」
実際、当時の彼女はほとんど外に出ていない。作詞作曲からレコーディング、何から何まで1人でやっていた上に、3か月に1枚作品を出していたので、時間的にもメディアに出る余裕はほとんどなかったのだ。
「自分で書いて自分で歌ってダビングして…ですからね。はい、出来ました!そして、歌・コーラスやってる間にまた次の発注きました!って(苦笑)。
私、1年365日のうち、364日スタジオに入っていたのが3年間という記録があるんですよ(笑)。休みは元旦だけ。だから、カリスマなんて言われてもまったくピンとこなかった」
'90年代は音楽漬けで爆走し続けた
それでも大黒は、音楽漬けの毎日が幸せだったと言う。
「私はバックコーラス上がりで、会社がどうしても欲しいと手を伸ばして買ってくれた姫じゃない。叩き上げだから、いつこの日常を奪われるかわからない、という恐怖がある。
音楽がやりたいのに、食べるために仕方なくスーパーの品出し、交通整理や夜中のバイトをやったりしながらやっと掴んだんだ毎日だから。いいですよ、365日でもやらしてくださいよって。ハングリー精神なんかじゃない、ハングリーそのものだったの、私は」
自分が爆発的に有名になっていることを知ったのもひょんなことからだった。
「実家の母親から“マキちゃん、雑誌に写真載ってるよ”って電話が来て。調べたら同級生に私の子どものころの写真をスクープ雑誌に売った子がいたの(笑)。子ども時代の金太郎カットみたいなガッカリするような写真(笑)。
その見出しに『あの謎の大黒摩季の秘蔵写真をゲット!』って。その記事を見たときに、“え? 私って謎だったんだ”(笑)と知ったんですよ」
そうして彼女は、'90年代を爆走したのだった。

“秘密の部屋”は音楽への扉だった
大黒摩季(本名「摩紀」)は、北海道札幌市で生まれ育った。実家は、パン工場を営んでいた。祖父は、銀座の木村屋の暖簾分けをしてもらい、『札幌キムラヤ』を開業。祖父、父親、弟と3代続き、まもなく創業100年を迎える、札幌では最も古いパン工場である。摩紀が誕生して2年後、長男となる弟が生まれた。
「物心ついたらプリンスが出てきちゃったんですね。弟は跡継ぎだから、一族郎党挙げて大フィーバー。みんな興味の対象はいつも弟だった」
摩紀は幼いころから、癇(かん)が強いけど協調性のない、マイペースの子だった。何も言わずにすぐいなくなる。
「興味を持ったら突っ走るみたいな。とにかくよく失踪してて、いつも捜索され続けていたみたい(苦笑)」
摩紀が3歳の時、誕生日のプレゼントにアップライトのピアノを買ってもらった。
「それまでリカちゃん人形ひとつ買ってもらえなかったんだけど、母が東京のOL時代、ヴァン・クライバーンというピアニストのコンサートでショパンの英雄ポロネーズを聴いて、“いつかお母さんになったら娘にピアノでも習わせて、毎週聴けたらいいなあ”と思っていたみたい。
で、その夢を私に託して、母がパンの配達のついでにピアノの先生の家まで送ってくれて、終わったら迎えに来る、という感じで通いました」
それが音楽との出会いだった。そして5歳の時――。
「うちのお父さんがお金を貸した人が逃げちゃった。それでその人の家に行って持って帰れるものはないかと探したら、レコードしかなかった。
その人がロックファンで、レッド・ツェッペリン、ディープパープル、クリームとか70年代ロックのレコードを、よくわからないままお父さんが持ってきて棚に入れてたんです」
母の夢、借金のカタ、祖父の趣味が作った大黒摩季の下地
ある時、摩紀はピアノ曲のレコードと間違えてそれらのレコードをかけた。
「何、この汚い音(笑)。何でこんなに速く弾いてるの?」
と不思議な感覚を覚えた。母といるときは、クラシック、留守番をしている時はロック、そしておじいちゃんおばあちゃんが来ると演歌、テレビからは歌謡曲、というようなごちゃ混ぜの音楽が流れる幼少期を過ごした。
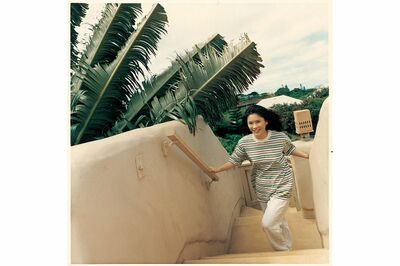
そして、もうひとつ幼い彼女にはこんな体験もあった。
「母方のおじいちゃんは、実は粋な人。実家には“開かずの間”があって、そこは屋根裏で“孫は絶対立ち入り禁止”という部屋。私は入ってみたくて仕方がなかった。
ある日、こっそり入ろうとしているのをおじいちゃんに見つかって、“あ、叱られる”と思ったら、“内緒だぞ。お前だけはいいぞ”と言って開かずの間に入れてくれたんです」
摩紀は驚いて目を見開いた。何とそこにはバイオリン、オルガン、サックスなどのあらゆる楽器が置いてあるではないか。いわゆる趣味の部屋だった。祖父は楽器が好きでコレクションをその部屋に集め、眺めたり、時に音を奏でたりしていたのだ。
それからというもの、摩紀は祖父の家に預けられるたびに、その部屋で遊んでいた。
「ママの夢のピアノ、借金のカタにもらってきたロックのレコード、おじいちゃんの屋根裏部屋というのが、幼い私に下地を作ったんですね」
小学生になると、ピンクレディー、石川さゆり、そしてニューミュージックのユーミンなどと出会う。
「あの頃の芸能界は本当に歌にあふれていた。だから急にテレビっ子になった。タレントになりたいと思ったことはないけど、何となく私は歌手にはなりたかったかな」
しかし、学校ではとにかく集団が嫌いな子だった。
「何でみんなで集まるのかわからなかった。むしろひとりで妄想してたりしてましたね。いつも跳び箱の中とか道具室とか用務員室とかに隠れているような子」
中学からは、札幌市内の私立中高一貫女子校に入学。
「音楽の時間も、クラスの中心にいる人だけが注目されるので、私が褒められたり目立ったりすることはなかった。でも放課後、勝手に音楽室に潜り込んでピアノで弾き語りをしていました。
ユーミンとか中島みゆきとか、シンガーソングライターが流行ってたから。『ひこうき雲』、『時代』、『恋に落ちて』なんかを中学生で歌ってました。まあ、そこに逃げ込んでいたんですね。でもちょっと歌がうまいってことがわかると、敵だった子たちが群がってくるのね。随分前から友達だったみたいな顔してね(笑)」
札幌で引っ張りだこのボーカルに
小学校高学年になると北海道にもFM局が増え、中学になるとテレビでも『ベストヒットUSA』が始まる。
「ホイットニー・ヒューストン、マライア・キャリー、マイケル・ジャクソン、マドンナと新しい音楽がどんどん入ってきた。札幌市内はレコード店は数軒だけだったのが、中古レコード店もできてワックワクでしたよ。そこで、15歳くらいに衝撃的な出会いがあったんです!」
それは、たまたまジャケ買い(ジャケットだけを見てレコードを買うこと)して出会ったアレサ・フランクリン。“レディ・ソウル”などの異名を持つ、ソウル・シンガーである。そこから彼女は、ソウルにも強く惹かれるように。
「かたや、レベッカからスライダーズ、モッズ、ブルーハーツ、カルメンマキさんとか、近隣の学校でロックのコピーバンドがいっぱい出てきてた。彼らの曲も全部歌えるようにしていました」
中学の終わりには、彼女は札幌のハコバン(店専属のバンド)のボーカルもやるほどに認められていたのだ。
札幌で様々なバンドのボーカルに参加
その当時、札幌の繁華街にバンドをやっている高校生たちが集まるビルがあった。
「近くに音楽の貸しスタジオがあって、順番待ちをしているバンドマンが2階のフロアにいっぱいたむろってた。そこの掲示板に“ボーカル募集”とか貼ってて、レベッカのボーカル募集ってあると、“あ、私やります”とバンドに加入したり、そこでは売れっ子になってました(笑)。
でも私にしてみれば、“私は、東京や世界を目指してるんですけど!”なんて生意気に思ってた(笑)。それでも彼らと一緒にやったのは、大人のバンドだけじゃなくて、同世代のバンドにも入っておきたかったから。レベッカはやりたかったしね」
当時はバンドブーム真っ只中。摩紀は、様々なバンドのボーカルとして歌い、札幌でも有名な存在になっていた。
「でも学校にバレちゃうとヤバいので、学校の近くではおとなしくしましたよ(笑)。え、部活動? パレー部でした。私の学校は、成績悪くても卒業する条件として部活動はちゃんとやるというのがあったから。ちゃんと部活にも顔を出していましたよ」

2年の約束で始めた東京での音楽生活
当初、摩紀は高校を卒業したら音楽大学に進みたいと思っていた。しかし、パン工場の経営には波があり、景気のいい時ばかりではなかった。ある時、母が言った。
「マキちゃんごめんね。4年制の音大に行かしてあげたかったけど、短大で我慢してくれる?」
2年だったら花の女子大生してたらすぐ終わっちゃうじゃん、クラシックは普遍な音楽だし今できることをしよう、と摩紀は考えた。
「だったら、自分でプロを目指して勉強すればいいやと思った。“東京に行きたい”と伝えると、一応儀礼的に反対されたけど、結局は“しょうがないな”と思われたみたいで。私は、2年間だけの約束で東京を目指したんです」
東京近郊にある叔母の家を拠点にして、オーディションを受けたり、レコード会社にテープを送ったりしながら、バイトをして過ごしたのだ。
そして1989年。テープを送っていたビーイングのオーディションの一次審査を通過した知らせが届く。
現在、大黒のチーフマネージャーを務める高野昭彦(67)は、その当時ビーイングの制作ディレクターを務め、テープ審査を担当していた。
「応募には5000本を超えるテープが届きました。それをディレクター達に振り分けて、毎晩、50本から100本聴くんですよ」
高野の分の中に、大黒から届いたテープが含まれていたのだ。
「オリジナル曲が3本入っていました。歌がいいなあ、魅力的だなあと。まずは会ってみたいと思いましたね」
2次審査は対面。20人ほどが残り、最終審査となる。とはいえ、それですぐさまデビューというわけではない。
「ビーイングのオーディションはデビューすることがテーマではないんです。合格した子は、そこから歌や作詞作曲を勉強しながらデビューを目指すんですね」
と高野。最終的な合格者は、大黒も入れて5組だった。そこで、審査した代表の長戸大幸(74)は彼女にこう言った。
「君はね、オーディション的にはまあまあ。君みたいな人は東京にいっぱいいるから。でも可能性はいささか感じている。うちのスタジオにはいろんなミュージシャンが出入りしてるから、コーラスなんかも勉強して磨いてみたら?」
大黒“摩紀”から大黒“摩季”へーー
この時のことを大黒はよく覚えていた。
「あの時、実はソニーさんとかビクターさんも受かっていたんです。ビーイングが一番小さい会社だったんだけど、長戸さんに会ったら、すごくいい目をしてたんですね。そして、ものすごく正直だった。その時の私には超面白そうに見えたんですよね」
ほかの会社はすぐにでもデビューさせるような言葉をくれたが、大黒は違和感を感じていたという。
「札幌では天才気分でいたけど、かと言って今すぐデビューできるとも思っていなかった。だから一番合点がいったんですね。もっと曲を作りたかったし、いろいろ吸収したかったので」
そこから、大黒の曲作りとバックコーラスの日々が始まったのだ。
「当時の自宅は、池尻大橋の6畳のアパート。部屋中が機材だらけで横になるスペースもなく、押し入れに足を突っ込んで寝てました(笑)」
曲作りの一方で、ビーイング所属アーティストのバックコーラスを務める。
当時彼女の担当マネージャーを務めた高野は、こんな記憶を話してくれた。
「おそらく1年目だけでも100曲くらい作ってたんじゃないかな。でも、なかなかデビューのきっかけがなかった」
そんな下積み時代、陽の目を見ない日々に飽き飽きした大黒は「勉強してくる」と言い残し渡米した。

同じころ、たまたまSILKというアーティストが歌った大黒の曲『STOP MOTION』(テープ審査に送った中の1曲だった)に長戸が注目し、急遽大黒のデビューが本格化。彼女は日本に呼び戻されたのだ。
1992年5月、大黒摩季は『STOP MOTION』で歌手デビュー。続いて9月に出た『DA・KA・RA』がCMのタイアップがつき注目を集め、初のミリオンセラー(100万超)を記録。その年の日本レコード大賞新人賞を受賞したのだ。
「それからですよ。3か月に1枚出していったのは。当時のレコーディングはテープでしたから作業が大変だった。やってもやっても仕事が終わらない日々が、1999年まで怒涛のように続いたんです」
“婦人科系の病気のバリューセット”と語る、身体の異変
2001年、「外の世界を見てみたい」とビーイングを飛び出した大黒は、音楽活動のさなか、2003年11月、友人の紹介で知り合った会社員の男性と入籍する。
2人は子どもが授かることを強く望んでいた。だが……。
彼女は、東京に出てきてしばらくたった20代のころから、生理不順をはじめとする体の異変を感じていた。
「私の場合、婦人科系の病気のバリューセットみたいでした」と大黒は妙な例えかたをしてみせた。
「卵巣嚢腫があって、子宮筋腫、子宮の内部にポコっておできみたいなのができて、子宮内膜に変異の物質ができる子宮腺筋腫、卵巣の周りに内膜症、その上、内膜も卵巣内もボコボコしてる、ハンバーガーにナゲットまでついてるみたいな状態(笑)」
歌いながら死なれたらみんなが困る
2010年には、音楽活動を休止するほどになる。
「その時は腹腔内全体に炎症を起こしちょくちょく高熱が出て死ねるかも、という状態だった。歩いてるだけですごい大出血。病院行ったら、腹腔内炎症、全部が機能不全になってた。おしっこの温度が42度、体内の熱がそれだけ高くなってたんです」
夫が彼女にこう言った。
「これは歌う歌わないのレベルじゃない。生きるか死ぬかの問題だ。昔のアーティストじゃないんだから、歌いながら死んだらかっこいいと思うかもしれないけど、そこに立ち会ったお客さんとスタッフは拷問だよ」
そして活動休止。'15年には子宮を全摘出。その後はアメリカの代理母出産も試みたが、'17年9月頃に送り出した、冷凍保存していた最後の受精卵でも妊娠には至らなかった。

不妊治療を終え、大黒は夫婦の形を見つめ直したと言う。
「彼が友達の赤ちゃんを抱っこして“こんな顔するんだ、愛おしいな”と思ったけど、ことあるごとにごめんねと思って生きていくのか、と考えた。2人でいて罪の意識を持ち続けるより、彼の別の幸せを心の底から応援する方が幸せで楽。そう思って'17年の暮れに離婚を決めました」
復帰へ背中を押してくれたのは──
2010年から6年間。大黒は療養のため休業した。
「2回目のオペの時は、まったく強い声が出なくなった。そのときに覚悟を決めて、もう歌い手は隠居だなって。
で次のオペの時はもっと酷くて、開腹手術の領域が広く(歌手にとっての)命の腹筋を縦に切ったのでファルセットさえキープ出来なくなった。子宮を全摘したことで空洞が出来るから、ゴルフで言えば、何を打っても「ファー!!」って感じでしたね」
つまり思ったように声を出せなくなっていたのだ。もう2度と大黒摩季として歌えないかもしれない――。そんな大黒の背中を押したのが、吉川晃司だった。
「もしや腐ってるんでしょ?」
「腐ってはないです。弱っているだけです」
「いいから来なさい。頼みたいことがある」
「いや、もう無理だと思います。全然歌っていないもん」
「お前は錆びない女だから大丈夫だよ。大黒摩季にしか出せない音があるだろ。それをやってみろよ」
「それがやれないから言ってるんです!!」
「いいからまぁやってみろよ」
スタジオに入り、恐る恐る歌ってみると、休んでいた分だけ声質はよかった。
そのとき、身体が「鳴った」のだ。
手術後に気付かされた「不調の原因」

ずっと歌ってなかったし、喋ってもいなかった。だが、いい音が鳴ると、身体その気になってくる。自分でもいい響きを感じていた。すると、「一発OK」が出た。
そして親友のボイストレーナーでもある原田ゆか(52)のアドバイスもあり、大黒は徐々に自信を深めていった。
「トレーニングし出したら、もともと体力はあったから、ガンガン行ける感じはした」
そして、手術前はいつでもどこかしら痛かったり、むくんでたりしていたのに、そんな症状が2年ほど前から一切見られなくなったのだ。
「不調はメンタルではなく完全に病気のせいだったんだなって。その病気の元を絶ったら整って来て、身体だけじゃなくて思考のスピードまで速くなった。
いい歌を歌うには、頭も心もスッキリしてないとダメ。ビブラートをかけるとかピッチの上げ下げ、ボリュームとか。すごく細かい作業で、やることはいっぱいあるから」
ツアーのコーラスにも参加している原田は、いつもすぐそばで大黒を見てきた。
「不妊治療では男性ホルモンと女性ホルモンを交互に投与するので、声域が変動しやすい。それが全摘して投与がなくなったこと、そして体幹トレーニングの効果もあったのでしょう。さらに精神的な理由もあって、声に変化をもたらしたのだと思いますね」
生まれて初めて自分の限界が見えた
そして、大黒はツアーの最中に「あれ?」と思うことが増えたらしい。
「よく“降りてくる”って言うじゃないですか。あれは自分がああしたい、こうしたいを超えて、何かに歌わされる感覚。それが増えたの。
だから、周りのミュージシャンがいいプレイをすると、それに乗っかって予想もつかないフレーズとかが出てくる。“あらやだ、私って天才?!”なんて(笑)。やろうと思ってもできない、何というか第六感みたいな。それがポツポツ出始めるとシメタものなんです」
記憶を辿ってみると、その感覚は病気が進行する前の十代のころにもあったらしい。
「札幌のころ、レベッカのNOKKOさんやっても、誰の歌を歌っても全部その人が鳴っているの。ホイットニー・ヒューストンもマライア・キャリーもなんでもカバーできた。どこまでもキーが上がる気がしてた。
それが東京に出てきてから、どんどんヘタってきた。それは全部病気のせいだったんですね。だから今のコンディションは最高!!ただそれだけに、今回のツアーの初日に生まれて初めて自分の限界が見えて、ものすごくショックだったんですよね」
限界とは何だろう。
「6月1日、私のホームの北海道・札幌でのコンサート。この時人生で一番いい初日だった。それまでは病気だったから、というのもあるんだけど、滞っていたものが復帰してからどんどん繋がってきた。
今、最高レンジのぶっちぎりくらいのところにいるんですけど、それが“ここらへんが私の最高値なのかな”と分かっちゃった」
それはスポーツ選手が「自分の限界を知って」引退を決める時のようだと言う。
「歌い手って、ほとんど運動能力なんですよ。“あ、ここなんだ!天井っていうか、限界って”というのが明確に見えたような気がした。だからすごい落ち込んだんですね」
「私、超越しちゃったかもしれない」

その1週間前に母親の納骨を済ませ、リード曲『Sing』のMVを母校で撮影したり、場所が北海道だったこともあり、人生を振り返ってしまったのだと言う。
「そのとき、これまでの唄い手としてのコースレコード(最高記録)がうっかり出ちゃったんですね。私、超越しちゃったかもしれないと。
すごく嬉しかったのと同時に、“あ、天井がここか”という。もうちょっとはできるかもしれないけど、10年後の40周年には朽ちるものなんだなと思った。その瞬間にガーンとモチベーションが下がったんですよね」
それでも、大黒は友人に誘われて北海道の森の中にあるトレーラーハウスで過ごし満天の星を見て、お酒を飲んでいたら開き直ったのだと言う。
「天井が見えたんだったら、そこにベタつきでタッチして“本当に限界ですね”というところまで行ってみようと。というか行ってみたいと思った。こうなったら自分を使い切りたいと。
それから毎回のコンサートが全力なんですよ。今日のコースレコードを毎回狙うなんて、この歳で身体的には地獄で、死んじゃうんじゃないかなと自分でも思うんだけど(笑)」
「生きる理由はここにある」
仕事では“最高レンジ”だが、プライベートでは、両親を見送り、自分の家族もない。そんな中、今年の正月は、仕事に逃避しないで、自分に決着をつけようとひとりで過ごしたという。
正月の3日。大黒は自宅のベランダで植木の世話をしながらブランチをしていた。突然携帯が鳴った。チーフマネージャーの高野だった。彼はこんなことを言い出した。
「摩季が歌う理由、歌い続ける理由を自分は聞きたいんだ。きっとファンも聞きたいはずだよ。もういいよ、世のため人のために作品を作らなくても。もう1回自分のためだけに書いてごらんよ。きっと摩季には、作れば、歌えば答えが見えるはずだから」
そう言われた瞬間、まるでダムが決壊するように、突然頭の中に言葉がとめどもなく溢れてきた。
彼女はすぐにピアノの前に座り、取り憑かれたように弾き語り、譜面を書いた。涙が溢れ出て嗚咽するほどだった。
ほんの1時間ほどで『Sing』という曲が誕生した。
そしてデモを録音してメールで高野に送ったのだ。
「摩季、この曲、響いたよ。きっとみんなの心にも響くよ」
高野はなぜ、そんな言葉をかけたのだろうか。
「彼女の最近の作品は、“大黒摩季”を背負い過ぎているような気がしてた。だから、そのフィルターを取り除いて素直に歌にすればいいじゃんと。これからはもっと音楽を楽しんで欲しい、心からそう思いますね」
――満たされない。諦めざるを得ないで生きてきた。なんで私ばっかり、と思ってた。
それが結果的に出てきた歌に答えがあったのだ。大黒は最後にこう言った。
「何だ、あったんじゃんって思いましたよ、生きる理由はここに」と。
〈取材・文/小泉カツミ〉

