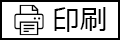年をとると不調や病気に悩まされ、のみ薬の量も増えていく。しかも女性は月経、更年期、婦人病など特有の症状や病気が起こりやすく、若いころから薬が手放せないことも少なくない。
ところが、「漫然とのみ続けると危険な副作用のリスクがある薬に要注意です」と内科医でアクアメディカルクリニック院長の寺田武史医師は言う。
女性ホルモンの薬に要注意
「まず気をつけたいのが、女性ホルモンをコントロールする薬。日本では低用量ピルやホルモン剤、排卵誘発剤などが普及していますが、それぞれ副作用やリスクがあり、長期間の服用には慎重な判断が必要です」
低用量ピルは、排卵を防いで月経の症状を緩和する効果があり、月経前症候群などさまざまな婦人病の予防、治療に有効な薬だ。
「低用量ピルに含まれるエストロゲンには血液を固まりやすくしてしまう凝固作用があるため、脳梗塞や心筋梗塞を起こす血栓症のリスクを高めます。
とはいえ基礎疾患のある人や喫煙者以外の発症リスクは低いので、医師の指示に従っていれば過剰に心配する必要はありません」

一方、更年期障害の症状緩和に有効なホルモン剤は、長期服用で高いリスクを招く。
「閉経が近づくと卵巣の機能が低下して女性ホルモンの分泌が減少します。するとホルモンバランスが崩れて不調を引き起こします。こうした更年期の症状にはホルモン剤によるホルモン補充療法が有効ですが、5年以上の長期服用で乳がんのリスクが高まるという報告も」
更年期の症状を緩和するにはホルモン補充療法以外にも、食生活や運動、生活習慣の改善が有効。服用の継続は、主治医と相談しながら慎重に行いたい。
また不妊治療で使う排卵誘発剤にも卵巣過剰刺激症候群という重い副作用が報告されている。
「不妊治療では1度に複数の卵子を採取するために排卵誘発剤を使って卵巣を刺激します。しかし刺激が過剰になると卵巣が腫れ、下腹部に激しい腹痛を引き起こす場合も」
不妊治療では主治医に不安や症状をこまめに伝えて、管理してもらうことが大切だ。
睡眠薬や痛み止め、身近な薬に潜む危険

実は日常的に使っている痛み止めや睡眠薬にも、種類によって強い副作用がある、と寺田医師。
「身近な薬で女性が乱用しやすいのが、生理痛や頭痛を抑える痛み止め。解熱鎮痛剤と呼ばれる薬で、種類は複数ありますが、なかでも強い副作用で知られるのがNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)と呼ばれる痛み止めです。
胃炎や出血性胃潰瘍を引き起こすリスクがあり、医療機関では胃薬が一緒に処方されます。しかしのみ続けるうちに胃薬の服用が面倒になって単独でのみ続け、ひどい場合は出血性胃潰瘍で黒い便が出たり、血を吐いたりすることも」
NSAIDsは、薬局でも簡単に手に入るため、間違った服用で副作用を引き起こすケースが後を絶たない。特に女性は生理痛や頭痛でNSAIDsに依存し、知らないうちに慢性的な薬物乱用頭痛にも悩まされている女性が多くいるという。
痛み止めが手放せないほど症状がつらい場合は、病気が隠れている可能性もあるため、まずは医療機関で医師の診断を仰ぐようにしたい。
「睡眠薬は身近な薬で、安全なイメージを持つ人も多いですが、種類によっては強い依存を引き起こします。
なかでも注意したいのが、入眠まで短時間で効果が表れるベンゾジアゼピン(BZ)系の薬。依存状態になった30代女性の患者さんは、薬がないと不安で落ち着かず、少し離れたゴルフ場にも行けなくなりました。
日常生活に支障をきたす睡眠薬依存は、家事と仕事の両立でストレスや不安を感じやすい30~40代の女性に多く見られます」
BZ系の薬は不安を和らげる効果もあり、急にやめると禁断症状でパニックを起こすケースもある。
また50歳以上の女性に増える過活動膀胱の治療薬にもさまざまな副作用がある。治療にはのみ薬だけでなく、骨盤底筋体操や肥満予防、生活習慣の改善も有効なので、自己管理も心がけたい。
女性がのみ続けると危険な薬《6選》
《1》ホルモン剤
女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロンを補充してホルモンバランスを整え、更年期障害の症状を緩和する薬。乳がんの発症リスクがあり、英国の研究では使用期間が4年未満の場合、未使用者に比べて1.74倍だが、5~9年になると2.17倍に跳ね上がると報告されている。
《2》排卵誘発剤
薬による刺激で卵巣が膨れ上がり、下腹部に違和感を感じる卵巣過剰刺激症候群を引き起こすことも。ひどくなるとお腹や胸に水がたまったり、腎不全や血栓症などの合併症のリスクも。
《3》低用量ピル
月経前症候群、月経過多、子宮内膜症、卵巣がんなどの予防・治療に効果的。しかし血液が固まりやすく血栓症を引き起こすリスクがある。吐き気やむくみ、乳房の張り、不正出血など多くの副作用も。
《4》睡眠薬
ベンゾジアゼピン系の睡眠薬には強い依存性があり、急にやめると不眠のぶり返し、動悸、発汗、息苦しさ、不安感、パニックを起こす。ふらつきや転倒、認知機能の低下といった副作用もある。
《5》痛み止め
NSAIDs系の解熱鎮痛剤は消化器への負担が大きく、胃炎、胃潰瘍、出血性胃潰瘍、十二指腸潰瘍のリスクを高める。乱用すると薬物乱用頭痛を引き起こす。
《6》過活動膀胱の薬
尿がたまりきらないうちに膀胱の筋肉が勝手に収縮して尿意を催したり、失禁したりする病気。治療薬のムスカリン受容体拮抗薬は、尿が出にくくなる、のどの渇き、便秘といった副作用がある。
医師と相談しながら断薬する努力を
「そもそも、どんな薬でものめば胃腸は荒れやすくなり、薬の代謝や排泄を行う肝臓、腎臓にも大きな負担がかかります。長期間のみ続ければ身体に思わぬ影響が及ぶことも想像に難くありません」
とはいえ、極端に薬を怖がってのまないのも危険、と寺田医師。

「医療機関は基本的に、必要な薬しか処方しません。自己判断で薬をやめれば、病気が悪化して命に関わることも。基本は医師の指示に従ってください。大切なのは声に出す勇気。薬を減らしたければ、主治医に減薬・断薬したいと勇気を持って伝えましょう。
そして薬をやめるための努力も必要。免疫力や自律神経に関わる腸内環境を整えたり、運動習慣や食生活を改善したりするなど、健康維持のための努力は不可欠です」
女性にはさまざまな症状や病気があり、一生かけて薬と付き合うことも多い。大切なのは薬を怖がることではなく、薬を賢く使いこなす知識を持つこと。
漫然とのみ続けるのではなく、自分の身体を管理する意識を持って疑問点や改善点は医師に積極的に聞き、減薬・断薬を目指してできることから実践したい。
教えてくれたのは……
アクアメディカルクリニック院長。精力的に情報を発信し、著書『なぜ、人は病気になるのか?』(クロスメディア・パブリッシング)が発売中。
取材・文/井上真規子