
“TODAY IS A GOOD DAY”
麻生圭子さんの好きな言葉だ。若いころは、明日は今日よりいい日にと考えてきたが、60代になり、明日ではなく今日をいい日にと考えるようになった。今日、今を幸せにと。
エッセイスト・麻生圭子さんの日課

琵琶湖畔に住んで8年目。目の前に広がる青く澄んだ湖は大きくたゆたい、季節や時間、天気によっても表情を変え、刻々と変化し、見ていて飽きることがない。朝に夕に、湖岸を散歩するのが、麻生さんの日課となった。
「広い湖を見ていると、心の澱が洗い流され、小さなことはどうでもいいと思えるんです」
と、遠くを見ながら言う。
湖をもっと感じたいとカヤックも始めた。インドア派だった人がすっかりアウトドア派に。着るものもジーンズにワークブーツ。ショートの髪には白髪も目立つ。それが、ナチュラルでカッコいい。

ほっそりとした身体からは想像できないが、麻生さん、結構たくましいのだ。住んでいる家は、古い保養所を夫婦でリノベーションしたもの。 天井をはがして梁を入れたり、床も壁も取り払い、張り替えたり塗り替えたり。夫の馬場徹さんは、一級建築士。馬場さんの指導のもと、ペンキを塗ったり、タイルを張ったりした。
「汚れが飛ぶから、作業着を着て、タオルを職人巻きにしてね」
と楽しそうに話す。
バスタブ、トイレ、洗面台、ランドリーなど水回りのものは、仕切りをつけずにひとつの空間に置かれ、清潔で、明るく開放的。この6畳ほどのスペースの床から天井まで、白いタイルを張るのは麻生さんの担当だった。
「だんだんできていくのを目で確認できるのは、うれしいもの。見えるものへのこだわりが強いのは、耳の問題があるからかもしれないわね」
実は、若いころから徐々に聴力が衰える耳の病気で、数年前には聴力を失った。そのために夫婦の確執もあったが、湖畔暮らしは心を穏やかにし、人生を再構築することとなった。2023年11月に上梓した『66歳、家も人生もリノベーション』は、66歳になった麻生さんの、住まいや暮らし、猫との生活などを、美しい写真とリズム感あふれる文章で描いたエッセイ集だ。
17歳のとき、養女と知らされパニックに
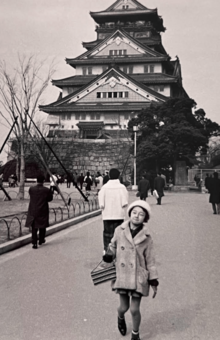
麻生圭子さんは、1957年に大分県で生まれ、東京で育った。両親は音楽好きで、お父さんの生家にはピアノがあり、蓄音機でレコードを聴いていたそう。お母さんは歌が好きで、上手だったとも。そんな両親のもと3歳からピアノを習い、上達も早かった。絶対音感があり、感受性が豊かで、小学校の高学年では音大の先生について特別教育を受ける。
「私も両親も、音楽学校に行くのは、当然のことと思っていたんです」
音大の附属高校に入るが、心を病み、学校に行けなくなって、中退。
「17歳のとき、麻生の親は本当の親ではない、私は養女だと知らされたんです。戸籍謄本を見せられて、おばさんだと思っていた人が実母で、いとこは本当の姉たちだと」
麻生家には子どもができず、妻の姉の子どもを養女としてもらった。それが圭子さん。事実を聞かされた多感な少女は、混乱し、苦悩し、自分の出自を憎む。ひきこもり、自傷行為に走ることもあり、学校をやめる。その後も悩まされることになるパニック障害やうつ病はここから始まった。さらに、
「圭子にはかわいそうなことをした」
と言ってくれていた養父は、入退院を繰り返し、麻生さんが21歳のときに他界した。
傷心の日々を癒してくれたのは、音楽だった。
「音楽があるから生きられた。音楽が救ってくれたんです」
その後、大学入学資格試験に合格し、
「絵が得意だったので」
と美術大学に進学。同時にNHKの音楽オーディションにも受かり、芸能活動も始める。多感な少女は多才でもあったのだ。シンガー・ソングライターを目指して作詞作曲をし、NHKの音楽番組にもレギュラー出演していた。
22歳で結婚。人生をリセットしようと、大学をやめて専業主婦になった。
「相手は優しい人でした」
だが、彼は仕事が忙しく、麻生さんの情緒は不安定で、心の隙間を埋めるように猫を飼い、可愛がる。

「オスのシャム猫で、私の心に寄り添ってくれる猫でした」
以来、猫派になる麻生さんだが、結婚生活は3年で終止符を打つことに。
そして1人ドイツ・ベルリンに遊学。壁が壊される前の、陸の孤島だった西ベルリンで10か月ほど過ごしながら、日本語で文を書き、歌詞を書いていた。
名プロデューサーの目にとまり、作詞家に

帰国後、ホテルのテレックスでアルバイトをしながら、歌詞をノートに綴り続けた。
「私が好きなレコードを作っていたプロデューサーに電話し、そのノートを見せたんです」
これがきっかけで、そのプロデューサーがほかの人を紹介してくれるなどして、作詞家としての道が広がっていく。
このころ、沢田研二などのバンドで、ベーシストやアレンジャーとして活躍していた音楽プロデューサーの吉田建さんとも知り合う。吉田さんは、当時の印象をこう話す。
「麻生さんと出会ったのは、'80年代の初めでしょうか。彼女は新人の作詞家で、目元が涼しげなお嬢さんという感じ。おしゃれのセンスもよく、“春”というイメージでした」
一緒に楽曲を作ることは少なかったが、よくスタジオで顔を合わせた。映画を見に行ったこともあり、
「映画の後、食事をしながらおしゃべりをしたのですが、自分の美意識をしっかり持った人だなと思いましたね」
と、吉田さん。
そのころは、プロデューサーの注文に応じて、作詞・作曲し、アイドル歌手が歌うという時代。吉田さんは、麻生さんが注文に応えるためにかなり無理をして歌詞を書いていると感じたそう。
「そんな呪縛から解き放ってあげたいと思い、この歌手はあなたの目にどう映る? あなたが感じたものを書いてごらんと話したことがあります」
そのアドバイスが効いたのか、麻生さんの肩の力は徐々に抜け、歌詞を提供する歌手とよく話すようになった。
「麻生さんは、10代だった私の目線まで下りてきてくれて、いろんな話を聞いてくださったんです」
と言うのは、歌手でタレントの浅香唯さん。
「私の言葉にできない気持ちも酌み取って、歌詞に書いてくださいました」
浅香さんのヒット曲『Believe Again』『セシル』などは、そうやって生まれた。35年も前のことを、浅香さんははっきりと覚えている。
「レコーディングには必ず来て、歌詞を曲にのせやすい言葉に変えてくださったこともありました。いつも、すごく褒めてくださったんです。うれしくて、調子に乗って歌いました(笑)」
麻生さんの書いた歌を、今も大切に歌い続けている。
「麻生さんは年上なのに可愛らしくて、憧れであり目標なんです」
浅香さんのほかにも、小比類巻かほる、小泉今日子、吉川晃司、徳永英明などのヒット曲を多数手がけ、'80年代のアイドル歌手全盛期の一翼を担ってきた。

難聴が進み、作詞家からエッセイストに転身

しかし、耳の聞こえが悪くなり、音楽に携わることを断念する。
若いときから徐々に聴力が落ちてくる、若年発症型両側性感音難聴という耳の病気で、ドラマ『silent』で目黒蓮扮する聴力を失った男性と同じ病気だ。麻生さんの場合は、高い音が聞こえなくなり、音楽を聴いていても、高音域になると音が消え、低音になるとまた聞こえてくる、高音急墜型感音難聴でもある。
10代のときから心の病と闘い続けてきた麻生さんにとって、救いは音楽だった。音楽が、気持ちを落ち着かせてくれ、助けてくれたというのに、そのメロディーが聞こえなくなるとは、何という神様のいたずらだろう。音楽に関わることは諦め、エッセイストに転身。恋心を歌詞ではなく文に綴り、心のひだを鮮やかに描く。前出の吉田さんは言う。
「麻生さんが作詞家をやめたのを知らず、本屋で彼女の本を見つけて知りました。若いときからしっかり自分を持っていて、素養がありましたから、エッセイストになったのは、ごく自然だと思います」
このころは軽度難聴で、高い音域は聞こえないものの会話は普通にでき、文章を書きながら、コメンテーターとしてテレビ番組にレギュラー出演し、ラジオにも出ていた。
「番組中に流された虫の音が私だけ聞こえずに困ったことも、発音があいまいな相手の話が聞き取れなくて、ボケてごまかしたこともありました」
麻生さんの担当医・山崎博司先生が説明する。
「大人になってから徐々に進行する難聴の場合、屋内での一対一の会話は比較的できるため、周囲が難聴に気づかないことがよくあります。屋外や騒がしい場所での聞き取りや複数人の会話は難しくなりますが、本人は聞き取りにくいことを言い出せず、孤立することが少なくありません」
難聴がゆっくり進行

難聴はゆっくり進行し、高い音から失っていったが、周囲に気づかれることなく仕事を続けた。
「聞こえない音は、相手の唇を読み、表情や話の流れで予測していたので、脳はフル回転、すごいストレスでした。大声で叫びながら運転して帰ることもありましたね」(麻生さん、以下同)
つらい気持ちをほどいてくれたのが、猫。ポルクという名前のヒマラヤンの、自由気ままなふるまいに“まあ、いいか”と思えることも多く、張りつめていた気持ちをかなり楽にしてくれたようだ。そのころ知り合ったのが、今の夫となる馬場さんだ。
「ポルクは膝にも乗ってこない猫なのに、彼にはすり寄って、懐いたんですよ」
1996年、結婚を機に夫の設計事務所のある京都に居を移す。もちろんポルクも一緒だ。京都では、マンションに暮らしながら町家探し。京都ならではの古い家を求めて奔走し、ようやく見つけた町家を夫婦でリノベーションした。使い込まれた古い木の家に、日本と西洋のアンティークが置かれた住まいは、陰影に富んで美しく、多くの雑誌に掲載された。そして、古刹や老舗を訪ね、京都の文化やしきたりを学び、次々とエッセイを著した。京都のこまやかな美に、着物姿の繊細な雰囲気がよく似合った。
結婚したころは支障なく会話ができ、テレビ出演も続けていた。しかし、年を追うごとに聞き取りが困難になり、番組を選びながら、少しずつフェードアウトしていった。夫との会話も込み入った話は避けるようになり、聞こえる音もさらに狭まった。50歳で聴覚障害6級と診断され、障害者手帳をもらう。
2014年、夫の仕事の都合でロンドンに移住。「18年住んだ京都を離れるのは、リセットするのによかったのかもしれない」と振り返る。最低限の家具と荷物を預けた以外はみな処分し、夫と2匹の猫と渡英。知る人のいない町で、テムズ川を眺めたり王立公園を散歩したり。アンティーク・マーケットにもよく通った。
「聴けなくなった音楽の代わりを、川の流れが、公園の花々がしてくれました」
しがらみを離れ、リラックスできる日々だったが、5年の予定が1年で帰国することになった。
琵琶湖畔に住み、人生をリノベーション

日本に帰ると、住まい探しがスタート。イギリスの湖水地方のような湖の近くに住みたいと、関東も関西も視野に入れて探した。たどり着いたのが、琵琶湖のほとり。湖は太陽の光を受けてキラキラと輝き、静かに波打ちながら広がっていた。水際から1、2分の廃屋のような小屋に案内された。蔦がからまるその建物が、麻生さんたち夫婦の目には、ビンテージ感が漂いカッコよく映ったのだ。
リノベーションに、約1年。基礎や屋根などはプロの手を借りたが、ほかは夫婦でつくり上げた。仮の住まいから日参して大工仕事や左官仕事に精を出し、最後の2か月は住みながらの作業となった。壁を塗り、ドアをつけ、空間がほぼできたところで、預けていた家具や荷物を入れ、イギリスから持ち帰ったアンティークも置いた。
京都やイギリスの家は暗く、差し込む光と織りなす影が美しかったが、この家はたっぷりと光が入り、明るく開放的。足場板を敷いた床も、壁に飾られた鹿の角も、ワイルドで大人のカッコよさがある。
「東京では上を目指して、京都では奥を見つめてきました。ここでは心を開放して生きていきたいと思うの」

その時々の生き方が住まいにも表れているようだ。
ここは京都から電車で40分ほどなのに、のどかでゆったりした雰囲気がある。目の前には大きな琵琶湖。その際まで水田がつくられ、古い遺跡が点在し、人々が脈々と生きてきた歴史も感じられる。
「ここに住んで、毎日琵琶湖を眺めていると、こうしなきゃという考えやしきたりが小さなことに見えてきて。自由になろう、自由になっていいと思えるようになったんです」
と、柔和な笑顔で言う。
実はこうやって会話ができるようになったのは、この春から。人工内耳の手術を受けたのだ。頭皮につけたボタンのような集音(マイク)装置が音を電子信号に変換し、頭蓋骨に埋め込んだ人工内耳から、聴神経に送られ、それを脳が音として認識する仕組みになっているそう。おかげで、会話ができるようになった。
映画をきっかけに手話を習い始める

ところで、前出の吉田さんと昨年LINEがつながり、スマホを通して会話するようになった。音楽業界で長年活躍してきた吉田さんだが、映画『コーダ あいのうた』 を見たことがきっかけで手話を習い始めたという。この映画は、耳の聞こえない親のもとで育った歌の大好きな少女の葛藤を描き、アカデミー賞を受賞したもの。
「僕は音の世界で生きてきたのですが、音のない世界で役に立てないかと手話を習い始めたんです。LINEで麻生さんが聴力を失ったことを知り、いろいろ話すようになりました。僕も年をとって聞き上手になったのかな(笑)」
若いころ音楽の世界をリードしてくれた吉田さんが、今度は聴こえない世界を理解しようとしてくれている。
「うれしかったです。映画『コーダ』を教えてくれたのも建さん。おかげで、夫と見ることができました」
この10年で聴力は著しく失われ、言葉での会話はできなくなり、猫の声も生活の音も聞こえなくなった。夫との日常のやりとりは読唇と表情を読みながら交わし、話し合いは筆談やスマホを介してするも、家の中からおしゃべりは消えていった。2022年65歳で聴覚障害は3級と診断され、人工内耳をすすめられた。
'23年春、人工内耳の手術を受ける。担当医の山崎先生は
「人工内耳手術で正常の聴力に戻るわけではありません。得られるのは、中等度の難聴に近い聞き取りです」
と強調する。
「健聴者の内耳の聞こえの神経は約3500個ありますが、人工内耳の電極は12〜22個。桁違いに少ないため、健聴者の聞こえとは異なります」(山崎先生)
言葉が金属音に聞こえる

麻生さんの場合は、言葉が金属音に聞こえ、
「グロッケンという鉄琴がしゃべっているような感じ」
だそうだ。それでも相手の声が聞こえ、言葉のキャッチボールができるようになったのは、うれしいこと。夫は、
「やっとひとり暮らしが終わった」
とつぶやいたそう。黙って食べ、黙って過ごすのは、ひとり暮らし同然。会話のない生活は、聴力を失った麻生さんだけでなく、夫も耐え難かったのだ。
「中途失聴の患者さんは、音や声の記憶が残っているため、人工内耳で特徴をとらえると、脳から記憶が引き出されて、昔聞いた音らしく聞こえる現象が起こります」(山崎先生)
秋、虫の音が聞こえた。子どものころ聞いた記憶があったのだ。
「これなのか、かつてテレビ番組で聞こえなくて困ったのは」
と思い出した。一方、失聴してから流行った曲は、曲として聞こえない。
「音楽は記憶で聴くけれど、人工内耳には音程がないので、聞いたことのない曲は聞き取れないんです」
やっぱり音楽が楽しめないのは、寂しいこと。
「でもね、猫の声が聞こえるようになったんですよ。車の中で会話もできるようになったから、ドライブも楽しめるようになりました」
聞こえた猫の声は、黒猫の“りん”。ロンドンまで一緒に行った2匹の猫を2020年に相次いで失い、身代わりのようにりんが来た。子猫のときに近所で震えていて連れ帰ったりんの声をようやく聞いたのだ。
そしてこの秋、ビーグル犬の“ジンジャー”が家族に加わった。まだ子犬のジンジャーの無駄吠えがうるさい。りんの鳴き声もうるさい。
「うるさいのがうれしい!」
と笑う。
今も定期的に病院に通いながら、人工内耳の調節をし、人工音を受け入れるための心療内科にもかかっている。脳が記憶の音を取り戻し、人工音に慣れるためにはもうしばらく時間がかかりそうだ。
琵琶湖にカヤックを漕ぎ出し、沖に出ていく。水鳥が飛び交い、魚が近くを泳いでいく。明け方の湖、青空の下の青い湖、夕焼けの空と湖……、美しい自然に見とれながら、360度水のパノラマに、心を開放する。
「耳が不自由なのも、時々うつになるのも、私の個性。これでいいんだって思えるんです」
琵琶湖のことを、マザー・レイク、母なる湖というそうだ。
毎朝、琵琶湖畔をジンジャーと散歩するのだが、途中までりんがお供をすることもある。時には、ジンジャーを連れて山歩きにも出かける。
トレッキングシューズを履いて、リュックを背負って。ジンジャーの息遣いが聞こえる。鳥の声も、枯れ葉を踏む足音も、聞こえる。すっかりたくましく、アウトドアが似合うようになった麻生さん。
TODAY IS A GOOD DAY。
新たな聞こえとともに、人生のリノベーションは、今を大切に続いていく。
<取材・文/藤栩典子>

