
1日だけで終わるはずのバンドだった。
1978年12月23日。ロックの聖地とも呼ばれていた東京・霞が関の久保講堂に、お祭り気分で集まった17人の若者たちがいた。その中心メンバーで、当時は高校3年生だったギタリストの吉田健二は振り返る。
寄せ集めバンドの17人目のメンバー・杉山清貴

「僕の兄がフルハウス(後のエイプリルバンド)というバンドのベーシストで、久保講堂でコンサートをやるから、おまえらが前座をやれって言われたんですよ。で、自分のバンド仲間に声をかけると、暇な連中がいっぱい集まってきたんですけれども、ヴォーカルがいなかった。それなら“ダメ元で1年先輩の杉山君にお願いしてみよう”ということになって、頼みに行ったら“うん、いいよ”って、杉山君はあっさり引き受けてくれたんです」
こうして寄せ集めバンドの17人目のメンバーになったのが、地元・横浜のライブハウスでアルバイトをしていた杉山清貴だった。
「僕らのまわりでいちばん歌がうまいのは杉山君でしたからね。彼が入ってくれたら何の心配もいらなかった。ただ、1回で終わるバンドですから先のことなんか考えていなくて、バンドの名前も面白ければいいだろうって、『きゅうてぃぱんちょす』に決まったんです」(吉田)
オープニングアクト(前座)とはいえ、きゅうてぃぱんちょすのステージは会場を大いに沸かせた。
1日で解散するには惜しいパフォーマンス。祭りの余韻から覚めて日常に戻るメンバーたちの一方で、「もうちょっと続けようか?」と、自分の正直な気持ちに抗えないメンバーもいた。
杉山は言う。
「大学でもない、就職でもない、そのどちらにもはまりたくないヤツらが、将来はどうなるかわからないけれども、夢だけを追い求めて生きていきたくてバンドに残ったんです」
それから4年半後。きゅうてぃぱんちょすは『杉山清貴&オメガトライブ』と名を変えて、日本の'80年代シティロックシーンに鮮烈なデビューを果たすこととなる。
夢をペンからギターに持ち替えて

「おふくろが日本舞踊と常磐津のお師匠さんだったんですよ。家には毎日お弟子さんが通ってきていて、朝から晩まで、ちんとんしゃん、ちんとんしゃん……って」
杉山は'59年に横浜の磯子で生まれた。産声を上げたときから音楽は身近にあった。が、幼少期に受けた邦楽の洗礼は、必ずしも楽しい記憶ではなかったという。
「小学校に入るくらいまで三味線を弾かされましたけど、ビシビシ鍛えられて、もうイヤで、イヤで。子どものころは絵が好きで、漫画家になりたかったんですよ。石ノ森章太郎さんの『マンガ家入門』という本を買って、漫画を描く道具をそろえて、学級新聞に4コマ漫画を描いたりしていました」
小学4年生のある日。休み時間に同級生の漫画友達が似顔絵を描いていた。見たことのない4人の外国人。
「それ、誰?」
「ビートルズ」
「ビートルズって?」
「ウチにレコードあるよ」
遊びに行くと、友達の5歳上の兄がビートルズのレコードを貸してくれた。
「何のアルバムかは覚えていないけど、家に帰ってポータブルプレーヤーで聴いたら、今までに触れたことのない世界が瞬間的にバーンと広がるような衝撃が走って。それからは漫画も描かずにビートルズばっかり聴いていた」
ジョージ・ハリスンに憧れた理由

ビートルズの中でも、ジョージ・ハリスンに憧れた。理由があった。
「'71年にジョージがバングラデシュの難民救済コンサートをやったんです。世界で初めてのチャリティーコンサートですよね。それが映画になって、見に行ったら心を持っていかれた。ミュージシャンって、こんな大きなことができるんだと。ステージでジョージは白いスーツに赤いシャツを着てたんで、僕も映画を見た後、赤いシャツを買って帰ってきました(笑)」
お小遣いは全部ビートルズに注ぎ込んだ。レコードは海賊版まで買いあさる。歌詞の意味が知りたくて訳詞集も買った。それを読み込むうちに自分でも詞を書くようになる。さらに、ギターを買ったことで作曲に興味が湧いた。中学時代に初めて作ったオリジナル曲のタイトルは『ことほどさように』。
「ことほどさように考え抜いて、いま来た道を戻り行く……。全然ビートルズじゃない(笑)。僕らの世代はフォークも通ってきていますから、(井上)陽水さんや(吉田)拓郎さんの影響ですよね」
それでも演りたいのはビートルズ。中学2年でバンパイヤという名のバンドを結成し、ビートルズの楽曲をコピーした。杉山のパートはギター兼ヴォーカル。だが、
「ヴォーカルをやりたかったわけじゃないんです。聴きまくっていたからたまたま歌えたというだけで」
その“たまたま”が周囲には無二の才能に映った。高校2年のクラス替え。名簿順に着席すると、杉山の前に座っていた椎野恭一が声をかけてきた。
「LAMBで歌わない?」
椎野が所属していたラテン・アメリカン・ミュージック・バンドは、横浜で受け継がれてきたハイレベルなアマチュアバンド。そこでドラムを担当していた椎野は、筋金入りのロック小僧だった。
「生意気なことを言うと、すでに僕はライブハウスやイベントに出演させてもらったりしていましたから、この高校に自分の相手になるようなヤツなんていないと突っ張っていたんです。ところが1年生の11月に冷やかしのつもりで文化祭で見たら杉山が歌っていて……。
ビックリしました、歌のうまさだけでなく、そのころからオーディエンスを楽しませるエネルギーにあふれているというか、“ヴォーカリスト・杉山清貴”のルーツができあがっているような印象でしたね」(椎野)
LAMBのヴォーカリストとなった杉山は、椎野とともに地元のライブハウスに出演するようになる。高校を卒業するころには、杉山の澄んだ伸びやかなヴォーカルは地元のアマチュアミュージシャンの間で誰もが知るところとなっていた。
ポプコン連続出場からプロデビューへ
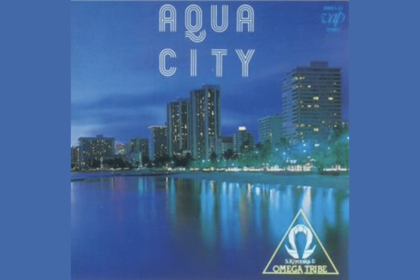
高3になり、自身の進路を考える時期。大学に行きたいとは思わなかったが、進学をすすめる母を心配させまいと受験に備えるフリをした。
「美大を受けると言って、学校が終わってから関内のYMCAで木炭デッサンとかやっていました。だけどYMCAの目の前がライブハウスで、結局そっちに入り浸るようになった」
音楽を続けたいという杉山の気持ちに、父は理解を示した。大学に行ったと思ってやるから4年間だけ好きにやってみろ─。警察官だった父は、わが子にも厳格だった。好きにやるなら自力で生活しろと、杉山は家を出された。
「高校在学中にアパートを借りて、卒業式もアパートから1人で学校に行きましたよ」
生活費も自分で稼ぐ。ライブハウスでのアルバイトは、夢を追いかけるとともに自活の手段でもあった。その時期に杉山はきゅうてぃぱんちょすに参加。ライブ演奏を録音したカセットテープを練習スタジオで流していると、それを聴いたヤマハのディレクターから声をかけられた。
「ポプコンに出てみないか?」
プロへの登竜門、ヤマハが春秋に開催するポピュラーソングコンテストへの出場がきゅうてぃぱんちょすの目標になる。そして、'79年秋の第18回大会で初出場を果たす。
「何の賞も取れませんでしたが、“もう少し頑張ればグランプリに届く”と、大人たちが持ち上げるもんだから、ガキは調子に乗って、また練習を始めるわけですよ(笑)」
翌年春の第19回大会。きゅうてぃぱんちょすは『GOSPELの夜』で見事入賞。レコードデビューの話も出た。しかし、
「デビュー曲ってバンドの代表作になるじゃないですか。僕らはロックバンドなのに、“ゴスペル”って違うんじゃねえのって」
続く第20回大会にも出場。その間にメンバーにも変動があり、2代目キーボードには後に東京藝術大学大学院を首席で修了する千住明が加わっていた。エントリー曲の『乗り遅れた747』は、同エリアのバンド仲間だった松井五郎の詞に杉山が曲をつけたもの。賞には届かなかったが、3大会連続でポプコン本選に出場したことで、杉山のヴォーカルに熱い視線を送り続ける人物が現れる。トライアングルプロダクション社長兼プロデューサーの故・藤田浩一氏だ。2年後、再び巡ってきたプロデビューのチャンス。
「藤田さんには自分がやりたい音楽があって、それを具現化するヴォーカリストを探していたらしいんです。だけど、バンドでやれないならイヤですって僕は断った」
高島信二(ギター)、大島孝夫(ベース)、西原俊次(キーボード)、廣石恵一(ドラムス)、そして吉田健二─仲間を置き去りにデビューなどできない。揺るがない杉山の意志に、藤田氏のほうが折れた。あらためてメンバー全員が藤田氏に呼び出される。そのときの記憶を、吉田がたぐり寄せる。
「藤田さんから最初に言われたのは、“君たち、髪の毛を切れ”だった(笑)」
こうしてメンバー全員がプロデビューのスタートラインに着いた。
藤田氏がプロデュースバンドのコンセプト
藤田氏がプロデュースしようとしていたバンドには明確なコンセプトがあった。楽曲は都会的な大人のロック。いわゆるAOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)で、作曲は林哲司、作詞は康珍化というヒットメーカーがデビュー曲を手がけることが織り込まれていた。
「本来ならきゅうてぃぱんちょすのオリジナル曲でデビューしたかったんですけど、林さんは『真夜中のドア』の作曲家、康さんは『バスルームから愛をこめて』の作詞家ですから、“絶対いい曲に決まってんじゃん!”って思いましたよね。それに、僕らだけではAORをつくるには力量が足りないとわかっていましたから、もうこっちから飛びついたような感じでした」
杉山の頭には、高校卒業後に新たなバンドを立ち上げて一足先にプロのドラマーとして活躍していた椎野の顔も浮かんだに違いない。
「僕のほうが先にライブハウスを卒業したというか、『バスルームから愛をこめて』でデビューした山下久美子さんや、吉川晃司さんなどのサポートメンバーとして、すでにプロの道を歩んでいましたから、杉山には“なにくそ”っていう思いも少しはあったんじゃないかな」(椎野)
共に追い続けてきた夢に、杉山もようやく手が届こうとしていた。だが、心の中には葛藤もあった。
「醒めていないと、あのデビューの仕方はできなかったと思いますよ」(杉山)
寝耳に水のバンド名にささやかな抵抗

杉山たちは困惑した。提示されたバンド名は“オメガトライブ”。名付け親は、藤田氏と親しかったハワイのカリスマDJ、カマサミ・コング。ギリシャ文字のΩには「最後・究極」という意味がある。TRIBEは「種族・人類」などと訳される。耳慣れないバンド名はメンバーたちにも抵抗があった。吉田は言う。
「きゅうてぃぱんちょすじゃマズいから、メンバーたちで考えて“ラグーン”に改名したんですよ。そしたら、いきなり事務所に呼ばれてオメガトライブに決まったと。本当に寝耳に水でしたね」
“オメガトライブ”はプロジェクトの名称ともいえた。杉山たちはプロデューサーの藤田氏が求める作品の表現者であり、創造者ではなかった。詞や曲だけでなく、音作りには超一流のスペシャリストが参加。レコーディングでの演奏はプロのスタジオミュージシャンが担った。
「自分たちで演奏できないのはショックでした。やらせてほしいと抵抗もしたんです。だけど、実際にスタジオミュージシャンの方々の演奏を聴いたら、自分たちとのレベルの差が歴然で、鼻をへし折られた気分でした」(吉田)
ヴォーカルに杉山の代役はいない。とはいえ、杉山も自由に歌えたわけではなかった。
「僕のロックヴォーカルに対して、藤田さんは“声を張るな、抑えろ”と。発声だけでなく、“君が好き”という歌詞があったら、“どういう気持ちなんだ、好きにもいろいろあるだろう?”とか、“この水は甘いって表現しろ”とか、無理難題ばかりで。1行歌うだけで1日が終わったこともあった。あの当時の音源を今聴くと、自分がふてくされて歌っているのがわかりますよ(笑)」
プロジェクトを成功させるための大人の采配。それを受け入れ、自らの欲求は封印した。結果的に、プロのミュージシャンとしてメンバーたちは磨かれていく。成長の実感があったと吉田は言う。
「コンサートになれば、スタジオミュージシャンの手を借りるわけにはいかないじゃないですか。“レコードと違う”とは絶対に思われたくないですから、音源を忠実に再現できるように、メンバー全員が寝る間も惜しんで猛練習しました」
レベルアップは杉山も同様だった。
「ふてくされながらも、藤田さんの要求を理解しようと歌っているうちにテクニックや表現力が身について、それが自分の個性になって……。そう気づいたのは、大人になってからですけどね(笑)」
'83年4月。プロジェクトは満を持してデビューシングル『SUMMER SUSPICION』をリリース。メンバーたちにとって想定外だったのはバンド名だった。藤田氏の一存で、“杉山清貴&オメガトライブ”に変更されていた。
「杉山君本人がいちばんイヤだったと思います。デビューが決まって、テレビ局やラジオ局に挨拶に行っても、杉山君は“オメガトライブです”って自己紹介するんです。ファーストツアーを組んだときも、自分から“杉山清貴&”と言ったことは一度もないんですよ」(吉田)
大人の采配に対する杉山のささやかな抵抗だった。とはいえ、デビュー曲がヒットする一方で、バンド名はしばしば“オメガドライブ”と間違われた。プロジェクトを売り出す商標として杉山清貴の名を冠したのは、藤田氏の卓見であった。
杉山は苦笑する。
「大人の言うことは聞いとけってことですよね(笑)」
人気絶頂の中、解散。その真意とは

売れれば忙しくなる。テレビに出る機会も増えた。
「『夜のヒットスタジオ』の出演が決まったとき、藤田さんから“小ぎれいな格好をして行け”って言われたんですけど、私服しか持っていなくて。慌ててDCブランドの店まで買いに行きました」
杉山が買ったのは中学生のときには買えなかった白いスーツ。衣装代は事務所が立て替えてくれた。売れっ子にはなっても、大金を手にしたわけではなかった。
「給料制でしたからね。しかも、事務所はヴォーカルの給料しか想定していなかったから、1人分をメンバー全員で分けろ、みたいな話で(笑)」
プロジェクトには明確なイメージ戦略もあった。夏、海、リゾート、都会……。レコードのジャケットにも美しい風景写真が使われる。横浜育ちのメンバーたちも“湘南の若者”として振る舞わなければならなかった。
「テレビや雑誌の取材で、“今朝は何を食べましたか?”と聞かれたら、たとえメザシに納豆だったとしても、“クロワッサンとカフェオレです”って答えていましたよ」
プロジェクトの表現者としての役割をメンバーたちは十分に理解していた。'85年3月、5枚目のシングル『ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER』はJALのCMソングにもなり、『ザ・ベストテン』の年間ランキングで2位となる大ヒットを記録する。
しかし、絶好調と思われる勢いの渦中で、杉山たちはバンドの“限界”を感じ始めていた。
「林さんと康さんが書いているんだから“ヒットして当たり前でしょ?”っていう感覚です。売れても売れなくても僕らの責任じゃない、と」
アルバムには杉山やメンバーが手がけた楽曲が収録されることもあった。が、それは藤田氏の“ご褒美”みたいなものだった。ライブを重ねて演奏の技術が上がったことで、メンバーによるレコーディングを何度も直談判したが、“ダメ!”のひと言で却下。
「ファンに対して“僕らは演奏していません”とは言いたくないし、“演奏しています”とウソもつきたくない。そういう状況を、いつまでガマンするのか? '85年のツアー中でしたけれども、僕が最初に言い出したと思います。“もう、解散しよう”って。もちろん反対するメンバーもいました。今やめるのはもったいないというのは、まともな意見ですよ。でも、まともじゃない意見が通っちゃったんです」
ツアーの途中でオメガトライブを脱退

解散に全面的に賛成したのは吉田だった。そして、正式な解散を待たず、ツアーの途中でオメガトライブを脱退した。
「この状態でオメガを続けていたら絶対に衝突もあるだろうし、メンバーの間に亀裂が入るのがイヤだったんです」(吉田)
反対していたメンバーも、話し合ううちに解散が前向きな選択でもあると考えるようになったと杉山は言う。
「当時、僕らは25、26歳でした。30歳という区切りを見据えたときに、あと4、5年ある。その間に、例えば作曲家になりたければ作曲の勉強をしようよ、プロデューサーになりたければプロデュースの勉強をしようよ、音楽の世界で生きていくなら、30歳までに生き方を決めたいよねって。そんなもっともらしい話をしたことを覚えています」
解散の申し出を、藤田氏をはじめとするプロジェクトの関係者は当然のごとく引き留めた。しかし、ひと足早い吉田の脱退がメンバーの固い意思表示となって大人たちの決定を動かした。
売れなければ自己責任のソロデビュー

デビューから2年8か月。杉山清貴&オメガトライブは'85年12月24日に解散。
「短かったとも長かったとも思いませんけれども、アルバム5枚、シングル7枚、53曲も発表したんですから、めっちゃ濃かったですよね。もう十分やった、これからは新しいバンドでも組んで、30歳までに何かできればいいかなって思ってたんですけど……。レコード会社から連絡が来て、“杉山君、来年はソロデビューだよ”と言われたときは、“はぁ!?”ですよね。勝手に解散したんだからケツ拭きなさいよ、みたいな(笑)」
プロジェクトとの「契約」は残っていた。杉山はシンガー・ソングライターとして、ほかのメンバーは新ボーカルにカルロス・トシキを起用した1986オメガトライブとして活動していくことになる。
「今度は売れなかったら全部自分の責任ですからね。なかなか曲が書けずにいたら、藤田さんから連絡があってカルロスの『君は1000%』を聴かされたんです。“こっちはできたぞ、おまえはどうなってんだ?”と強烈なプレッシャーをかけられた(笑)。
だけど、あの時は曲作りの苦しさと同時に、初めて楽しさも知った。オメガトライブの一員として林さんと康さんの曲を歌わせてもらっているうちに、全体的なアレンジなども頭に浮かべながら、大人の曲が書けるようになったのかなという気がします」
'86年5月、杉山はソロデビュー曲『さよならのオーシャン』をリリース。この曲をプロジェクトの外から聴いた印象を、吉田はこう述べる。
「杉山君が持っているアメリカの西海岸的なテイストが加わって、彼が本当にやりたかった音楽に一歩近づいたなと感じましたね」
'87年5月、ソロ3作目の『水の中のAnswer』はオリコンチャートで1位に輝いた。そして、サポートメンバーに椎野を迎えてライブで共演する機会も巡ってきた。
「会場に杉山のお母さんも来ていて、久しぶりにお話ししたんです。そのときに、“清貴が美大に行かずに音楽の世界で生きていくと言ったときは椎野君を恨んだけれど、今は感謝してるわよ”って言ってもらって。うれしかったですね」(椎野)
デビュー40周年でたどり着いた境地

デビュー10周年では、ライブ会場にサプライズでオメガトライブのメンバーを呼んだ。20周年には脱退した吉田が戻り、オリジナルメンバーでオメガトライブの再結成が叶った。
「20代のころの粗削りな勢いは出せなくなっていましたけれども、みんな成長して楽曲への理解度も深まって、オメガの曲をスムーズに表現できるようになった気がしました」(吉田)
そして40周年を迎えた今、世界中の音楽が時を超えてネット上にアップされる時代になり、『真夜中のドア』が火付け役となって日本の'80年代のAORが世界中で再評価されている。椎野はこう話す。
「当時の杉山のヴォーカルは今も健在で、深みも増していますからね。世界中の音楽ファンに日本のAORを紹介できるアーティストになったのは、杉山の運命なのかもしれませんね」
杉山清貴&オメガトライブの生みの親である藤田氏は'09年に他界した。しかし、名プロデューサー亡き後も、'80年代に音楽ファンを魅了した爽やかなサウンドは、より洗練され、ライブで聴くことができる。
3月から『LIVE EMOTION』と銘打った杉山清貴&オメガトライブのファイナルツアーが始まった。リハーサルスタジオでメンバーたちに囲まれながら、杉山は人なつっこい笑顔でツアーに向けた心境を語った。
「ソロになってからセルフプロデュースも手がけたおかげで、自分を客観的に見つめることができるようになった。そうするとね、オメガの曲をやるときは“オメガトライブの杉山さん”が降りてくるんですよ。だから好き勝手に歌い方を変えたりできない。
オリジナルを忠実に再現しつつ、ふてくされることなく(笑)、大人になったオメガトライブのライブができることを僕らも楽しみにしていますよ」
<取材・文/伴田 薫>

