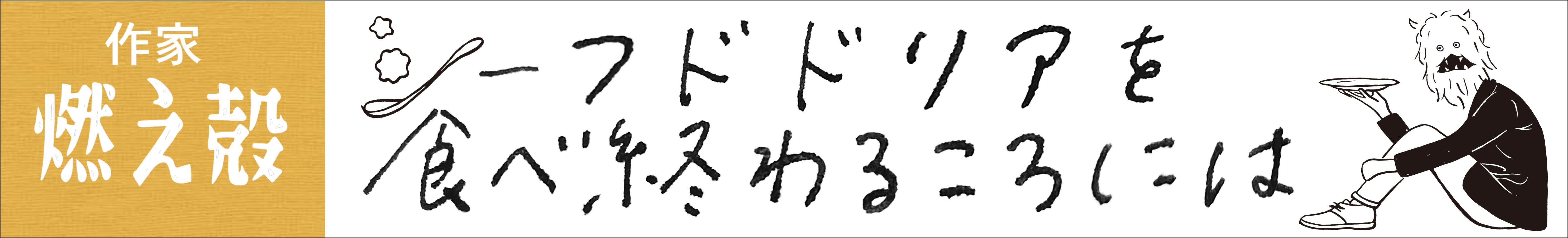ある料理、ある酒を口にするとき、将又(はたまた)、ある店であのメニューを頼むとき、ふと思い出してしまう人―。料理やお酒をきっかけに引き出されるあの日、あの人を描く。グルメじゃないけど、僕にとっての忘れられない味は……。
* * *
横浜中華街で夕飯を食べて、横浜のホテルニューグランドに泊まる。これは社会人になってから、「遠くに行きたい、でも近場じゃないと無理」というときに使う僕の奥の手だ。
だんだん油っぽいものが堪(こた)える年齢になってきて、そのエスケープ方法も、年相応に変化していった。
現在は、横浜ニューグランドのレストランで軽く夕飯を食べ、そのまま泊まる。翌朝は一階にある『ザ・カフェ』で朝食を食べて、世知辛い現実世界に戻るというのが定番だ。
東横線にふらり
中目黒で打ち合わせが終わって、頭が回らないくらい疲れていたら、そのまま元町・中華街駅行きの東横線にふらりと吸い寄せられるように乗ってしまうことがままある。
ホテルニューグランドは、窓の外に山下公園が見え、少し歩いて大通りを越えれば横浜中華街という場所にある。氷川丸がときどき、汽笛を鳴らすのも非日常感があっていい。
今朝、久しぶりに中目黒で打ち合わせだった。帰りに目黒川沿いをプラプラ歩いて、行き当たりばったりのカフェに入る。「打ち合わせ」というお題目が付かずにカフェに入るのは、久しぶりな気がした。
予定は常にタコ足配線のようにこんがらがり、一つ終わると二つタスクが現れる細胞分裂のような状態だった。
注文したホットコーヒーを、半分くらい飲んだところで発作が起きたように会計を済ませて店を出て、僕は駅に急ぎ、東横線に飛び乗っていた。
夜の打ち合わせ相手には、「ダルさが半端ない」と伝えて別日に変更してもらう。まんざら嘘でもなかったが、そんな一言では表せないほど精神的に参ってしまっていた。
多摩川が近づいてきて、罪悪感より解放感が増してくるのがわかる。仕事が追いかけてこない安堵(あんど)からか、恐ろしいほど眠気に襲われた。うとうとしながら、僕はいつかの誰かと、いつかの自分を思い出す。
「シーフードドリア、一緒に食べたいな」
そう言ったのは彼女のほうだった。本当に失礼なのだが、彼女の名前を正しく思い出せない。それに、彼女との関係性も、人には説明できないものだった。もしくは、言葉にしたくはない関係だった。
そんな彼女と僕は、いつかのある日、ホテルニューグランドに泊まった。僕はあのときも仕事で行き詰まっていたが、それ以上に彼女は、人生に行き詰まっていた。何度か理由を聞いたことはあったが、「言葉にすると怒りが溢(あふ)れてきてしまいそうだから」と、なかなか教えてくれない。
「遊びに来てよ」
ふたりで一泊して、朝は中華街で中華粥(がゆ)を食べる予定だったのに、起きることができず、チェックアウトギリギリまでぐずぐずしてしまった。一度ちゃんと休めたことで、毛穴という毛穴から、疲れと澱(よど)みと世間体が漏れ出すような朝だった。
僕たちは身体を引きずるようにしてチェックアウトをして、近くのマクドナルドでコーヒーを買った。
山下公園のベンチに座り、コーヒーをすすりながら、しばらくぼんやりしていた。空は雲が一つもない快晴で、暑くも寒くもない。風だけが強い日だった。
ベンチに体育座りをして、ぼんやり行き交う人々を眺めていた彼女が、仲良くランニングをする老夫婦を目で追いながら、「いいなあ」とだけつぶやく。
そのとき、また氷川丸の汽笛が鳴る。あまりの汽笛の音の大きさに、ケラケラと大声で笑い出す彼女。季節は初夏で、僕はまだ若かった。彼女もじゅうぶん若かった。
彼女はもうすぐ仕事の関係でカナダに行ってしまうということをそのとき教えてくれた。「遊びに来てよ」老夫婦の姿を目で追いながら彼女がゆっくりと言う。「うん」とは答えたが、僕のパスポートは何年も前に有効期限が切れていた。
それに「温泉に行きたい」という細(ささ)やかな夢ですら、簡単に叶(かな)えることが難しいほど仕事が多忙を極めていた。
「ちょっと風が冷たい。シーフードドリア一緒に食べたいな」と彼女が言った。
「美味しくて、涙出ちゃった」
僕たちは、もう一度、ホテルニューグランドに戻る。一階の『ザ・カフェ』で、約束通りシーフードドリアを注文した。昼だけど、と断りを入れてから、白ワインも注文する。
程なくして現れたシーフードドリアは、グラグラと熱を放出しながら、立派なホタテや海老(えび)がゴロゴロ入った豪勢な一品。熱い器に注意しながら、スプーンで一口すくってみる。「ホフホフ」と漫画のようなリアクションをとってしまう。
その瞬間、白ワインを一口、口に含んでみる。シーフードドリアと少し酸味のきいた白ワインが口の中でゆっくりと溶け合っていく。そして白ワインの味が増した瞬間に、ゴクリと喉を通過させる。するとなんとも言えない多幸感が、口いっぱいに広がる。
彼女もすぐにその食べ方を真似する。ゴクリと喉を通過させたあと、「美味しい」と言った彼女が、「わたしさ、やっぱり離婚するのやめようと思うんだ」と行き詰まったすべての話をしはじめる。
話が終わる頃、彼女は「美味しくて、涙出ちゃった」と涙をそっと拭きながらつぶやいた。
それから彼女がカナダから帰ってきたのかどうか、僕は知る由もない。東横線は多摩川の陸橋を越えて、一目散に横浜を目指している。座席はほとんど空いていて、陽射(ひざ)しは優しい。
季節は秋なのに、春のような暖かさだった。少しだけ喉が渇いていた。僕はまたうつらうつらとしてしまう。眠ってしまいそうだ。口がシーフードドリアを欲している。白ワインも必ず付けようと心に決めていた。
あのときの、名前も思い出せない彼女は、何をしているだろう。彼女もまた、僕の名前は忘れてしまったかもしれないが、あのシーフードドリアを一口含んだ瞬間を、ふと思い出したことはあるだろうか。

燃え殻(もえがら)●1973(昭和48)年、神奈川県横浜市生まれ。2017(平成29)年、『ボクたちはみんな大人になれなかった』で小説家デビュー。同作はNetflixで映画化、エッセイ集『すべて忘れてしまうから』はDisney+とテレビ東京でドラマ化され、映像化、舞台化が相次ぐ。著書は小説『これはただの夏』、エッセイ集『それでも日々はつづくから』『ブルー ハワイ』『夢に迷ってタクシーを呼んだ』など多数。
『BEFORE DAWN』J-WAVE(81.3FM)
毎週火曜日 26:00〜27:00放送
公式サイトhttps://www.j-wave.co.jp/
※本連載の一部を燃え殻さんが朗読するコラボ企画を実施中