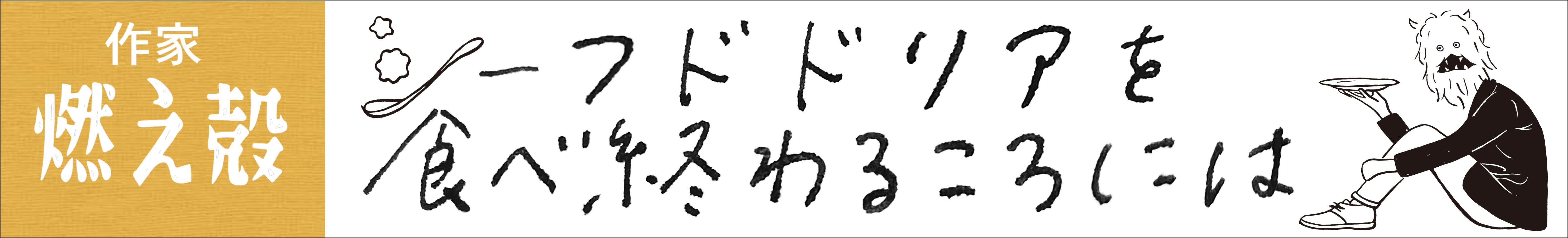ある料理、ある酒を口にするとき、将又(はたまた)、ある店であのメニューを頼むとき、ふと思い出してしまう人―。料理やお酒をきっかけに引き出されるあの日、あの人を描く。グルメじゃないけど、僕にとっての忘れられない味は……。
* * *
SNSの数少ない良いところは「死にたい」とつぶやくと「わたしも」と返ってくるところだと思う。
ずいぶん前に、僕はそのようなことをつぶやいたことがあった。
そのとき、「わたしも」と返事をくれた人は、イラストレーターを生業(なりわい)にしている女性だった。
彼女が取り沙汰されていたすべてを知っているわけではないので、言われていたどれもが言われなきことなのかどうか判断できないが、彼女が死にたいほど悩んでいたことは事実だ。
ジャンボモナカを食べながら
その日から彼女と文通のようなメッセージを交わすようになった。
あるとき、彼女から〈電話で話したい〉とメッセージが届く。
「もしもし……」
電話口の彼女はゴソゴソモゴモゴしながらそう言った。
「なにか食べてるの?」と僕が訊くと、「バレた。チョコモナカジャンボ」と白状する。「バニラに挟まってるチョコが、パリパリで美味しいんだよね」と彼女はことのほか上機嫌だった。
ベッドに寝転んでいた僕は起き上がって、パーカーを着て部屋を出る。「もしもし」と返しながらエレベーターに乗って、一階に降りる。
そこから近くのローソンまで歩いて、アイスのコーナーで、チョコモナカジャンボを見つけて、レジまで持っていく。会計を済ませている間、彼女はケタケタと笑っていた。
部屋のベッドに戻り、チョコモナカジャンボをパリパリ食べながら、「久しぶりに食べた」と言った。
「ね~、初めての電話なんですけどー」と言う彼女もまだ、ゴソゴソモゴモゴとチョコモナカジャンボを食べながらの抗議。「で、どうしたんだっけ?」ととぼけながら尋ねると、彼女は最近あった落ち込んだ話を一から順に丁寧に話し始めた。
「それは大変だ……」と、僕はモゴモゴ答える。
「ね~、ちゃんと聞いてる?」と、彼女は笑っていた。
でも、程なくして、お互いちょっとシリアスに話し込んでしまう。
彼女は、一日に「死ね」「消えろ」と十通以上のメッセージが届くことを教えてくれた。僕は電話番号が漏洩して、いたずら電話が延々かかってきた時期があったと伝えた。
少しの静寂が訪れて、それをかき消すように彼女が言う。
「わたしさ、有名になりたかったなぁ……」
「有名になってどうするの?」と僕が訊く。
「そこから見える景色が見たかったかも……」
その後、いまは誰にも会いたくないけどね、と付け加えた。
「イラストレーターとして、もっといろいろなことがしたかった」と言う彼女に「これからもっといろいろできるよ」と返すと、「そうかなあ。うーん」とごまかされた。
彼女がフッとこの世から消えてしまったのは、その電話から数日後。本当にすぐのことだった。
彼女に誹謗中傷を繰り返していたアカウント群は、彼女が亡くなった夜に、その多くが消えてなくなる。きっとまた彼らは反省もなく、次の標的を見つけ、同じことを繰り返す気がする。
正直、彼女は傍(はた)から見れば生前十分に売れていた。活躍の場を広げていくチャンスを既に掴んでいるように見えた。でも、彼女の志は僕などが思うよりも、もっともっと高かったのだろう。
亡くなった後も、美術系の雑誌や女性ファッション誌で、彼女のイラストレーションは何度も紹介された。某有名クリエイターが、作品の多くを買い取ったということが記事になったときは、本当に驚いた。
深夜のコンビニで、彼女のイラストレーションがカラーで数ページにわたって特集された雑誌を立ち読みしたとき、嬉しさと哀しさがぐちゃぐちゃになって込み上げてきた。
僕はまだ、さよならが言えていない別れに実感を持てずにいる。
いい加減な話をしよう
「わたしさ、有名になりたかったなぁ……」
彼女がポツリと言った言葉をふと思い出す。あの夜、もっといい加減な話だけすればよかったと、ずっと薄いもやがかかったような後悔を引きずっている。
僕たちはあの夜、精神的にはギリギリの場所にいた。突き詰めたら「死にたい」と吐露してしまいそうな閉塞感の中にいた。
昔、いじめにあったとき、担任教師は楽観的でいい加減な人だった。上履きから教科書まで隠された僕に、「まあさ、こういうのも流行りみたいなもんだから」と言って、僕の肩をポンポンと叩く。担任教師はさらに、職員室の脇でタバコを吹かしながら、こう続けた。
「流行りは全部すぐ終わるだろ?ブームって一過性だからさあ」
今なら、最初から最後まで全部アウトだろう。でも、あのときの僕はたしかに、その楽観的でいい加減な言葉に救われていた。
答えは常に一つじゃない。右か左か、上か下か、黒か白か、だけじゃない。保留もあれば、逃げもある。それどころか、答えは常に無限だ。
選択肢がいくつかに絞られて見えたら、ギリギリの精神状態に近づいているから、一旦全部傍(そば)に置いて、どこにもたどり着かない話でもすればいい。
答えなんて出なくても、希死念慮を、時間を、強迫観念を、やり過ごせる。それでいい。
だから、あの夜もどこにもたどり着かない、答えなんてない、これから先の話だけをすればよかった。そうすれば、彼女はいまのこの景色を見れたかもしれない。
回顧展ではない、華やかな個展を開いていたかもしれない。そうすれば、僕はその個展に行って、あの夜の会話の続きができただろうか。あの問いに答える彼女が見たかった。
「有名になってどう?」
真面目に答えようとする彼女に、僕はまたいい加減な聞き方を笑いながら咎められる。
「ね~、ちゃんと聞いてる?」
「聞いてる。ねえ、そこから見える景色はどう?」

燃え殻(もえがら)●1973(昭和48)年、神奈川県横浜市生まれ。2017(平成29)年、『ボクたちはみんな大人になれなかった』で小説家デビュー。同作はNetflixで映画化、エッセイ集『すべて忘れてしまうから』はDisney+とテレビ東京でドラマ化され、映像化、舞台化が相次ぐ。著書は小説『これはただの夏』、エッセイ集『それでも日々はつづくから』『ブルー ハワイ』『夢に迷ってタクシーを呼んだ』など多数。
『BEFORE DAWN』J-WAVE(81.3FM)
毎週火曜日 26:00〜27:00放送
公式サイトhttps://www.j-wave.co.jp/
※本連載の一部を燃え殻さんが朗読するコラボ企画を実施中