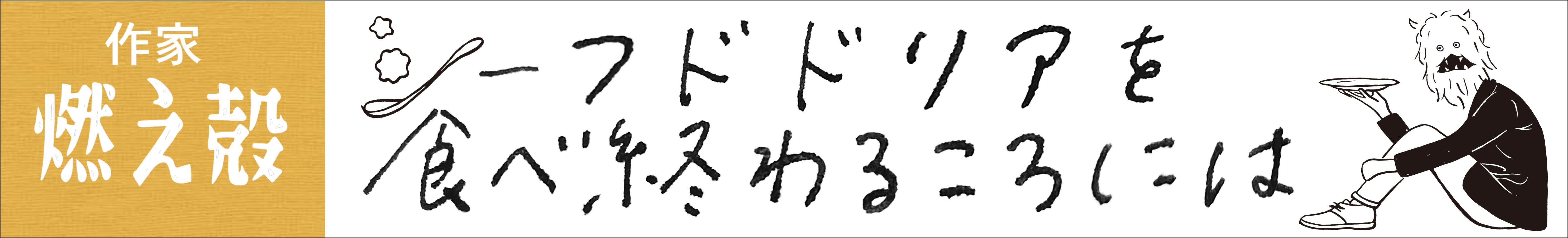ある料理、ある酒を口にするとき、将又(はたまた)、ある店であのメニューを頼むとき、ふと思い出してしまう人―。料理やお酒をきっかけに引き出されるあの日、あの人を描く。グルメじゃないけど、僕にとっての忘れられない味は……。
* * *
サラリーマン生活が長かったので、物書きを生業(なりわい)にしてからも規則正しい生活を送ってしまう。必ず朝八時から道玄坂の仕事場で原稿を書き始めるのが日課で、近場のカフェでコーヒーを買って行くことが多い。
その道すがら「朝キャバいかがですか?」と首から『朝キャバ1時間2000円!』と明記されたプラカードをぶら下げた薄着の女性に必ず声をかけられる。
気づけば、朝の挨拶が日課に
渋谷道玄坂近辺には、朝から営業しているキャバクラが何軒かある。学生時代、通学路で毎日立っている交通整理のおじさんと、だんだんと朝の挨拶をする関係になっていくように、いつしか「あー、おはようございます」などと、朝キャバの女の子たちと朝の挨拶をする関係になっていった。
今朝も、コーヒーを買おうと道玄坂を歩いていると、「おはようございま~す。なんか疲れてない?」と朝キャバ嬢に声をかけられた。昨日、あまりに仕事が立て込んでいて、ほとんど眠れていなかった。さすが、毎日挨拶を交わしているだけのことはある。僕の寝不足を彼女は一発で言い当てた。
「ちょっと休んでいったほうがいいと思うの」
彼女は強引に腕を組んできて、店まで連れて行こうとする。欲望にはすべて負けたいが、どうしても、とある原稿を書かないと間に合わない事情がこちらにはあった。
が、煮詰まった状態で仕事に臨んでもいい結果はなかなか得られない。一度原稿から離れてみるのもいいだろう、という完璧な言い訳が頭の中で成り立ち、初めて朝キャバというものを味わうことにした。
店内に入ってまず驚いたのが、結構お客さんがいるということだ。今朝は、ガタイのいい男たちのグループと、ホストっぽい若者グループ、そして、おじいさんがひとりというラインナップだった。
僕の隣のソファー席では、おじいさんが若い薄着の女性とニコニコ話している。まるで縁側で話す孫と祖父のようだ。僕を店内まで引っ張ってきた彼女は、横に座って「やっとだね」とご満悦そうに、おしぼりを渡してきた。
「なぜ朝キャバで働いているの?」と聞いてみると、朝はノルマがなく、女の子同士の派閥などもないのでラクなのだという。午後からは一般職でも働いているらしい。
「真夜中に準備して、早朝過ぎる時間から働いているから、実際は夜勤だけどね」と彼女は笑った。
僕も昔、テレビ業界で夜勤をやっていた時期があった。シフトは夜九時から朝方まで。一見過酷だが、クライアントも含めて夜勤をやる人間は限られていて、あっという間に顔見知りになり、どこか同志感が出てくる。
テレビ業界は、基本的には厳格な縦社会なので、いつなんどきでもクライアントには最大限の敬語で接しないといけない暗黙のルールがある。だが夜勤の場合、顔を合わせる相手も限られるので、距離が異様に近くなり、「うっす!」とこちらが言って、「うっす!」で返してくれるような関係になることが多かった。
朝、お互い仕事から解放されたときに待ち合わせをして、一緒に映画を観に行ったことすらある。中には、互いの会社の悪口も言い合えるほどの信頼感で結ばれた相手もいた。会社側も夜勤は常に人手不足なので、金銭面でも優遇してくれた。
弊害を強いて言えば、昼間に無理やり眠らないといけないので、厚手のカーテンを買わないと陽の光が部屋に入って、どうしても眠れないことだろうか。
夜勤が終わると早朝必ず、溜池山王の某牛丼チェーンで、牛丼大盛りを食べていたのも懐かしい。牛丼屋の夜勤もだいたい同じメンツで、通ううちにだんだん店員と顔なじみになっていく。信じられないくらいのつゆだく、玉ねぎ多めのサービスをしてくれたりもした。
その店は外国人のアルバイトが多かったが、一人だけ日本人の男性がいた。僕がまだ三十代前半くらいのときに、彼は五十代くらいには見えた。
「お疲れで~す」と言って僕が席に着くと、「はい、お疲れ~い」と自分の居酒屋かなにかのように、慣れた感じでお冷やを置いてくれる。その夜にあった仕事についてのいろいろを、牛丼を食べながら話したり、聞いたりもしていた。
「仕事仲間」というのは普通、同じ社内の先輩後輩やクライアントのことを指すと思うが、「夜勤仲間」という括(くく)りも、世の中には存在することを、朝キャバに行ってみて、久々に思い出した。
あの牛丼屋の男性との最後は、いまでも憶(おぼ)えている。いつものように夜勤終わり、僕は腹を空かせてその店に行く。自動ドアが開くと、大きな怒号が突然聞こえてきて、思わず厨房のほうを覗いてみた。
店内には僕ひとり。厨房の奥で、外国人のアルバイト長のような男性が、流暢な日本語で、彼のことを叱っている真っ最中だった。外国人の男性のほうは、まだ二十代くらいに見えた。
しばらく怒号はつづき、僕の存在に気づいて、一度止(や)む。そして俯(うつむ)いた彼が厨房から出てきて、僕の前にお冷やを無言で置くと、チケットを取って、「しばらくお待ちください……」とだけ言った。
僕たち「夜勤仲間」が、実際は「下請け雇われ仲間」だという現実を提示されたような気がして、自分のことのように落ち込んでしまったことを憶えている。
次にその店に行ったとき、もう彼の姿はどこにもなかった。同じ空の下、一緒に夜を越えた仲間は、同じ仕事じゃなくても、どこか同志の匂いがした。目の前で薄い水割りを作り始めた朝キャバ嬢を眺めながら、もう名前も忘れてしまった彼らのことをぼんやりと思い出していた。

燃え殻(もえがら)●1973(昭和48)年、神奈川県横浜市生まれ。2017(平成29)年、『ボクたちはみんな大人になれなかった』で小説家デビュー。同作はNetflixで映画化、エッセイ集『すべて忘れてしまうから』はDisney+とテレビ東京でドラマ化され、映像化、舞台化が相次ぐ。著書は小説『これはただの夏』、エッセイ集『それでも日々はつづくから』『ブルー ハワイ』『夢に迷ってタクシーを呼んだ』など多数。
『BEFORE DAWN』J-WAVE(81.3FM)
毎週火曜日 26:00〜27:00放送
公式サイトhttps://www.j-wave.co.jp/
※本連載の一部を燃え殻さんが朗読するコラボ企画を実施中