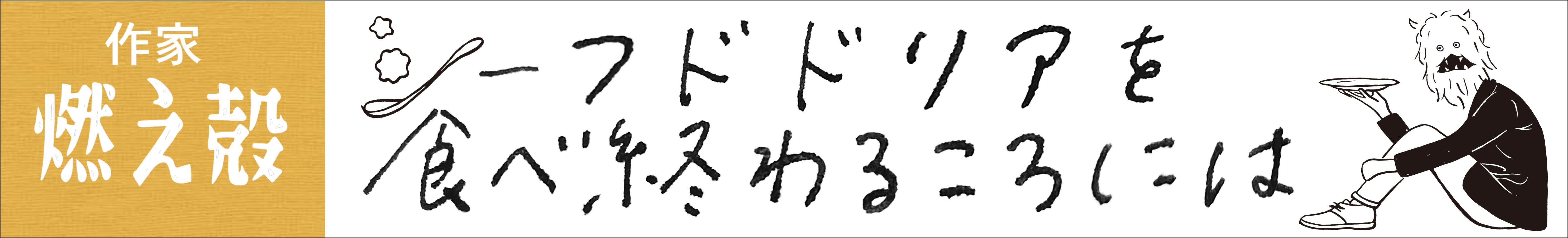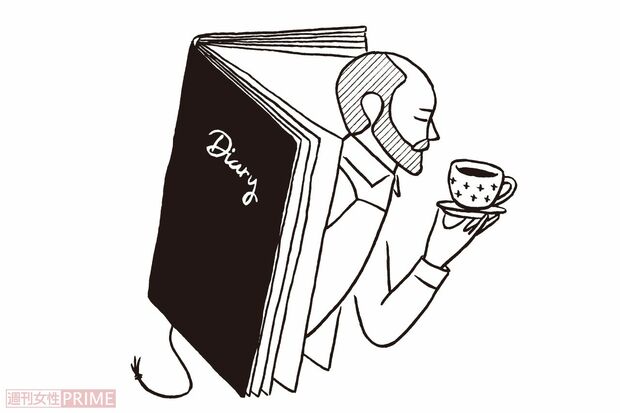
ある料理、ある酒を口にするとき、将又(はたまた)、ある店であのメニューを頼むとき、ふと思い出してしまう人―。料理やお酒をきっかけに引き出されるあの日、あの人を描く。グルメじゃないけど、僕にとっての忘れられない味は……。
* * *
五十歳くらいになると、知っている誰かが亡くなることがポツポツと起き始める。行きつけの喫茶店のほぼ同い年のマスターが、体調を崩して入院して、あっという間に昨日亡くなってしまった。入院する前日まで、店でコーヒーを淹(い)れる姿を見ていたので、悲しいという気持ちが正直まだほとんど湧いてこない。
クサくてキモくて面白い男
マスターの奥さんから昨夜連絡をもらって、今日これからお線香をあげに行くところだ。彼の死に顔を見たら、現実だと納得できるだろうか。
奥さんは少々変わった人で、「彼が大量の日記を残していたんだけど、それがどれもこれもクサいのよ~」と電話口で笑っていた。こちらもイマイチ感情が湧いてこないので、「あいつ、キモいとこあったもんねえ」といつもの調子で言えてしまう。
「日記をパラパラ読んでみたんだけど、絶対死んだら私が読み返して感動するだろうって想像しながら書いているのが、行間から匂い立ってるのよね~」と、奥さんの口ぶりはキレキレで容赦がない。
「あー、絶対読むだろうと思って書いていたと思いますよ。キモいっすねえ~」と、容赦という言葉を捨てた僕も続けた。
「まあ、供養だと思って読みに来てやってよ」
奥さんはそう言って、最後だけ少し寂しげな声で電話を切った。
僕はこれから彼に線香をあげ、キモい日記を隅々まで読んでやろうと企んでいる。きっと僕のことも、エモキモく書いてあることは、ほぼ間違いない。
彼は本当にクサい男だった。クサくてキモくて面白い男だった。
どれくらいかといえば、店に初めて来た綺麗な女性には、「いままでお祝いできなかった誕生日の分です」と言って、サンドイッチをプレゼントするのが定番であるくらいに、だ。そんな(どんな!)彼の喫茶店に初めて行ったのは、まったくの偶然。知り合いのライターが、「いつもスカスカで座り心地のいいイスがある喫茶店を見つけた」と、連れて行ってくれたのが最初だった。
店に入った瞬間、マスターは慌ててジャズのレコードをかけた。僕たちはコーヒーを注文する。店内に程なくして、小さくウディ・ハーマンが流れ出し、美味しそうなコーヒーの匂いが充満した。
そのとき、彼の奥さんが店に入ってきた。「外からジャズが聴こえてきたから、お客さん来てると思ったわ」と笑いながら僕たちに会釈をする。そして、「この人、ひとりのときはサザン聴いてるんですよ。お客さんが来ると、突然レコードでジャズをかけ始めるの~。キモいでしょ~?」と手を叩いて笑った。
その日マスターは散々僕たちに言い訳をしていたが、僕が店の常連になる頃には、BGMは常にサザンオールスターズに変わっていた。
カッコつけで、村上春樹に憧れてるのに、『風の歌を聴け』しか読んだことがなくて、『SLAM DUNK』と『幽☆遊☆白書』が心底大好きな人だった。ことごとく俗人っぽい彼のことが僕は好きだった。
奥さんの趣味のジャズを一生懸命好きになろうとしているところも好きだった。小説やエッセイを読むことが大好きな奥さんに愛されたいと、店の一番隅の奥さんがいつも座る場所に、自分が書いた日記を置いている健気(けなげ)な努力も好きだった。
いつだったか、彼が「ジャズって、どう聴けばいいんだろうね?」と真顔で聞いてきたときは笑ってしまった。それでも最後の何年か、彼がジャズの演奏に合わせて、カウンターを無意識に指でトントントンと叩いている姿を眺めながら、日々を重ねていくことっていいなあ、と心から思った。
彼の淹れる浅煎りのコーヒーは、疲れ切った夕方でも、休みの日の早い朝でも、ふと飲みたくなった。良いことがあったときも、悲しいことがあったときも、急に飲みたくなった。季節によってカップを変えて出してくれたのも嬉しかった。
その夜、線香をあげた後、奥さんに手渡されて彼の日記を読んだ。それは僕の予想通り、大半がクサくてキモいものだった。
〈5月8日(月) 今日のランチは、僕が彼女にパスタを振る舞った。アルデンテ!〉
例えば、アルデンテに「!」を付けて締めるところ。村上春樹は結局、三行くらいしか読まなかったんじゃないだろうか? と推測される。
〈9月5日(土) 駅前のラーメン屋ですべての事件は起こった。その出来事が起こる前には、もう僕たちは戻ることはできない〉
ここから始まるのは、ただ味噌ラーメンを食べたら火傷(やけど)して、その後、風呂場ですっ転んだというだけの、“出来事”だ。改めて言い直したい。彼は村上春樹を二行しか読まなかったんだと思う。
そんなツッコミどころ満載の彼の日記のある一文に、ふと目が留まった。それはただ、奥さんとふたり、ちょっと遠くの映画館に行って、マクドナルドに寄ったという内容で、最後はこう締めくくられていた。
〈何事もない日だった。来年には忘れてそうなくらい完璧な日だった。それはとても幸せなことだ。また近いうち、みさこと一緒に来れたらいいな〉
季節がまた変わろうとしている。日々は待ったなしで過ぎていく。こちらは昨日、一つ仕事が片付いて、二つ面倒なことが起きた。そっちの具合はどうだろうか?
僕はいま、マスターが淹れてくれる浅煎りのコーヒーが無性に飲みたいよ。

燃え殻(もえがら)●1973(昭和48)年、神奈川県横浜市生まれ。2017(平成29)年、『ボクたちはみんな大人になれなかった』で小説家デビュー。同作はNetflixで映画化、エッセイ集『すべて忘れてしまうから』はDisney+とテレビ東京でドラマ化され、映像化、舞台化が相次ぐ。著書は小説『これはただの夏』、エッセイ集『それでも日々はつづくから』『ブルー ハワイ』『夢に迷ってタクシーを呼んだ』など多数。
『BEFORE DAWN』J-WAVE(81.3FM)
毎週火曜日 26:00〜27:00放送
公式サイトhttps://www.j-wave.co.jp/
※本連載の一部を燃え殻さんが朗読するコラボ企画を実施中