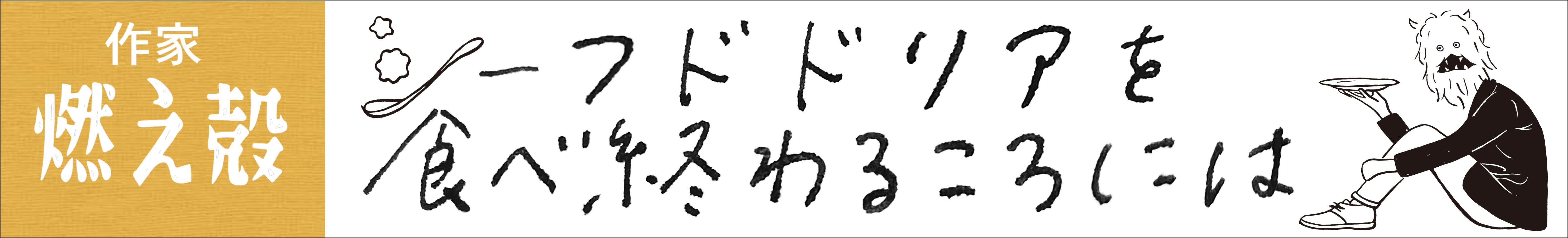ある料理、ある酒を口にするとき、将又(はたまた)、ある店であのメニューを頼むとき、ふと思い出してしまう人―。料理やお酒をきっかけに引き出されるあの日、あの人を描く。グルメじゃないけど、僕にとっての忘れられない味は……。
* * *
その土地の匂い、料理、そこで暮らす人々。すべてがマッチする場所が、まーまー長く生きていると、一つや二つ誰にでもあるはずだ。僕にとってのそんな場所がタイだった。
突然の遅すぎるアーティスト宣言
十年以上前、僕の友人が「サラリーマンを辞めて、写真家として生きていきたい」と飲みの席で宣言した。当時すでに三十代半ばで、遅すぎるアーティスト宣言だ。しかし、彼の情熱は本物だった。「タイの子供たちの笑顔を撮りに行く」と言って、翌日には会社を休職し、プーケットまでのチケットを予約する。
もともと大人しい性格で、真面目に印刷業をこなし、金遣いも荒くない男だった。二十年以上一緒にいて、怒ったところは見たことがない。その代わり、自分から主張して行動するところも見たことがなかった。口癖は「それでいいよ」。だから突然のアーティスト宣言が嬉しく、よほどのことだと受け止めた。
「一緒に来ない?」
その誘いに二つ返事で乗ったのは、彼の人生の分岐点に立ち会ってみたかったからだ。
プーケットに到着した翌朝、彼は早速撮影に向かったようで部屋にいない。約束した夕飯の時間まで、僕は異国の地を散歩することにした。
朝から地べたに座っているおじさんたちが気持ちよさそうに、甘い煙を燻(くゆ)らしている。知らない路地を曲がって、知らない食堂に入る。カウンターに座ったと同時に、ザザーッとゲリラ豪雨が降ってきた。バケツをひっくり返す、なんて生やさしいものじゃない。地面を叩きつけるように降る激しさに、しばらく呆然と外を眺めた。
気づくと目の前に恰幅(かっぷく)のいい女性が立っていて、オーダー待ちをしている。僕は慌ててメニューにある写真を指さす。コクンと頷(うなず)いた女性は、テーブルをまあるく拭き、厨房へ戻って行った。
雨はすぐにやみ、今度はギラギラとした太陽が顔を出す。全開の窓から熱風が入ってくる。店内では、カタカタと壊れかけた扇風機が一台だけ頼りなく回り、ムンとした動物の匂いがずっとしていた。
運ばれてきたシンハービールをグラスに注ぐとすぐに、ガパオライスと揚げたエビに塩をふんだんに振った料理が1つの皿に盛られ、運ばれてきた。ガパオライスは東京で食べたものより油っぽくない気がした。いや、ムンとした気候も相まって、ちょうどよく感じただけかもしれない。
途中、ナンプラーをドバドバかけ、味変を楽しむ。唐辛子や砂糖も微調整しながらかけてみる。これもまた美味い。エビの揚げ物は塩の量が半端なく、舌先が痺れてシンハービールをもう一本注文した。
その後、店を出て、ビーチまで歩く。プラスチックのイスに座ったタイの若者が、タバコらしきものをプカ~とやって、「お金をください」としっかりした日本語で話しかけてきた。「なぜ日本語喋れるんですか?」と野暮なことを僕は聞いてしまう。「日本の女の子は優しいよ」と彼は柔和(にゅうわ)な笑顔を作った。
僕の友人のミュージシャンは二年半前、登戸の半地下のワンルームマンションに住んでいた。でも、数年で彼はヒット曲を連発し、中目黒のタワーマンションの最上階に引っ越した。貯金額は通帳を記帳するたび跳ね上がり、最近は「あまりに桁が多くなって、気持ち悪いとすら思うんだ」とこっそり教えてくれた。
彼が、中目黒のタワーマンション最上階から見る夜景を楽しめたのは、最初の二週間だけ。耐震性に優れた建物は細かく揺れ、三半規管に異常をきたしたのは入居して一ヶ月。写真週刊誌には常に追われ、期待とプレッシャーは、貯金額と同じように桁違いに上がっていく。久々に食事をしたとき、「俺、なんなんすかねえ」と彼はため息をついた。
タイのプーケットで出会った男は、「ドゥと言いますぅ」と僕に握手を求めた。ドゥはひと夏に最低でも、日本人の女性二十人くらいと関係を持つらしい。基本はその日暮らし。食事は観光客に奢ってもらうのが日常だ。関係を持った日本人の女性に会うため、十回は来日したという。『一風堂』の赤丸が好きだと言うので、本当はそれ以上かもしれない。
僕がタイに滞在する間、ドゥとは何度も会って、何度も「お金をください」と口慣れた日本語でねだられた。「無理」と返すと、ニヤッと笑って、そのまま甘いタバコを吸い、「プハァ~」とやって終わりだ。あのすべてに対しての執着のなさは、ちょっと見習いたくもなる。
渋谷の仕事場で久々にガパオライスが食べたくなって、近くのタイ料理屋に出かけた。しっかり辛くて、プーケットで食べたガパオライスに似ている。ドゥはあれからどうしただろう。夏が来るたび、日本人女性とうまいことやっているのだろうか。ぼんやりタバコらしきものを吸って「プハァ~」とかやって、自由気ままに生きているのだろうか。
中目黒のタワーマンションに住むミュージシャンは、秋に引っ越すことが決まった。
突然アーティスト宣言をした彼は、タイの食べ物が身体に合わず、激しい腹痛を繰り返し、実は僕より先に日本へ帰国した。出端(ではな)をくじかれた彼は、今はクライミングに挑戦している。
東京はあのとき食べたガパオライスと遜色ないガパオライスが食べられる土地で、清潔で、治安も良く、夜は煌々(こうこう)と灯りがついている。なんでもあるこの土地で、僕は仕事をしながら、成功や失敗を日々繰り返している。久しぶりに満員電車に乗ったら、あまりのギュウギュウ詰めの状態に、一駅前で降りてしまった。
ゲリラ豪雨が降ったりやんだりする土地。ねっとりとした空気。空港からすでにうっすらとナンプラーの香り。ムンとした動物の匂い。程よく弛緩(しかん)した人々。そのどれもが、ずっと暮らしてきたかのように心地良く感じられる場所だった。
僕はまた満員電車に乗る。自分はどんな地で、どう生きていきたいのか、正解はわからない。「そんなものは最初からないよ」とドゥに笑われそうな気がするけれど。

燃え殻(もえがら)●1973(昭和48)年、神奈川県横浜市生まれ。2017(平成29)年、『ボクたちはみんな大人になれなかった』で小説家デビュー。同作はNetflixで映画化、エッセイ集『すべて忘れてしまうから』はDisney+とテレビ東京でドラマ化され、映像化、舞台化が相次ぐ。著書は小説『これはただの夏』、エッセイ集『それでも日々はつづくから』『ブルー ハワイ』『夢に迷ってタクシーを呼んだ』など多数。
『BEFORE DAWN』J-WAVE(81.3FM)
毎週火曜日 26:00〜27:00放送
公式サイトhttps://www.j-wave.co.jp/
※本連載の一部を燃え殻さんが朗読するコラボ企画を実施中