
『情熱大陸』(毎日放送・TBS系列)を収録するスタジオにひとり、異様に楽しげな男がいた。今にも踊り出すのではないか、と思うほど全身でリズムを取り、“ことば”に息を吹き込んでいくナレーター・窪田等。絶妙な“間”と含みのあるしゃべり。そのやわらかな低音ボイスの裏には、桁外れな「もう1回」の軌跡があった。
金曜日の夕方6時。東京・赤坂にあるスタジオで、『情熱大陸』(毎日放送・TBS系列)のナレーション収録が始まった。
ナレーター・窪田等のこだわり

ナレーターの窪田等さんが2重の扉を開けて、狭いブースに入る。ヘッドホンをつけ、目の前のモニターに映る映像をチラッチラッと見ながら、マイクに向かって手元の原稿を読むと、低めで安定感のある穏やかな声がスタジオ全体に流れる。
モニターからおなじみのテーマ曲が聞こえると、窪田さんも楽しそうに身体を揺らす。ナレーションが入らないところでは映像に見入って、クスリと笑うことも。時折、指揮者のように指を動かしてテンポを取ったり、歌手のように握ったこぶしを回して、ナレーションを入れるタイミングを計る。
「ここはもうちょい、間を取ってもいい?」
窪田さんがこだわっていたのは、「好きでたまらない」というセリフ。「好きで」で一度切り、1秒弱の間を取って「たまらない」と続けると、確かにより深く余韻を感じる。
「もう1回お願いします」

窪田さんはブースの外のスタッフに声をかけながら、手にしたペンで原稿に注意点をすごい勢いでサラサラと書き込んでいく。
『情熱大陸』は、第一線で活躍するさまざまな分野の人たちに密着した30分のドキュメンタリー番組で、今回の主役は売れっ子脚本家・演出家の加藤拓也さん。2日後の放送に向けて、急ピッチで収録が進められていく。
1998年の放送開始時から窪田さんは26年間ナレーションを担当。バイオリニストの葉加瀬太郎さんが奏でるテーマ曲とともに、番組に欠かせない存在だ。
毎回、原稿を下読みした後、映像を見ながら一度テストをする。ナレーションだけを次々録っていく通常の収録方法より手間はかかるが、「自分からお願いしてテストをやらせてもらっている」と窪田さんは説明する。

「僕のわがままなんですけどね。テストするといろんな発見があるんですよ。ここはこんな音楽が流れてくるのか、じゃあ、もうちょっと軽いノリで読んでみようとか。
ナレーションが入るタイミングにしても、他の番組だと『とりあえず録っておいて、後でずらして調整するからいいですよ』と言われるけど、機械的に調整したのと、映像を見て間を取りながら読んだのと、微妙に違ってくると思うんですよ。AIにはまねできないところ(笑)」
元乃木坂46・生田絵梨花の回で“ダメ出し”

テストが終わると、窪田さんはブースから出てきて、「この言い方だとわかりにくい」など、“最初の視聴者”として感じたことを伝える。プロデューサー、ディレクター、構成作家などスタッフは、窪田さんの率直な感想をドキドキしながら待つという。
逆に、スタッフのほうから窪田さんに注文を出すこともあるが、窪田さんは笑顔で聞いている。
「他の現場では僕に遠慮があるのか、こうしてください、ああしてくださいと言われることが少なくなっているので、ダメ出しをもらえると、うれしいんですよ」
例えば、今年10月に放送した元乃木坂46の生田絵梨花が登場した回。「歩む道にゴールはない」というエンディングの言葉を最初、窪田さんは力強く言い切った。だが、毎日放送プロデューサーの沖倫太朗さん(43)は、窪田さんにお願いをした。
「もうちょっと、やさしく読んでみてくれますか」
その理由を沖さんはこう語る。
「番組として生田さんの背中を押すというか、応援している感じが欲しかったんです。窪田さんは読み方のパターンをたくさん持っているので、僕が詳しく説明しなくてもわかってくれる。このときもすぐにニュアンスを変えて読んでくれました。
以前、窪田さんにどうやってニュアンスを変えているのかと聞いたら、距離感だと。空に向かってか、目の前の相手か、自分自身に向かってか。どこに向かって話すかでトーンが変わると言われて、わかるような、わからないような(笑)。でも、それがナレーションなのか、すごいなあと」
『情熱大陸』の開始当初から何度も一緒に仕事をしている構成作家の田代裕さん(68)は、窪田さんのナレーションを「職人技」だと称賛する。
「窪田さんは音に敏感ですね。ドキュメンタリーだからクラクションの音とか、その場の環境音も視聴者には情報になります。大事な要素なんですが、例えば、僕が指定したところでナレーションを読み始めるとクラクションの音と重なってしまうと思うと、窪田さんは実にうまくすり抜けて読みのタイミングをずらしてくれるんですよ。環境音を生かして臨場感を残す。その柔軟な対応力はすごいなと思います」
田代さんによると、わかりにくい一連のセリフに対して、「こうしようか、ああしようか」と20分も議論して直したこともあるそうだ。
窪田さんを含めて、みんなで意見を出し合い、ナレーションを修正した後、本番の収録に臨む。どんなに時間がかかっても、窪田さんは面倒くさがるどころか、むしろ喜々としている。
「僕はもう、仕事バカっていうか、ナレーションが好きなんです。何の抵抗もなくスーッと内容が入っていくようなナレーションができたら最高なんですが、ここはリズム感が悪いなとか、少しでも違和感のあるところは、何度も直します。自信がないから、逆に、とことん突き詰めちゃうんですよ。今日も何回、『もう1回お願いします』と言ったか(笑)。
それだけやっても完璧な仕事って、ないですもん。オンエアされた映像は恥ずかしいからあまり見たくないけど(笑)、仕方なく見ると反省するわけですよ。あそこはちょっとこだわりすぎたなとか、もっとサラッとやればよかったなとかね」
前職がしゃべりの仕事で生きた!?
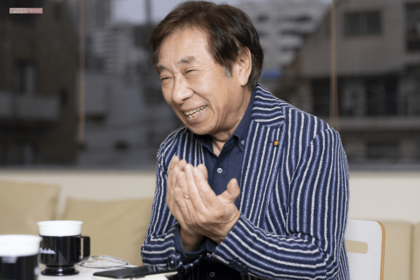
窪田さんが最初に“自分の声”を意識したのは、まだ小学2、3年生のころだ。国語の授業で音読すると、担任教師が「はっきりしている声だね。アナウンサーになるといい」と褒めてくれたことを、よく覚えている。
「読むことが好きだったから、うれしかったですよ。もともと算数よりも国語のほうが好きで、貸本屋に行って江戸川乱歩やシャーロック・ホームズを読んでいたし、中学生になったらSF小説を読みあさってました」
ナレーターという仕事があることを知ったのは中学生のときだ。窪田さんが生まれ育った山梨県でも、当時『ディズニーランド』(日本テレビ系)というアメリカのテレビ番組が放送されており、クレジットのナレーターという文字が目に留まった。
高校は自分で決めて山梨県立甲府工業高校に進んだ。会社員の父親も専業主婦の母親も、口出しをしなかったという。だから独立心が養われたのだろうか。その後の進路もすべて自分で決めたそうだ。
入学後すぐ運命的な出会いがあった。
「部活紹介の司会をした男子の先輩の声がやわらかくて、カッコよくて。なんてきれいなしゃべり方をするんだろうと、その人のしゃべりに魅了されちゃったんですね」
窪田さんは、その先輩が委員長を務める放送委員会に入った。たった1年間の付き合いだったが、ナレーションの仕事につながる大切なことを教わったという。
「やっぱりタイミングです。校内放送は『真珠貝の歌』に乗って、『みなさん、こんにちは』と始まる。先輩は、『窪田、どこで出る? これは、ここだよな』と、すごくやさしく教えてくれて。僕が3年のときには自分で台本を書いてラジオ作品コンクールにも出ました。そういう活動が好きだったんですね」
だが、どんなに好きでも、“声”の仕事につながる伝手など何もない。卒業を控えた窪田さんは冷静に進路を考えて航空会社の整備士の採用試験を受けた。中学生のとき熱心に読んだSF小説の影響で飛行機や宇宙が好きだったのだ。ところが健康診断で血尿が出てしまい断念。2週間入院して調べたが原因不明のまま退院し、教師のすすめで富士通に就職した。
川崎工場に配属され、担当した仕事は無線機の調整。
「技術者です。これで合格ラインだけど、この波形を調整すると、もうちょっと良くなるんじゃないかとか考えて仕事をしました。そうして粘り強く工夫したことは、今の仕事にも生かされていると思うんですよ」
「いいや、会社を辞めちまえ」

就職して3年が過ぎた21歳のころ。
《CMナレーター養成講座開講 受講生募集》
通勤で毎日乗っていた東横線で、こんな中づり広告を見かけた。すると、それまで忘れていた“声”への情熱が一気に蘇ってきた。
「ナレーターという文字がパーッと目に飛び込んできたんです。そうかナレーターか。勉強してみたいなぁと」
窪田さんは夕方4時55分に仕事が終わると、週3回、電車を乗り継いで銀座まで通った。さぞや楽しく学んだのかと思いきや、ひどく落ち込む毎日だったという。
「山梨のなまりがすごくて。アクセントの違いもあるけど、決定的にダメだったのは、母音の無声化ができないんですよ。僕は母音まで発音しちゃうからカクカクした感じに聞こえて、美しくないんです」
しかも受講生は俳優やアナウンサー志望の人ばかり。舞台や芝居などの話にもついていけない。
「みんなが話していることがわからなくてガーンときているのに、先生に怒られるでしょう。もう、先生の前でしゃべるのが嫌になっちゃった。非常につらかったけど、それでもやるしかない。一生懸命勉強して、微妙な音の違いがわかるようになって、やっと直すことができたんですね。今でもアクセントには苦手意識があるから、迷ったらすぐ調べるようにしています」
1年間の講座が終わると、テレビCMのナレーションの依頼が来た。窪田さんは会社を休んで収録に臨んだ。
「この放送が気になったら、××生命にお入りください」
自分ではうまくできたと思ったのに、オンエアされたCMを聞いて愕然とした。
「がっかりしたんですよ。下手くそだなって。でも、ディレクターたちの狙いは、いわゆるプロのしゃべりじゃなくて、素人っぽいしゃべりが欲しかったみたいで」
しばらくするとまた依頼が来た。だが、仕事が休めずに断ると、「じゃあ他の人に回す」とあっさり言われた。
そのとき、窪田さんは大きな決断をする。
「もし、仕事が来たのが1回だけなら、そのままだったかもしれないけど、また来たことで、気持ちが変わったんです。『いいや、会社を辞めちまえ』と。僕ってね、意外と単純な性質で、落ちたら危ないから川の深さを測るんじゃなくて、飛べるかどうかわかんないけど、飛んでしまえっていう、いいかげんなところがあった(笑)。それが幸いしたんでしょうね」
家族には相談しなかったのかと聞くと、そもそも両親には何も伝えていなかったという。辞表を出すと会社から山梨の実家に電話がかかってきたが、父親はこう答えてくれたそうだ。
「息子がやりたいことに口ははさみません」
パンツ一丁の仕事でも、何でもやる!

会社を辞めた2年後に24歳で結婚した。相手は会社の同僚で1歳年上。窪田さんが辞めるタイミングで一緒に住み始めたのだが、彼女はこんなふうに背中を押してくれた。
「好きなことをすればいい。ダメだったら私が食べさせてあげる」
窪田さんはその言葉にすごく励まされたと感謝する。
「もし、ちゃんとしてくれなきゃ困るとか言われていたら、僕は弱いところもあるから、ふにゃふにゃになっていたかもしれない。だけど、なんとかなると言ってくれて、すごく気持ちが楽になりました。まあ、相手もいいかげんだったんでしょう(笑)」
妻は結婚後も富士通で働いていたが、「妻を働かせて夫はフラフラしている」と思われるのが嫌で、結局、辞めてもらったという。
いわば自ら退路を断ったわけだが、ナレーションの仕事が来るのは1週間に1度くらい。事務所からの電話を待つしかなく、「明日の仕事はなくなった」と一方的にキャンセルされることも。窪田さんは「わかりました。またよろしくお願いします」と言って静かに電話を切った瞬間に、「この野郎!」と悔しさを爆発させた。
次の仕事につなげるため、来た依頼は断らなかった。
「パンツ一丁でやった仕事もあります(笑)。『裸一つで全部そろいます』というコンセプトの百貨店のCMで。広告代理店の新年会のゲスト呼び出し係とか、銀座祭りのパレードの案内とか、声じゃない仕事でも何でもやりました」
そのころ、よく見ていたのは新聞の折り込み広告の求人情報。高度経済成長は終わりかけていたが、まだ働き口はいくらでもあり、「もし、今の仕事がダメでも会社勤めに戻ればいい」と考えると、不安が消し飛んだ。
生活を支えるため友人が紹介してくれた印刷会社でアルバイトもした。テレビ局の収録で使うために印刷・製本した台本を運ぶ仕事だ。
ある日、アルバイト先に大手広告代理店のラジオCMディレクターがやってきて、窪田さんは驚いた。ナレーター養成講座で講師をしていた男性で、この偶然の再会をきっかけに、レギュラーの仕事に抜擢してくれた。
「僕のことを『あいつ心臓に毛が生えているから何でもやるぞ』と言ってくださって、それから仕事が好転していったんです。僕はただ単に、人のご縁に恵まれたのと、運がよかったんですよ」
その言葉を受けて筆者が「窪田さんのナレーションへの愛が、運を引き寄せたんじゃないですか」と感じたままを口にすると、窪田さんはハッとした顔をして、考え込んだ。
「そんなふうに考えたことなかったけど……、何のとりえもない僕がずっと続けることができたのは、そうか、ナレーションの神様が引き寄せてくれたのか……」
大御所の現場で決意。「ああはならないぞ」

今の窪田さんからは想像もできないが、若いころはラジオCMなど短いセリフの仕事が多く、長いナレーションが苦手だったという。
「収録の途中で何回も間違えると、へこたれますよね。で、ブースの中で『なんで読めねえんだよ、おまえは』って言いながら、自分の頭をポカポカ叩きました」
方言を直したときと同様、努力で克服した。新聞の社説など長い文章を声に出して繰り返し読み、文章の流れをつかんだのだ。
「ナレーターとしてのプライドは持っていなきゃいけないけど、その出来に対してのプライドは捨てるしかない。自分がダメだったら素直にやり直すしかないですよね。
でも、一度見学させてもらった大御所は違いました。明らかに変なのに、『どこが悪いんだ』と怒り出して。それを見て、『僕は、ああはならないぞ』と思いましたね」
テレビやラジオなどエンタメ以外の仕事もたくさんやった。意外なところでは、公共の建築物ができたときに建築記録を音声で残す仕事。窪田さんと30年以上苦楽を共にした元マネージャーの川村道彦さん(71)によると、全国の空港や橋
梁など多くの建物の建築記録を窪田さんが読んでいるという。
「あまり表に出ない技術的な解説の仕事ですが、窪田さんはもともと技術者だったこともあり、すごくやりがいを感じていました。難しい内容をわかりやすく理解してもらうために、文章のどこに要点があって、どこで区切って、何を強調して読み進めるかという、読み方の研究をすごくされたんです。その積み重ねで、彼の読みは、より説得力を持ったのだと思います。
CMやドキュメンタリーでも、普通は与えられた文章を読むだけですが、彼の中には作家さんの意図を視聴者に100パーセント伝えたいという思いがあるから、映像や音楽の邪魔にならないようにして、全部を生かそうとする。だから、制作の方にも好感を持っていただけるのだと思います」
いつまでもOKが出ない深夜のYouTube収録

こうした不断の努力に裏打ちされた窪田さんのナレーションは高く評価され、仕事の場はどんどん広がっていった。代表作の『情熱大陸』の他にも、『F1』(フジテレビ系)、『THEフィッシング』(テレビ大阪、全国TX系)、『もうひとつの箱根駅伝』『24時間テレビ』(共に日本テレビ系)など長く担当する番組は多い。
ナレーションは基本的にスタジオで事前に収録するが、ごくまれに「生」で話すこともある。長いナレーター人生でヒヤリとした瞬間は一度や二度ではない。
忘れられないのは、2017年12月に放送した『情熱大陸』。神戸でクリスマスツリーを立てる様子を生放送で伝えるため、窪田さんも外で原稿を読んだ。ところが、放送が最後に差しかかると5秒余ってしまいそうに─。
窪田さんはとっさに思い浮かんだ言葉を口にした。
「神戸の港から、少し早いけれど、メリークリスマス!」
言い終わった直後に放送が終わり、中継車から「ワアッ」と歓声が上がった。
そのとき中継車に乗っていた映像ディレクターの三木哲さん(47)にとっても、忘れられない出来事だという。
「あのときは本当に感動しました。僕もタイミングを遅らせながらキュー(合図)を出したりしたのですが、窪田さんが最後の最後に、いきなりアドリブで言ってくださって。鳥肌が立ちました。それで尺もバッチリ収まったし、番組全体も締まったんです」
近年は仕事以外の活動にも力を入れている。きっかけは東日本大震災だった。
「みなさん、炊き出しに行ったりしていたけど、僕はそんなことはできないし、せっかく声の仕事をしているのだから、この声を生かして何か役に立つことができないか。そう思っているとき、マネージャーの川村さんに『窪田さんの声は癒しになるから』と言われて、聞いた方が少しでもホッとできたらと」
構成作家やスタッフもノーギャラで協力してくれて、ラジオ番組をつくり、YouTubeで公開した。
コロナ禍では「窪田等の世界」をスタート。太宰治、芥川龍之介、宮沢賢治など著作権フリーの「青空文庫」の作品を朗読して、YouTubeで毎週配信している。
「コロナで『情熱大陸』の収録をリモートでやることになって、マイクが自宅にきたんです。パソコンにマイクを挿したら録音できる。こんなに簡単なら、自分でも発信できると思ったんですね」
作業をするのは仕事を終えて帰宅した後の時間。夜中の3時過ぎまで収録を続けることもざらだ。
「翌朝早いし、よせばいいのに聞き直して、『あ、ここはちょっと変だな、もう1回録ろうかな』とか、なかなかOKが出せない。自分1人だから終わりがないんです(笑)。
つらいな、苦しいなと思いながら、なんとか綱渡りで4年間毎週続けているってことは、文章を読むことが好きなんだな。やっぱり、ナレーションの神様がいるんですかね」
ヤンチャな娘に見せた意外な父の顔

仕事人間の窪田さんだが、プライベートでは3人の子どもの父親でもある。家ではどんな「お父さん」なのか知りたくて、末っ子の愛さん(40)に聞くと、自分が結婚したときのエピソードを教えてくれた。
「兄と姉はまじめなのに、私だけ若いときは派手な格好をしていたんですよ。私の旦那は芯の通った男なんですけど、見た目がちょっといかつくて眉にピアスをしていて。父は結構、躾に厳しいイメージだったから、旦那を父に会わせるとき、すごく不安だったんです。
で、彼が帰った後に、どうだったと聞いたら、父は『愛が選んだ人だから』と言ってくれて。それって、私のことを信頼してくれているってことじゃないですか。本当にうれしかったですね。ああ、自分の父が父でよかったとすごく思いました」
現在は2児の母である愛さん。子どもを連れて水族館に行ったら展示物の解説の声が窪田さんだったり、電化製品を見に行ったらゲーム売り場のCMから窪田さんの声が流れてきたり。窪田さんが朗読した『杜子春』が娘のクラスの授業で偶然使われたこともある。
「うちの子どもたちも最初は驚いていましたが、あちこちで聞くので、今は『じじ(の声)じゃん』みたいな軽い感じです(笑)。
最近、父は鼻の調子が悪いみたいで、実家に行くと録音を聞かされてノイズがどうとか言うけど、私には違いがわからない(笑)。そうやって家でも常に仕事のことを考えていますよ」
これまで、1日に最高で8本の仕事をこなしたことがある。今でも複数の仕事を掛け持ちすることは多いが、窪田さんは意に介さない。
「仕事で緊張して、終わるとほぐれて、また緊張してほぐれて。切り替え、切り替えだから、もつんですよ。ずーっと緊張ばっかりだとダメだと思うけど」
『情熱大陸』の放送は1300回を超えたが、休んだのは1回だけだ。心筋梗塞で救急搬送され、カテーテル手術を受けたのだが、翌週には復帰した。
特別な健康法があるのかと聞くと、窪田さんは「何もないんですよ。あるがまま」と言って笑う。
「風邪をひくこともありますよ。切れ味のいいカミソリみたいな繊細な声だと大変でしょうけど、僕の場合、鉈みたいなぶっとい声だから、そんなに気を使わなくても、なんとかなってきた。本当にあるがまま。ただ現場を楽しんでいるだけなんです」
そこで言葉を切ると、少し遠くを見つめて、続ける。
「それでも、いつか読めなくなる日はくるんだろうなぁ。読めなくなったら何をしたらいいんだろうと、ふっと考えたりしますよ。でも、『窪田さん、もういいよ』って断られるまで、頑張ってみようと思っています」
最後のセリフに迷いはなかった。
<取材・文/萩原絹代>

