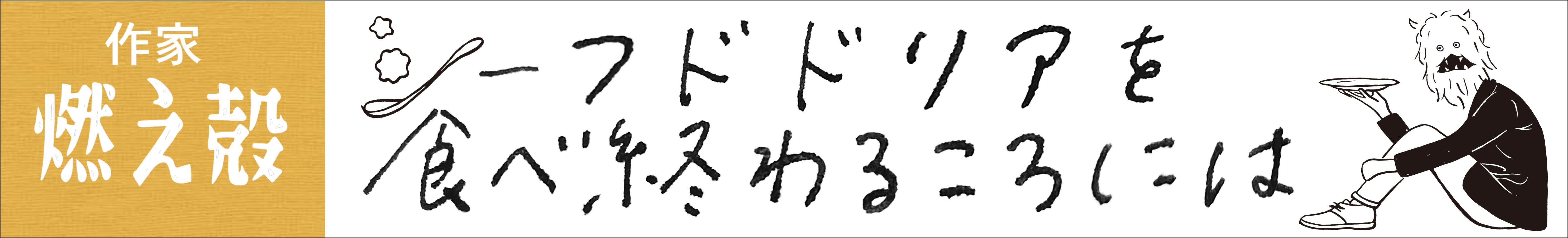ある料理、ある酒を口にするとき、将又(はたまた)、ある店であのメニューを頼むとき、ふと思い出してしまう人―。料理やお酒をきっかけに引き出されるあの日、あの人を描く。グルメじゃないけど、僕にとっての忘れられない味は……。
* * *
四十年とちょっと歴史がある居酒屋が、半月前にひっそり閉店した。木造の二階建て、築五十年はくだらない佇まい。お品書きはすべて店主の手書き。日本酒と芋焼酎の種類はピカイチで、お通しの角煮は、口の中ではらはらと崩れて溶けるほど柔らかく、味もしっかり染みていた。
親戚のおじさんよりは近しい存在
僕はその店に三十代前半から通っていて、人生で初めてボトルを入れた店だった。焼酎のボトルに、サインペンで自分の名前を入れるとき、大人になれた気がして、嬉(うれ)しかったのを憶(おぼ)えている。店主のことを常連客は「おっちゃん」と呼び、慕っていた。
カウンターにはいつも、近くの小学校の子供たちが遊びに来て、夕方から夕飯時まで、漫画を読んだりしながら時間を潰(つぶ)している。早くから飲み始める常連客たちは、子供たちの学校であった出来事や最近の子供事情を肴(さかな)に日本酒をひっかけるのが恒例だった。
おっちゃんは、子供たちにとって、親よりは遠いが、親戚のおじさんよりは近しい存在に見えた。それは僕たち常連にとっても同じだった。常連客同士の結婚式、あるときは葬式。誰よりも涙しながら参列するのが、おっちゃんだった。
閉店を決めた理由は、おっちゃんの腰痛と、店を切り盛りしていた奥さんが、コロナにかかって以降調子が戻らないこと。最後の半年は、常連が何人かでシフトを組み、店を手伝った。僕も数日だけ、厨房(ちゅうぼう)で慣れないサワー作りなどをした。
「氷多いだろ!」とか「チャッチャ動けや!」と、とにかくおっちゃんからの怒号が凄(すご)い。「ハイハイ」と最初はみんな我慢していたが、「チッ」と見事な舌打ちをし始める常連もいた。
それでも、「おい、お母ちゃんどうなんだ?」と僕の母が体調を崩していることを憶えていて、気遣ってくれたり、「来週、お前のかみさん誕生日だろ」と手伝っていた常連の奥さんの誕生日を憶えていて、お土産を渡してくれる。
いつかの年越し、店でみんなそろって迎えたときの額装された写真を眺めながら、おっちゃんが手ぬぐいで涙を拭ったときは、いい年をしたおっさんばっかりの常連たちが、釣られて涙を流した。おっちゃんの店にいると、いつもより口が悪くなって、いつもより優しくなって、いつもより涙もろくなってしまう。
最終日の前夜、僕はシフトに入って、洗い物や片付けを手伝った。深夜0時に閉店すると、パチパチパチと小さく拍手が起こる。おっちゃんの奥さんが、「ヤダ、あと一日あるのよ」と笑う。おっちゃんもニコニコしながら、手を動かしていた。
僕は「一緒に宇都宮に行って餃子を食べ歩きする」という約束を今年中に果たそうと、抱き合いながら伝えた。
宇都宮はおっちゃんの地元で、何度も「おっちゃんオススメの店何軒かを食べ歩きしよう」と話していたのに、実現できないままだった。おっちゃんは「これでこっちは暇になるんだから、行こうぜ!」と笑顔で洗い物をしながら答えてくれた。
僕が暖簾(のれん)をくぐって外に出ると、その店でしか会わないが、二十年くらい顔見知りだった男性が店先でタバコを吸っていた。男性が、「聞いた? おっちゃん、かなり悪いらしいよ」と心臓あたりを指差す。
腰痛以外で身体が悪いことを僕は知らなかった。タバコの煙を吐きながら、男性は「なかなか難しいですね」とこぼして店に戻った。
おっちゃんは店を閉めてから、二週間も経(た)たずに入院した。容態は落ち着いているが、この原稿を書いている現在もまだ入院したままだ。
いまから六年前、僕は一度だけ、両親に鮨(すし)をご馳走したことがあった。最初の小説の印税が入ったとき、絵に描いたような親孝行を一度きっちりしたくなって、銀座の鮨屋に両親を誘った。
母は「そんなお金があるなら貯金しておきなさい」と何度も言ったが、父は「そうか、ありがとう。お母さんと一緒に行くよ」と母を説得してくれた。
店はカウンターのみで、客は僕ら三人だけ。日本酒を父に注ぐと、いつも不機嫌そうな口元が緩む。父が僕のおちょこにも日本酒を注いでくれる。一口で僕がそれを飲み干すと、父もくいっと飲み干した。
「よくやってる」
ひと言だけ、父がつぶやく。その言葉にホッとして、僕はその日やけに酔っ払ってしまった。支払いを済ませて外に出ると、父が「ごちそうさまでした」と笑顔を見せてくれた。その後すぐ、僕がタクシーを止めようとしたときだ。父が、「うう……」と唸(うな)り声をあげて、路上に倒れてしまった。
母はなぜか、異様に冷静で、父親のベルトを緩め、ボタンを外し、意識を確認する。僕は慌ててしまって、スマートフォンで救急車を呼ぼうとするが、住所がわからず混乱状態に陥る。結局、救急車は通りすがりの人が手配してくれて、救急病院に運ばれた。
夜の待合室で母親とふたり、診断結果を待つ間、久しぶりにゆっくり話した。
「お父さん、嬉しかったのよ。嬉しくて飲みすぎちゃったのよ。ばかねえ」と母は呆(あき)れるように笑った。
僕が二十歳になり、成人式に向かおうとしたとき、父はわざわざ僕を呼び止め、「お前とこれで酒が飲めるんだな」と言ったことがある。僕はあの日、なんと答えただろう。どうしても思い出すことができない。
結局、四十代半ばまで、父と酒を飲んだことは一度もなかった。大人同士の約束は、ときに月日を要する。果たされず、約束を交わした事実だけが標本のように大事に保管されることすらある。
「普通に大学に入って、普通に就職して、普通に孫の顔を見せてくれ」
それが父の、僕への希望だった。その「普通」は、僕にとってはオリンピックで金メダルを獲(と)るくらいに難しいことだった。父の理想と僕の現実は、今のいままで寄り添うことがなかった。
真っ暗な病院の待合室で、急に父に申し訳なくなって、こみ上げてくるものがあった。僕が堪(こら)えようとして踏ん張ったとき、母が隣で「あなたたち、ばかねえ」と僕よりも先に涙を流してくれた。

燃え殻(もえがら)●1973(昭和48)年、神奈川県横浜市生まれ。2017(平成29)年、『ボクたちはみんな大人になれなかった』で小説家デビュー。同作はNetflixで映画化、エッセイ集『すべて忘れてしまうから』はDisney+とテレビ東京でドラマ化され、映像化、舞台化が相次ぐ。著書は小説『これはただの夏』、エッセイ集『それでも日々はつづくから』『ブルー ハワイ』『夢に迷ってタクシーを呼んだ』など多数。
『BEFORE DAWN』J-WAVE(81.3FM)
毎週火曜日26:00〜27:00放送
公式サイトhttps://www.j-wave.co.jp/
※本連載の一部を燃え殻さんが朗読するコラボ企画を実施中