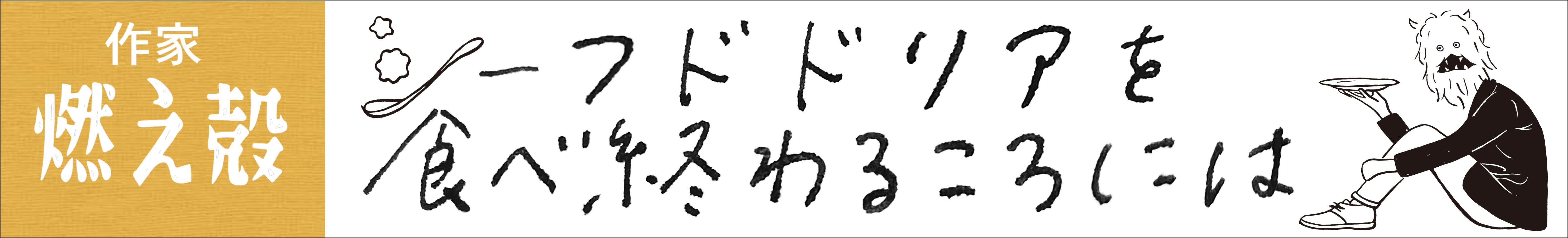ある料理、ある酒を口にするとき、将又(はたまた)、ある店であのメニューを頼むとき、ふと思い出してしまう人―。料理やお酒をきっかけに引き出されるあの日、あの人を描く。グルメじゃないけど、僕にとっての忘れられない味は……。
* * *
「あのう、シェフの気まぐれサラダって何が入っているんですか?」
一緒に食事をしていたライターの女性が、注文を取りにきた居酒屋の店員にそう聞いた。
冒険を避ける彼女
「あ、シェフの気まぐれなんで、シェフ次第なんです……」
店員は申し訳なさそうにそう答える。そりゃそうだ、と僕は心の中で思いながら、「ホッケ焼きください」と告げる。ライターの女性は悩んだ末、「じゃあ、シーザーサラダで」と冒険を避けた。
別の日に焼き鳥屋で彼女と一緒に飲んだときも、「すみません、このおまかせ串六本って、何がくるんですか?」と聞いていたのを憶(おぼ)えている。店員は「おまかせなので、その時々で違うんです」とこの上なくまともな説明をし、「なるほど。では、レバーとつくねとハツをください」と彼女はまた冒険を避けた。
飲食店のメニューにしばしば登場する、「店に身を委ねる系メニュー」。僕がテレビの仕事をしていた頃は、とにかく時間に追われていて、早く食事を済ませるよう求められたので、「おまかせ」や「おすすめ」をサクッと選んで終わらせていた。メニュー選びに割く時間すら短縮したかったからだ。
その癖が抜けず、僕は店に身を委ねがちだ。でも彼女のように、ベールに包まれた1品が気になりつつ、中身が分からないなら頼まない慎重派もいることをそのとき知った。
それから季節は冬から春へ。出会いと別れが交錯しがちな門出のシーズンを迎えるころ、ライターの彼女から“人生の冒険をやめる”という主旨のメールが突然届く。
〈これから先のことを考えたら、ライター業は不安定だから、結婚して普通に生きてくわ〉
誰もが知っているIT企業の日本支社の四十代の男と、彼女はマッチングアプリで出会って、あっさり結婚したらしい。そのメールを最後に連絡も途絶えてしまった。
正月にテレビを観ていると、いろいろな店に置かれている福袋の中身を公開する番組をやっていた。デパートの寝具コーナーでは、枕カバーやシルクのパジャマ等のグッズ。化粧品コーナーでは、ブランド品の詰め合わせ等、福袋の中身は価格の五倍以上の商品が入っていると、一点ずつカメラに映して説明していた。
最近では中身がわかるように、福袋を透明のビニール袋にしているところもあるらしい。誰もがハズレを引きたくないのだ。外せる余裕がなくなってしまったのかもしれない。
その番組を観ながら、ふと彼女のことを思い出して、何気なくフェイスブックを検索してしまった。
彼女はいま、東北地方のとある温泉地で古民家カフェを経営しているらしい。お子さんはふたり。まだ上の男の子は小学一年生。旦那さんとは離婚して、ライターをしていた当時の友人とカフェ経営を始めたことが、長い文章で書かれていた。
夏は近くの森でキャンプをすること、まるで野良猫のようによく遊びにくる馴染(なじ)みのリスがいること。冬は積雪が三メートルにもなるらしく、慣れない雪かきに奮闘する様子。一面真っ白の世界が色を消し去り、森の木々が奏でる音、風のささやき、動物たちの生活音、人々のおしゃべり、それらすべての音が、雪に消されてしまう不思議について、丁寧に書かれていた。
初めての経験ばかりで不安なことは間違いないが、毎日を楽しんでいる様子が文面から伝わってきた。安定を求めた先で不安を買って、「いま」を懸命に生きているように見えた。
僕が作家になる前、彼女に「小説を書いてみようかと思う」と打ち明けたことがある。テレビの下請け業をやっていた僕は、この先テレビ業界がどうなるのか、自分の人生はこのまま大きな大流に身を任せるだけでいいのか、悩んでいた。先が見えない深い霧がかった自分の人生に心からの不安を感じていた。
ただ、人から勧められて書き始めた文章が思いのほか好評だった。食べていけるかどうかの保証はまったくないが、散文を本格的な小説にしてみないか?という話がきていることや、それが不特定多数の人に必要とされた気がして嬉(うれ)しかったことを彼女に話した。ほんの少しだが、「自分への期待」を持つことができた喜びを彼女に伝えた。
「人生は一度きりだもんね。やってみたら?」と言った後、彼女は少し考えて、「でも、あなたがステージに立つことは想像できないかも……」と、いつもの冒険しきれない彼女が顔を出し、そう付け加えた。
僕は「そうだよね。どうしようかな」と返答して、冒険を選んだ。
でも、今ならわかる。表現をすることは、ステージに立つような眩(まぶ)しい職業ではない。他のあらゆる仕事と同じく、節度とルールと誠実さが求められるところだった。
クライアントが何を欲しているか、それを予算内でどう実現するかが求められ、そこに自分の個性をうまくちりばめる。右に行っても、左に行っても百点はない。八十三点と七十九点を彷徨う世界だ。
どちらの道が正解か?ではなく、ゴールまで諦めず、腐らず、楽しめる道はどっちか?という選択の繰り返しだった気がする。
あのときは霧がかって、ただただ険しく遠く見えた世界で、僕はまだ物を書いて生きている。他の仕事と同じ構造だと理解できたころから、グッと気持ちが楽になって、今もほんの少しだが、自分に期待している。
いつかどこかで彼女と、お互い諦めず、腐らず、なんとか楽しんでやってきた過程で起きたことを話せたら嬉しい。きっとそのときは、シェフの気まぐれサラダを彼女が平気で頼んで、ふたりでシェアして食べられるようになっているはずだから。

燃え殻(もえがら)●1973(昭和48)年、神奈川県横浜市生まれ。2017(平成29)年、『ボクたちはみんな大人になれなかった』で小説家デビュー。同作はNetflixで映画化、エッセイ集『すべて忘れてしまうから』はDisney+とテレビ東京でドラマ化され、映像化、舞台化が相次ぐ。著書は小説『これはただの夏』、エッセイ集『それでも日々はつづくから』『ブルー ハワイ』『夢に迷ってタクシーを呼んだ』など多数。
『BEFORE DAWN』J-WAVE(81.3FM)
毎週火曜日26:00〜27:00放送
公式サイトhttps://www.j-wave.co.jp/
※本連載の一部を燃え殻さんが朗読するコラボ企画を実施中