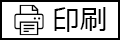駅に何気なく貼ってあった『九都県市受動喫煙防止キャンペーン』のポスター。スモーカーに眉をひそめるモデルの女性の表情がリアルなのでつい見入ってしまった。
ネットで調べてみると、毎年「がん征圧月間」とされている9月から11月までの期間に行われている健康増進キャンペーンのようだ。2020年4月から施行された受動喫煙防止法に関連して行われているのだろうか。
「九都市」とは、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県と、横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市だという。横浜市と川崎市、相模原市は神奈川県であり、実質関東地方の1都+3県で開催されているようだ。これらのキャンペーンを行う予算は、もちろん税金から出ているのであろう。
この九都県市の理由や、ポスター掲示以外の活動はあるのだろうか。また、効果測定はどのように行っているのだろうか? 今回は、主要な都県市である「東京都」「千葉県」「埼玉県」「神奈川県」「横浜市」の5つの自治体に、それぞれが行っている活動や予算規模について取材を行った。
活動内容は「ポスター」の掲示や配布がメイン
まず、この活動について各自治体に問い合わせた結果、このキャンペーンは平成21年(2009年)から行われており、実に15年以上もやっているキャンペーンであることがわかった。相模原市は翌年の平成22年(2010年)から参加し、現在の九都県市という形になったようだ。
キャンペーンは、毎年9月の「がん征圧月間」からスタートし、11月までの3ヶ月間行われる。「九都県市共通のロゴマーク」を使用し、主にポスターや電子掲示物の制作・掲示や配布を行っているという。ポスターデザインは共通だが、それをどのように配布するかは、あくまで各自治体によって違うようだ。
また、「幹事」を持ち回りで行っており、令和6年度に関しては、神奈川県が幹事を行っているという。この「幹事」については、活動の呼びかけや諸連絡をリードするポジションということで、特に活動全体の方針を決めるというものではないようだ。
東京都以外は、県とその内包する市が両方参加している。特に神奈川県は「横浜市」「相模原市」「川崎市」を内包しているが、取り組みの棲み分けはどのように行っているのだろうか。
神奈川県と横浜市それぞれに同様の質問を行ったところ、「具体的な手法は様々ですが、受動喫煙防止のため、県市では地域の状況に応じて取り組んでいます」という神奈川県の回答に対して、横浜市は「健康増進法に基づく事務は、政令市及び保健所設置市がそれぞれの市域の事務を担い、県はそれ以外の地域の事務を担っています」と回答した。基本的に県内の活動については把握していないようで、ふわっとした印象は否めない。
予算は0円〜100万円まで自治体によりまちまち
では、このキャンペーンには予算がどれくらいかかっているのだろう。我々の税金からの支出であるため、知る権利があるはずだ。各自治体に問い合わせた、本キャンペーンの令和6年度の予算についての回答は以下の通りであった。
「予算は100万円程度で、今年度60万円ちょっと使っている」(東京都)
「予算は10万円で、今年度の支出額は7万3000円程度」(千葉県)
「費用はかけずにキャンペーンを実施している」(埼玉県)
「令和6年度の支出については、ポスター作成 の2万6000円あまり」(神奈川県)
「令和6年度の実績額については約150万円 です」(横浜市)
上記の回答から、それぞれ自治体によってキャンペーンに関する予算には開きがあることがうかがえる。都市ごとの人口など規模は大きく違うものの、「合同」と名がつくわりには、活動の足並みが揃っているとは言い難い印象だ。
大きく異なる各自治体の活動内容と、温度感

続いて、キャンペーンにおける活動内容を各自治体にヒアリングした結果、活動の基本は、共通のデザイン、ロゴマークを使用した「ポスターの掲示や配布」であった。
デザインについては、記事トップに掲載した2種類で、横浜市によると、
「こちらのデザインは、平成30年度に刷新しましたので、それ以降については、こちらの2種類のデザインを九都県市共通で使用しています。なお、キャンペーンの趣旨を損ねない範囲で、語句やイラストなどを変更することは可能となっていますので、年によっては、各都県市の状況に応じてアレンジする場合がございます」
ポスター配布の場所や方法、規模感については自治体ごとに大きく異なっている。
東京都の場合、東京メトロの160の駅にポスター掲示をしたほか、都営地下鉄でも掲示場所の指定はしていないが、浅草線の5駅に掲示を行ったという。
千葉県はポスターを2種類・600枚制作し、JR県内各駅や郵便局、警察本部(警察署含む)、関係団体、県有施設に掲示。

埼玉県は「ポスターを制作し、広く広報」、そして県民から希望があればポスター送付の対応を行っているという。
神奈川県はポスター380枚を作成し、「県保健福祉事務所や県政総合センター等の県施設をはじめ、県内市町村や協力企業・団体、病院等に掲出を依頼しました」と回答。また、横浜市はポスター225枚を区役所・薬局・市内大学に配布したという。
また、神奈川県や横浜市では、動画を制作しSNSやデジタルサイネージ等で配信するなど、独自の受動喫煙防止キャンペーンを併せて実施しているという回答があった。とりわけ横浜市では、喫煙所利用者の位置情報を活用して喫煙者のスマホにピンポイントで広告配信、路上喫煙者の多い場所でのパトロール実施や看板の掲示、屋内禁煙など健康増進法に違反する店舗への指導、街頭キャンペーンや禁煙支援などを行っている。いっぽう「本県ではポスター掲出以外実施してはいません」(千葉県)など、自治体によって活動の温度感には大きな差異があるように感じられた。
また、キャンペーン期間中に情報交換をすることもあるそうだが、内容については回答が得られなかった。情報交換はしていると言いつつも、それぞれ他の自治体の活動状況について把握しているということもないことがうかがえる。この活動の大半はポスター掲示が主であり、その他の目立った活動を行っていないというのが現状のようだ。
受動喫煙防止キャンペーンの現在の意義は?

九都県市受動喫煙防止キャンペーンについて行政から得た情報をまとめると以下のようになる。
・平成21年から開始(相模原市は平成22年から参加)
・がん征圧月間である9月から、11月の間までに行う
・主に共通デザインのポスターの制作・掲示、配布などを行っている
・九都県市共通のロゴマークを各自治体の取り組みに使用している
(共通の活動である意義は薄い)
さて、ここで疑問が湧いてくる。もちろん受動喫煙は防止すべきものだが、2020年から改正健康増進法が施行され、飲食店などお店を含む公共の屋内では、ほぼ喫煙できない状態になっている(改正健康増進法のポイントはこちら)。つまり、受動喫煙の機会というものが、日常からかなり姿を消している現在でも、このキャンペーンを続ける意味はあるのだろうか?
後編では九都県市受動喫煙防止キャンペーンがそもそも起こった背景や、この九都県市になった座組について、そして気になる効果測定の方法などについても聞いていく。
<取材・文/白石優>