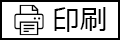《キャンバスに夢中になりて描きゐしかの日のことはなほあざやかに》
新春恒例の「歌会始の儀」が1月22日、皇居・宮殿「松の間」で行われた。今年のお題は「夢」で、天皇、皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻と次女、佳子さまらが詠んだ歌、それに応募作約1万6250首から選ばれた10人の入選者の歌などが、伝統的な発声と節回しで披露された。
時間を忘れて絵を描かれていた佳子さま

鮮やかなブルーのローブ・モンタントと帽子姿で出席した佳子さまの歌が冒頭のものだ。宮内庁の説明によると、佳子さまは、幼少のころから、絵を描いたり、工作や手芸でさまざまなものを作ることが好きだった。今ではそのように過ごす時間が限られているけれども、以前に描いた絵を見ると佳子さまは、絵を描いていた日のことを鮮やかに思い出すらしい。時間を忘れて絵を描いていたころを懐かしみながら、この歌を詠んだという。
両陛下に続いて、秋篠宮ご夫妻と佳子さまが入場した。佳子さまは、両陛下の前を通る際に丁寧に頭を下げ、両親と並んで席に着いた。
《絲と針夢中にオヤを編む先に二つ三つと野の花が咲く》
昨年12月上旬、秋篠宮ご夫妻はトルコを公式訪問した。糸と細い針を使ってスカーフなどの縁飾りを編む「オヤ」は、トルコの人々の間で長い歳月にわたって受け継がれてきた、きめ細やかな手仕事のひとつだ。紀子さまはトルコ訪問前にオヤを習い、帰国後もオヤの作品を編んでいるという。トルコの自然や人々の暮らしを思いながら夢中になって野の花を二つ三つと続けて編んだことを歌に詠んだ。
紀子さまの歌に続いて、秋篠宮さまの《初夢に何を見たのか思ひ出でむ幼き頃の記憶おぼろに》という歌が紹介された。正月、枕の下に「宝船」の絵を入れて眠りにつく習わしがあるが、秋篠宮さまは幼少時代、そのようにして寝ていたという。今回のお題が「夢」と聞いて、真っ先にこのことを思い浮かべたが、何の夢を見たのかは記憶が曖昧であるという思いを歌に詠んだらしい。
《我が友とふたたび会はむその日まで追ひかけてゆくそれぞれの夢》
この歌は、今回、「歌会始の儀」に初めて出席した、両陛下の長女、愛子さまが詠んだものである。昨年3月、学習院大学を卒業し、翌月からは社会人として日本赤十字社で勤務している。大学の卒業式、一緒に卒業する友人たちの晴れ姿を見て、学友も自分自身も、これからそれぞれの新たな道を歩んでいくことをしみじみと感じ、学友とのこれまでの日々と将来に思いを馳せた。
また、同じ大学には通わなかったけれども、別の道で夢に向かって歩みを進めている友人とのつながりも大切にしている中で、友人たちといつの日か再会できることを楽しみにしながら、その日までそれぞれの夢に向かって励んでいこうという、初々しい気持ちを詠んだという。
令和初めての「歌会始の儀」

2020年1月16日、「令和」となって初めての「歌会始の儀」が行われた。天皇陛下とともに皇后雅子さまも出席したが、病気療養中である雅子さまにとっては、'03年以来、17年ぶりとなる「歌会始の儀」への出席となった。
欠席した'04年1月の「歌会始の儀」の雅子さま(当時は皇太子妃)の歌は、《寝入る前かたらひすごすひと時の吾子の笑顔は幸せに満つ》だった。これは、公的な仕事から東宮御所に戻った雅子さまが、愛子さまが寝る前のひととき、ベッドの傍らでいろいろな話をした際に、愛子さまがあどけなく幸せそうな笑顔を見せたことに安堵し、将来にわたって愛子さまの幸せを願って詠んだものだという。
また、'07年の「歌会始の儀」で披露された歌は、《月見たしといふ幼な子の手をとりて出でたる庭に月あかくさす》だ。月見の時季の夕方、愛子さまが「お月さまが見たい」とせがみ、雅子さまは愛子さまと東宮御所の庭に出た。そして、ふたりで月見をした情景を詠んだ歌らしい。
さらに'09年では、《制服のあかきネクタイ胸にとめ一年生に吾子はなりたり》である。'08年4月、愛子さまは学習院初等科に入学した。小学生となった愛子さまが、新しい制服を着た喜びを歌で表現した。このように、「歌会始の儀」で披露された歌を見る限りにおいても、雅子さまと愛子さまがいかに強い絆で結ばれているのかがよくわかる。体調回復に向けて療養に励む雅子さまにとって、愛子さまが大きな支えとなっている。娘の健やかな成長と幸せこそが、何よりの薬なのかもしれない。
「やはり、愛子さまが出席したからでしょうか。今年の歌会始の儀は、皇后さまがとても楽しそうに見えました」
このような感想を知人が伝えてくれた。皇室の人間模様が、三十一文字を通してより深く味わえるところがとても興味深い。
歌会始の選者で山梨県立文学館長の三枝昂之さんは、佳子さまと愛子さまの歌の特徴などを次のように解説した。
「佳子さまは、表現力を感じさせる歌ですね。お題の『夢』を、夢そのものではなく『夢中』と自分の行為に引き寄せて、結句を『なほあざやかに』と余韻の広がる言いさしに近い形で収めた点に工夫が光ります。
愛子さまは、卒業という節目を経て新たな一歩を踏み出したときの歌ですが、キャンパスライフを振り返っての感慨ではなく、これからの、前を見つめた友情と志の歌です。『それぞれの夢』とお題の『夢』の受け方がオーソドックスで、名詞止めのスタイルにも安定感があります」
三枝さんによると、今回のおふたりの歌の特徴は結句によく表れているという。
「『夢』は人生への肯定が広がるお題ですが、佳子さまは過去のある日の忘れがたさを、愛子さまはこれから始まるきらめきを通して、お題のイメージをよく生かしています。その点は同じですね。
宮中の歌会始は、一つのお題のもとで多くの人が心を寄せ合い、新しい年を祝福する儀式ですが、その特色をおふたりの歌がよく担われたことが心強いです」
これからも佳子さまと愛子さまの歌がとても楽しみだ。
<文/江森敬治>