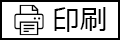2020年4月に全面施行された「改正健康増進法」によって、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わり、公共施設をはじめ、オフィスや飲食店など屋内は原則として禁煙となった。それに伴って街中に見られた灰皿の多くが撤去されたが、歩きたばこや吸い殻のポイ捨てなどの迷惑行為が目立つようになったという声も聞く。あれから5年、望まない受動喫煙の防止や環境美化を推進するためにも分煙施設の設置が推奨されているが、各自治体はどのような対策を行なっているのだろうか。【大都市の分煙事情】として3日連続で、全国9つの大都市の役所に取材し、現状をお伝えする。
今回は北海道の中心札幌市、東北一の大都市仙台市、そして日本の首都東京都の取り組みに迫る。
さっぽろ雪まつりで導入されたユニークな喫煙所

年間を通して国内外から多くの観光客が訪れる札幌市。特に札幌の冬を彩るさっぽろ雪まつりは、今年も2月4日から11日までの1週間でおよそ233万人もの来場者を記録し、大いに盛り上がりを見せた。その会期中は中国の旧正月・春節とも重なり、雪まつりの会場には多くの中国人観光客が集まったが、中国には3億人もの愛煙家がいるといわれている。中国ではたばこが文化的に親しまれており、特に年配の男性の間では、来客や友人にたばこを勧めることが習慣となっていることもその一因だろう。
そんな中国人観光客をはじめ、さっぽろ雪まつりでは愛煙家への対策がしっかりと行われていた。雪まつりの会場は禁煙だが、会場内には喫煙所が数か所設置されており、大通会場4丁目STV広場に設けられたスノードーム型の喫煙所では、温かい飲み物が無料で提供されるなど、一服できるスペースとして好評を博していた。
なお、札幌市では、2004年12月14日に「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例(ポイ捨て等防止条例)」が施行され、市内全域における“ポイ捨て”の禁止および喫煙制限区域(大通公園や札幌駅周辺など約86.7ヘクタール)における喫煙の禁止といったルールが定められている。
しかし、条例が施行されてからも、大通公園で喫煙者が一角に集まって一服している現状を見て市民から苦情が発生しており、札幌市保健福祉局は2023年12月に大通公園西5に簡易な喫煙所を設置。タバコを吸う人と吸わない人の双方にとって、喫煙所の有無が公園の利用環境の向上につながるかどうかを調査する二つの検証を行なった。
吸う人も吸わない人も好意的に受け止めた喫煙所の設置
まず札幌市保健福祉局が行なったのは、公園内の喫煙者の人数を計測する調査。簡易喫煙所の設置前は2023年11月28日・30日、設置後は同年12月12日・14日と2024年5月8日・9日の各平日2日間で、12:30~13:00と15:00~15:30の1日2回計測が行なわれた。場所は大通公園西5~7丁目の公園内だ(設置後は喫煙所内も計測)。
「喫煙者数調査を行なったいずれの日時においても喫煙所は利用されており、一定の需要があることが確認できました。ただ、利用者の多い12:30~13:00の西5丁目は、喫煙所だけでなく路上喫煙者も見受けられ、12:30~13:00、15:00~15:30のいずれの時間帯も西6、7丁目での路上喫煙者の減少傾向は見られませんでした」(担当者)
この計測では、簡易喫煙所を設置しても路上喫煙者の人数に大幅な変化はなかったようだが、同時期に行なわれた公園利用者・喫煙所利用者へのアンケートでは興味深い結果が出ている。
「2024年5月7日~9日の3日間、休日は5月5日、11日の2日間、10時~16時の時間帯に、大通公園西4~6丁目(公園利用者)および西5丁目喫煙所(喫煙所利用者)で喫煙所の設置に伴う大通公園での過ごしやすさや利用頻度、活動拠点の有無などについてヒアリングを行ないました(5月7日は雨天により1時間で中止)。
回答数は5日間で845件(公園利用者658件、喫煙所利用者187件)で、吸う人・吸わない人を住み分ける取り組みそのものは、ほぼすべての人が良い取り組みであると感じ、公園利用者・喫煙所利用者ともに90%以上の人が、喫煙所設置後は公園が過ごしやすくなったと感じていたことがわかりました。一方で、喫煙所の衝立越しでも臭いや煙を感じている人も見受けられました」(担当者)。
札幌市保健福祉局によると、喫煙制限区域内における新たな分煙施設の設置に関してはまだ未定とのことだが、吸う人・吸わない人を住み分ける取り組みはほぼすべての人が好意的に受け止めているアンケート結果からも、何らかの分煙対策が急がれるところだ。分煙施設を設置し、その存在を周知させれば、路上喫煙者の減少につながる可能性もあるだろう。
分煙の課題に揺れているのは札幌市だけではない。杜の都・仙台市の中心部にある勾当台(こうとうだい)公園も、平日の昼時になると喫煙所に愛煙家が詰めかけ、受動喫煙が問題視されているという。こちらも2021年に分煙の社会実験を試みる予定だったが、コロナ感染拡大防止の観点から実施が見合わせとなった。その後、公園内に設置されていた喫煙所は園内東側の“みどりの道”に移設。
仙台市健康福祉局によると、「移設後の喫煙所には、受動喫煙防止の啓発看板設置や人感センサーによる呼びかけなどの対策を実施しており、今後も継続していく予定」とのことだが、同公園は今年度中にも再整備工事に着手する予定となっている。事前に寄せられた公園利用者の意見には、「喫煙者用のスペースを作ってほしい。副流煙はイヤ」という声も上がっており、同公園における喫煙所設置も課題のひとつといえる。
受動喫煙対策に関して、区市町村間の連携を図る東京都

札幌市や仙台市のような地方の大都市だけではなく、東京都も各区がさまざまな受動喫煙対策を行なっている。例えば全国に先駆けて、2002年に路上喫煙に罰則(過料2000円)を設けた条例を定めた千代田区は、積極的に喫煙所の設置を進めている。2019年に導入された「喫煙トレーラー」は、現在「ちよだプラットフォームスクエア」で稼働中だ。
「トレーラー型の喫煙所は、2年に1度、周辺地区で開催される『神田祭』で神酒所を設置するため、公衆喫煙所を移動する必要があり採用しました。トレーラー型は必要に応じて移動できるのがメリットだと考えています」(担当者)

また、台東区でも1997年に「東京都台東区ポイ捨て行為等の防止に関する条例」を制定。ポイ捨て及び歩きたばこを禁止するとともに、通勤時間帯である午前7時から9時までの2時間を喫煙禁止時間とし、路上や公園などの公共の場所における喫煙を禁止している。そんな同区も公衆喫煙所の整備を推進している。
「区による整備も行っていますが、用地の確保に課題もあり、区の整備に加えて、民間事業者が公衆喫煙所を設置する際の設置経費、維持管理経費を助成するなど、民間企業の協力も得ながら喫煙所の整備を行ない、分煙が図れる環境づくりに取り組んでいます」(台東区 環境清掃部 環境課担当者)
品川区も2003年に「品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例」を施行。区内全域における歩行喫煙、ポイ捨て防止の啓発活動を進めると同時に、区民の良好な生活環境を実現するため、一般開放可能な屋内喫煙所(コンテナ型、トレーラー型など、屋内と同等の設備を有する屋外設置の喫煙所を含む)を設置する建築物の所有者に、喫煙所の設置および維持管理費を助成している。
なお、東京都は区市町村部などの自治体によって喫煙に関する条例が異なり、住民はもちろん、旅行者やビジネスでの訪問者の中には異なるルールに戸惑う人も少なくない。その点を東京都の保健政策部に尋ねたところ、「受動喫煙対策に関して、各自治体の担当者との意見交換を定期的に実施しており、工夫した取り組みを行っている内容を共有し、それをもとに各自治体で検討していただきます」(担当者)との回答が得られた。また東京都では、区市町村が整備する公衆喫煙所の費用の1/2を負担する(上限あり)という支援を行なっていることもあり、都内の喫煙所は増設傾向にあるといえそうだ。
この10年間で現在習慣的に喫煙している人の割合は減少しているが、国内で販売された紙巻たばこの2023年の総本数は878億本。また、新しいたばこのスタイルとして販売が開始された加熱式たばこの同年の総販売本数は585億本と市場の広がりを見せている。この先、望まない受動喫煙や、吸い殻のポイ捨てを防止するために一定の効果があるとされる分煙施設の整備に取り組む自治体が増えていけば、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる社会もそう遠くない未来に実現できるだろう。