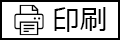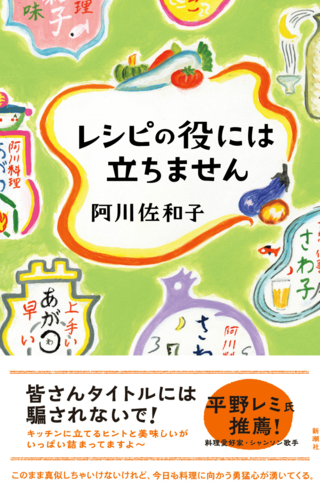おふたりは初対面。阿川さんはタイトルの『この味もまたいつか恋しくなる』をしげしげと眺めて……。
締め切りに苦しみたくない

阿川(以下阿):雰囲気ありますよね、このタイトル。それにしてもよく食べ物の話でこれだけエピソードあるなと思う。しかも、どの話にもちょっとキュンとするストーリーが入ってるから、テレビドラマにしたらいいのに、ミニドラマで。
燃え殻(以下燃):ありがとうございます。エッセイもなんとなく振りがあって、オチがあるほうがいいなと思っていて。だからショートショートみたいにできないかな~と意識しながら書いているところはありますね。
阿:ちょっとキュンとするエピソードなんて……めったにあったもんじゃね~ぞ(笑)。
燃:ははは(笑)。でも僕、週刊連載が得意じゃなくて、結構な数の原稿を担当編集者に渡してから始めています。締め切りが怖いんですよ。今回も一度書き上げた原稿を毎週直しながら続けたんです。「来週締め切り」となると「もうダメだ!」ってなっちゃって……他のことに関しては超適当なんですけど。
阿:私は新聞連載を始めたとき「2週分くらいストックしてください」と言われて、「まぁ、できるだろう」と甘く考えていたら、すぐなくなってしまって。餃子屋の女将になった気持ちです。「だいぶストック作ったわ~」と思っていたのに、いつの間にかお客さんが餃子を全部食べちゃって、ストックがなくなって、追い立てられますけど……学習はしない!(笑)
燃:それは阿川さんが書けるからですよ。
阿:いやいや、切羽詰まると出てくるんです!
燃:切羽詰まると出てこないです、僕。
阿:出てこないとどうなるんですか?
燃:編集さんに怒られるじゃないですか。それで以前「これはホントによくない」と思ったことがあって、ストックするようになったんです。
阿:物書きとしては締め切りに苦しむ同志を増やしたいのに……(笑)。ただ私は食べることが好きなので、だらだら書いてると原稿になるんですよ。でも燃え殻さんのエッセイを読んでると、どうしてこんな人情噺みたいに毎回書けるんだろうと思って。話に余韻があるじゃないですか。このとき付き合ってた女の子どこ行ったのかなとか、いろんな人と一緒に暮らしてるなとか、結構フラレてるな、とか。物書き専業になってから、どれぐらい?
燃:8年ぐらいです。書き始めたのが43歳からで、それまではテレビの美術制作会社に勤めていました。番組で使うパネルとか◯×の札とか、小道具を作ってました。阿川さんが出てる『ビートたけしのTVタックル』の小道具も作ってましたよ。
阿:え~、そうなの!?
燃:その仕事は20年ぐらいやってました。「明日の番組に間に合わないといけない」というので徹夜をしたりとか、「悪魔が使いそうなボールペン」みたいなむちゃなオーダーがきて、ペンに羽根をつけたりして。みんなでわーっとたたえ合うという、文化祭の前みたいな感じの仕事でした。
阿:もしかしたら、会ってたかもしれないのね?
燃:いや、たぶんなかったと思います。来る前に引き揚げるのが僕の仕事で、出演者の方と会っちゃうというのは、作るのが間に合ってないということなので……。
阿:あ、そうか(笑)。
家庭の味とクセの強い家族ネタ

話題はおふたりが育った“家庭の味”の話へ。
燃:僕はもう本当にザ・中流家庭育ちです。父はエレベーター会社の営業で、母は母方の祖父がやっていたスーパーでずっとパートをしていて。
阿:鍵っ子だったのね。本にあったけど、子どものころ、妹さんに夕ごはん作ってあげていたとか。
燃:そうです。だいたい缶詰のパスタソースをかけたものとかラーメンとか。そのときは必死に作ってました。小学校から中学校くらいかな。母が帰ってくるのが夜の9時とかだったんで。
阿:子どもにとっては遅い時間よね。
燃:きょうだいでテレビを見ながら食べて、両親が帰ってくるのを待ってるみたいな。父は遅くまで働いて、終電で帰ってくるような人でした。
阿:お父さんが作ったチャーハンの話があったけど、面白かった。
燃:油が多すぎてベチャベチャで。でも妹と僕はおいしかった、って言って。一生懸命作ってくれたから、なんかすっごい覚えてるんですよね。
阿:ウチの父は決して美食家ではないんですけど、食い意地が張ってるんですよね。車を運転していて、通りかかったところに蕎麦屋があって、「うまいかな?」とか言って寄ろうとするんですよ。でもどうせおいしくないって文句を言うに決まってるからやめようと言うんだけど、結局寄って「まずい!」と怒る。
燃:ははは(笑)。
阿:私が“エンゲル係数”という言葉を覚えたのは小学校3年生のときで、父は着るものはどうでもいいけど、おいしいものを食べたいという人だったんです。でも印税が入ってこないとお金がないから、父から「いいか、おまえら明日からもやしと鶏肉だ」って言われて。いったいウチはお金持ちなのか貧乏なのか、よくわからないんだけど、食べ物がバロメーターになっていたようなところがあったんですよ。
そういう意味では私も食べることに関心が高いのは確かだなと思うし、晩ごはんを食べながら「明日の晩ごはん何食べようか」と旦那に聞いてしまうんです。そうすると「今お腹いっぱいで考えられない」って言われるんだけど……だからやっぱり食い意地が張ってるんでしょうね。
燃:僕は父方のおばあちゃんが沼津で一杯飲み屋をやっていて、子どものころ、その店へ行って、カウンターの下に潜り込んでお客さんとの会話を聞いてるのが好きだったんです。たばこの煙と臭いがすごくて、目が痛くなるくらいだったんですけど。
阿:孫は見ていた、みたいな。
燃:ばあちゃんが三ツ矢サイダーを下に置いてくれて。それを飲みながら、聞いてたんです。常連客の国鉄職員に口説かれたりとかしてて。
阿:おばあちゃんといっても、当時40、50代? そりゃモテるでしょう。
燃:着物に割烹着を着てやってましたね。夕方くらいになると化粧するんですけど、それを横で見てるのが好きで。
阿:だんだんおばあちゃんじゃなくなっていく感じね?
燃:そうなんです。それで熱燗作ったり、沼津なんで干物とか、しらすと大根おろしにちょっとしょうゆをたらしたりする料理なんかを出してました。それがすごくおいしかったんですよ。阿川さんの本にも酒の肴の話がいっぱいありましたよね。
阿:そうそう、私も酒のつまみが好きな子どもだった。でもね私、白いご飯が好きだったんですよ。頂き物のイクラとかこのわたとかを白いご飯にのせると、どれほど幸せな気持ちになるか! 洋菓子とかでもウイスキーボンボンとかサバランが好きだったなぁ。
燃:阿川さんの本に、ご飯の上に紅生姜をのせてちょっとおしょうゆをたらすというのがありましたけど、僕、調味料が大好きなんですよ。
阿:燃え殻さんも本に書いてましたね、味変させるのが好きって。そこは共通しているところでしょうね。私は加工癖があって、レシピを自分なりに変えたり、お店で「お待たせしました」と出てきたチャーハンにすぐに豆板醤とか酢をかけて加工しようとするから家族に怒られて。
燃:最初からですか(笑)。僕はちょっとずつ変えるのが好きですね。調味料を変えたり、少しずつレモン搾ったりとか。
阿:まあお互いね、料理人に失礼同士ということで(笑)。
嫌なことは全部ネタになる!
燃え殻さんは阿川さんのエッセイ『レシピの役には立ちません』に出てきた、不思議な名前の食べ物が気になったそうです。
燃:阿川さんのエッセイに書かれているのって、まねできる料理ばかりですよね。
阿:簡単でしょ?
燃:和田誠さんとか、すごい人たちと食べてるのが面白い。しかも、どれもおいしそうに書いてるんですよね。特殊な食べ物じゃないから、なんとなく味がわかるし、その絵が浮かぶんです。そんな中で気になったのが「ラクダのつま先」と「象の鼻」で。
阿:はいはい。ラクダのつま先はモンゴルの大変な珍味で、豚足みたいなものなんですけど……なんて説明すればいいんだろう、とにかく獣臭がすごくて。象の鼻はちょくちょく行ってた小さな中華料理屋さんで食べたもので、そこはシェフが一人でやっていたところなんだけど、「ほかの料理ができるまで、食べてて」と出されたんです。
燃:名前がすごいですよね。
阿:ビーフジャーキーのもうちょっと癖のあるような味で、赤黒い見た目なんです。でも最近になって、ある方に聞いたら、九州でとれる貝を干したものを、地元では象の鼻というんですってね。
燃:へ~。
阿:九州出身だったのかなぁ。面白いシェフだったけどね、その人お酒飲みだったから、死んじゃった。
燃:ああ、悲しい話……。
阿:そうか、燃え殻さんみたいな話にするには、こういうふうに書いてみればいいのか。
燃:ええ、僕は料理そのものというより、食べ物にひもづいた思い出として書いていますね。
阿:思い出といえば、不思議な女性関係が多いですよね?
燃:かもしれないですね、沼津のおばあちゃんの影響なのかなぁ。あとはスーパーをやっていた母方のおばあちゃんも江戸前って感じのすごい人で。僕ね、小学校のときにいじめられていたんですけど、それを聞いたおばあちゃんが「おまえ、それ全部覚えとけ。大人になったら好きな女に今日いじめられたことを情感たっぷりに話せ。モテるぞ」って言ったんですよ。
阿:おばあちゃん、先見の明がありますね~。
燃:そうすると、今ひどい目に遭ってるけど、なんか未来に希望が持てたんですよね。
阿:なるほど。私もね、自分には才能も何もないから、父とは違う優しい人と結婚しようと思ってお見合いをたくさんしたんだけど、うまくいかなくて鬱々としていたときに、知り合いのおばさまに「父がひどい」という話をしたら、「いいじゃないの、後々いっぱい思い出になるから。ウチの父なんてホントに優しい人だったから、何も覚えてないのよ」とおっしゃって。そのときは「冗談じゃない!」と思ったんだけど、今になってみるとおっしゃったとおりだなと思って。しかもその思い出を書いて、原稿料稼いでるからね(笑)。
だから嫌なことは全部ネタになる、後々人を笑わせるネタになる、ってみんなに言ってるの。いい目に合った話なんて誰も喜びはしない、ひどい目に遭った話には食いついてくるから、みんな!
燃:そうですよね。それでそれで?って聞きたくなりますよね。ひどい目に遭った話って、いつか恋しくなるものなんですかね(笑)。
『レシピの役には立ちません』(新潮社)
冷蔵庫の残り物をどうするかと日々台所で奮闘し、出てきた料理や気になるレシピを見つけては自己流アレンジを加える“加工癖”などを開陳する、新潮社の情報誌『波』の連載から生まれた3冊目の食エッセイ。カラスミのみりん漬け、紅生姜など、まねしたくなる阿川流メニューがめじろ押し!
『この味もまたいつか恋しくなる』(主婦と生活社)
『週刊女性』に連載された『シーフードドリアを食べ終わるころには』に加筆修正と書き下ろしを加えて書籍化。朝煎りコーヒー、生姜焼き定食、チャーハン、金目鯛の煮付けなど、さまざまなメニューにまつわる味の記憶と、その食べ物から思い出されたちょっぴり切ない物語を展開する。
1973年、神奈川県生まれ。テレビ番組の小道具制作会社勤務を経て、'17年にネット上で連載した『ボクたちはみんな大人になれなかった』で小説家デビュー。著書に小説『これはただの夏』『湯布院奇行』、エッセイ『それでも日々はつづくから』『夢に迷ってタクシーを呼んだ』『明けないで夜』など。作品が次々と映像化、舞台化されるなど、今注目の作家。
1953年、東京都生まれ。'81年、テレビのリポーターを務めたことをきっかけに報道番組キャスターを担当、以後も番組に出演。エッセイスト、小説家として著書多数、『聞く力 心をひらく35のヒント』は180万部を超すベストセラーに。また女優として映画やドラマに出演するなど、幅広い分野で活躍中。父は小説家の阿川弘之。
<取材・文/成田 全>