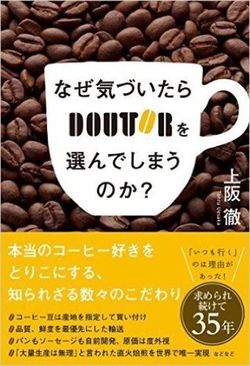この20年で、競争環境が熾烈になった市場の1つが喫茶店やカフェなどコーヒーの提供を主体とするお店ではないだろうか。ファミリーレストランをはじめ、コーヒーを飲める店は大きく拡大。ファストフード店も次々に格安コーヒーを展開している。スターバックスコーヒーをはじめ海外から新しい文化もやってきた。100円台で飲めるコンビニコーヒーのヒット、サードウェーブと呼ばれるハイクオリティコーヒーのブーム――。
堅実な人気を保ち続けるドトールコーヒーショップ
ところが、これだけの荒波に揉まれながらも堅実な人気を保ち続ける老舗コーヒーチェーンがある。ドトールコーヒーショップだ。1990年代後半に外資系コーヒーチェーンが続々上陸した後も、コンビニコーヒーが猛威をふるっても、今なおドトールはにぎわっている。朝早くから夜遅くまでひっきりなしに来客があるお店が多い。
拙著『なぜ気づいたらドトールを選んでしまうのか?』にも詳しく書いたが、ドトールにお客が集まるのには、理由がある。
ドトールコーヒーショップの誕生は、1980年。人々の度肝を抜いたのは、その価格設定だった。コーヒー1杯、150円(当時)。これは、普通の喫茶店で出されているコーヒー価格の半分以下だった。
背景にあったのが、創業者である鳥羽博道氏による強烈な理念だ。「おいしいコーヒーを、消費者の負担のない価格で提供したい」。単に安いだけのコーヒーを提供しようとしたのではない。どうすれば本物のコーヒーを、安い価格で提供できるのかを考えたのだ。お店はすぐに長い行列ができるようになった。フランチャイズの仕組みを取り入れ、一気に店舗展開が図られていった。
本物を手頃な価格で、という思いは今もまったく変わっていない。実は店頭価格だけで想像すると、ドトールコーヒーを見誤りかねない。
コーヒーの味は「コーヒー豆」や「焙煎」などに左右される。ドトールの場合、コーヒー豆はブラジル、コロンビア、エチオピアなど世界20数カ国から輸入している。だが、買い付けを現地の会社や商社にただ任せることはしない。自分たちの目と舌で豆を確かめ、時には現地に足を運び、直接、品定めをする。
ドトールのクオリティにふさわしい豆を生産するエリアを指定したり、さらにピンポイントに農場や品種、コーヒーの木を指定して輸入したりすることもある。こんなことをしてコーヒー豆を買い付けているケースは、世界にもそうそうないという。
輸送にもこだわる。赤道直下を船が通るため、船底指定で運ぶ。これをやらないと豆が汗をかいてブヨブヨになり、ひどい状態になりかねないらしい。コーヒーは、デリケートな素材なのだ。だから、日本に届いてからも、つねに一定の温度を保つ定温倉庫に入れる。コーヒー豆に定温倉庫、というのは、かつては仰天の発想だったという。
何杯飲んでも胃がおかしくならない鮮度
そして、保管されているコーヒー豆は、その日に使う分だけが毎日、焙煎工場に運ばれる。コーヒーの味を左右する要素の1つである「焙煎」後の豆の鮮度のコントロールにも、工夫が凝らされている。基本的に、全国のお店からオーダーをもらった分だけ、工場でコーヒー豆を焙煎する。お店は基本的に、古い豆の在庫を持たない。
たとえばお店が月曜日に発注すると、工場が火曜日にデータをまとめ、朝から焙煎して夕方には出荷される。しかし、店舗に直送はされない。1度、ワンクッションが置かれるのには、理由がある。焙煎したてのコーヒー豆は、ガスが出て抽出が安定しないから。最も飲み頃になるタイミングで届くよう、調整される。
店舗から毎日のオーダー生産。おいしいタイミングでの配送。同様の取り組みをやっている会社は、ほぼ皆無だろうとみられている。それこそ多めに焙煎しておけば、在庫切れも起こさずに済むように思えるが、それはしない。焙煎した豆は、どんどん酸化していってしまうからだ。
コーヒーには15%前後の油脂分があり、空気に触れると酸化現象が起こる。これが、コーヒーの味を落とす。コーヒーを飲むと胃が痛くなる、というのは、酸化してしまったコーヒーだったからではないか、と取材で聞いた。毎日、何リットルも飲んでいるドトールの工場の焙煎士が、胃をおかしくすることなど、まったくないという。
これほどまでにドトールが強くこだわる鮮度だが、コーヒーチェーンの中には、海外で焙煎されたコーヒー豆を船で日本に運んでくるところもあるらしい。1カ月前後の日数をかけて、である。本当においしいコーヒーを飲みたいなら、お店で聞いてみたほうがいいかもしれない。「このコーヒー豆は、いつ焙煎され、どうやって配送されているのか」と。
つまり、ドトールが提供しているのはこだわりぬいたコーヒーであって、単に安いだけのコーヒーではない。1度、本物の味を知ったお客はそうそう後戻りできない。飲食業界や食通の人たちの間でドトールのコーヒーを高く評価する人は多い。
スプーンがソーサーに滑り落ちないからイライラしない
ドトールコーヒーのこだわりは、豆だけにとどまらない。たとえば、コーヒーカップ。オリジナルのカップ&ソーサーは形状、厚さ、取っ手なども考え抜かれている。
唇が触れるカップの縁は、飲み口が滑らかになるよう、スムーズな口離れによって、液だれを起こしにくい曲線に吟味されている。
取っ手の持ちやすさも、右手の人差し指を入れ、親指で上部を、中指で下部をはさみこむようにして持ち上げる前提で、最も指が当てやすい形状になっている。もちろん、熱いカップに指が触れずに済むよう計算されている。サイズによって取っ手の形状も変わる。また、釉薬(うわぐすり)も考えて選び、洗浄したときに口紅が落ちやすいよう、調整したという。
コーヒーを飲むとき、カップを持ち上げると、スプーンがソーサーにするりとすべり落ちてしまうことがある。カップをソーサーに戻そうとするとき邪魔になり、これが意外にイライラするのだが、ドトールコーヒーショップの食器では、絶対にこうはならない。スプーンがすべり落ちないよう設計されているのだ。本を出した後、お店の中でこれを確かめている人が何人もいたのを見た。もちろん、私もやってみたのではあるが。
「言われてみれば、確かに心地がいい」
持ち帰り用の紙コップにもこだわりがある。もともとメーカーからは、ファストフードなどで使われるプラスティック素材のモコモコした形状のカップを提案されたが、「持った感じが気持ち悪い」という意見が社内で出た。
そこでエンボスタイプと呼ばれるものをメーカーと共同で開発した。紙の表面に小さな凸凹がついて熱さをカバーする。最近では、セブン-イレブンのコーヒーも、このカップが使われている。実は業界では「ドトールタイプ」とこのカップは呼ばれている。
多くの人はこだわりに気づいていないかもしれない。しかし、それでいいのだという。何も意識されない、というのが、ドトールにとってはベストなのだ。
上阪 徹(うえさか とおる)○ブックライター。1966年、兵庫県生まれ。85年、兵庫県立豊岡高校卒。89年、早稲田大学商学部卒。アパレルメーカーのワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスに。経営、金融、ベンチャー、就職などをテーマに、雑誌や書籍などで幅広く執筆やインタビューを手がける。主な媒体に、『GOETHE』(幻冬舎)、『AERA』(朝日新聞出版)、『週刊現代』(講談社)、『就職ジャーナル』(リクルート)、『Tech総研』(リクルート)など。著書に『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか?』(あさ出版)、『僕がグーグルで成長できた理由』(日本経済新聞出版)、『職業、ブックライター。』(講談社)、『成功者3000人の言葉』(飛鳥新社)、『リブセンス』(日経BP)など。他の著者の本を取材して書き上げるブックライター作品も60冊以上に。