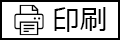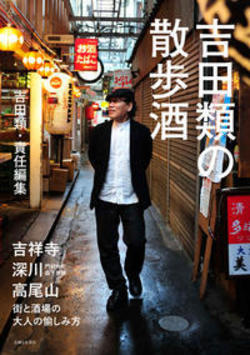“酒場放浪記”が映画に? 映画初出演で初主演!
いつものハンチング帽、黒ずくめの服に身を包み、酒場詩人・吉田類が味のある大衆酒場の、その店主の、そのおすすめ料理の魅力を語る。もちろん、酒を片手に─。
お酒が大好きな人も、そうじゃない人も、性別を超え、幅広い年齢のファンが放送を楽しみにしている『吉田類の酒場放浪記』(BS-TBSにて、毎週月曜、夜9時~)。
この番組のナビゲーターであり、今日の大衆酒場ブームを巻き起こした張本人である吉田のスクリーンデビュー作が『吉田類の「今宵、ほろ酔い酒場で」』(6月10日公開)。
「映画初出演で、初主演ですよ。役者でもなんでもないのにね(笑)」
そう語るが、'15年末に放送されたTBS系の大ヒットドラマ『下町ロケット』の最終回で、小泉孝太郎が演じた椎名の父親役で演技を初経験している。
「あれはね、プロデューサーから“ドラマに出てみませんか? ちょっと遊んでみてくださいよ”って言われて出演したんです。僕は、遊ぶときは、一生懸命なんです。子どものころから遊び好きで、母親が困っちゃったくらいにね。高熱が出ていようが、飛び出していって、帰ってこなかった。
母には“鉄砲玉みたいなもんや”って、よく言われました(笑)。そのかわり、夢中になるタイプなので、好きなことはある程度、モノにできちゃう。ずっと“好きなこと以外やらない”ということにはこだわって、自由に、気ままにやっています」
居酒屋と大衆酒場の違い
高知県の山あいの町に生まれた吉田少年は、小学生のころから大好きで「いちばん凝っていた」という絵で食べていきたいと、主に、ヨーロッパで勉強を続け、10年ほどパリを拠点に活動。30代半ばからは、パリと日本を往復するように。そのときに出会ったのが“大衆酒場”だった。
ここで、居酒屋と大衆酒場の違いを─。コの字型のカウンターで、店内のお客さん同士の交流を前提に作られているのが大衆酒場だそう。全国各地に名物といわれる酒場があるようだが、オリジナルは、東京の下町。
吉田に初めて“大衆酒場”に触れたときのことを聞くと、
「日本に戻って、ひとりでゴハンを食べようと思っても、食べる場所がない。いまもそうですが、当時から食事は外食。努力したけれど、“家庭”が向いていなかったんです(笑)。で、探していたら、門前仲町のある立ち飲み屋を見つけた。

すごくおいしいマグロを仕入れるっていうので有名な店で、その日のうちに店主と友達になってね。彼とは、登山仲間でもあるんだけど。そこで会った人たちと自然に飲み歩きをするようになったんです。
“酒場”は、自分にとって、すごく面白い世界だった。例えば、それまで、モツも食べたことがなかったわけですよ。これが……と、思って食べてみたらおいしいんです。いまは、とくにシロ(豚の大腸)なんて、大好きですもん。食べものだけでなく、酒場そのものも魅力的でしたね。人間って、こんなにいろいろなタイプがいるんだと知れるわけです」
映画にも出てくる土佐の幼少期の体験
酒場との出会いが、のちに“酒場放浪記”となっていった。この放浪記からイメージを膨らませて製作され、3軒の居酒屋で繰り広げられる人間物語を覗くことのできる映画のストーリーテラーであり、ひとつの物語では、主役である巨額詐欺事件の犯人として追われる投資会社の社長・森本を吉田が演じている。
「僕はね、作り込むなんてできないタイプ。監督は、それでよしとしてくれて“そのまま、ふつうに動いてください”って言われたので、ふつうにやりました(笑)」
気負いがなかったように答える吉田に、今作のためにダイエットをしたと聞いたことを伝えると、
「失敗したの(笑)。思ったほど、減量できなかったんです。やりたかったですよ。だって、逃亡者の役ですから。それなのに、毎晩、おいしい酒と肴を食べていたら無理ですよね(笑)」
公開を待ちわびるファンのために、思った役作りができなかったという。
追い詰められた社長・森本が、故郷の土佐の酒を口にしながら、幼いころを思い出す場面が映画の中に出てくる。
両手ですくった水をそのまま飲み干せるほどの清流で遊び、友と一緒に登った山の頂から遠くに光り輝く海を見つける。それは、まさに吉田が幼少期に体験したことだったそう。
「再婚して、山むこうの村に越していった従弟を驚かせようと思って山に登ったわけです。そうしたら、ずーっと先に光るものがあって“あれ、なんや?”と言ったら、土佐湾だった。初めて見た海でした。そこから、憧れをもって西洋の話をいっぱい聞くようになるんです」
そのころ、吉田の人生に大きな影響を与えた、もうひとつの経験をしている。
昼間の恐怖が“夜行性”の原点に
「火球が落ちてきたんです。流れ星の大きさは、いつも見ているから知っているわけですよ。それよりもずっと大きいもので、当時は“隕石”なんて知らなかった。不思議に思いながら火球が飛んでいくのを目で追っていたら、金縛りになったんです。
それから、昼間が怖くてたまらなくなった。日中は、身体が震えてね。そのくらい、ショックだったんだと思います。いままでガキ大将で走り回っていたのに、夜しか動けなくなった。日が暮れると母親に気づかれないよう、そっと家を出て、お月さまの輝きに吸い込まれそうになりながら歩くんです。そのときは、怖さなんてなくて、むしろ安心するんです」
月明かりの中、山道を歩きながら隕石を見たときのことを思い出した。故郷を追放され、地球ではない惑星から来た宇宙人が、人間の身体の中に入り込み、人である苦しみを味わうことで自らの罪を贖う、そんな想像を膨らませながら。
「モノを書いたり、詩をつくったりするようになったのは、この経験が原点。もうひとつ、夜、山道を歩いていたことで、夜目がきくようになった」
隕石を見たのは、夏休みに入ったばかりだったこともあり、休みが終わるころには“昼間の恐怖”を克服できていたそう。
「夜目がきくようになって、夜行性になりました。だから、街でも夜行性(笑)。これまで、素晴らしい出会いや経験ができているのも、この体験があるからかな。小さいころに、火球を見ないといかんな(笑)」
幼少期から絵が好きだったように、映画も「ものすごく好きで、見た作品は全部おぼえている」と語る。実は、隕石を見たのも、映画の帰り道だった。いまでも、テレビで映画を映しながら原稿を書いている。“酒場”と同じように愛する映画、それも自身が出演していて、見た人は必ずその足で“酒場”に行きたくなる作品。どんな期待をもって劇場に足を運んでほしいか聞くと、
「女性でしたら、この映画を通して“酒場”の一端を知っていただくのもいいと思う。いろいろなことを勉強できると思いますし、知識を増やすためにも“酒場”は、オススメです。
ただ、お酒は幸せになるためのもの。“お神酒”というように神様から与えられたもので、その思いで造られているんです。神聖なものであるということをわかってほしい。
僕ら酒飲みも、お酒をけがさないような飲み方をしようと気をつけている。だから、スマートに格好よく、とはいっても酔っぱらって、そこからはずれることもあるかもしれないけれど(笑)。でも、そんなことを心がけながら、“酒場”の魅力を味わってください」
「最期」の質問です

人生、最期に飲みたいお酒は?
「日本酒『金凰司牡丹(きんおうつかさぼたん)』。蔵元と生まれ育った場所の水系が一緒なんです」
死ぬ前に食べたいものは?
「うつぼのしゃぶしゃぶ。白身で、フグに似ています。てっさ(フグ刺し)より厚めに切って、ポン酢で食べる。皮を長めにしゃぶしゃぶするとコラーゲンがとろっとろになっておいしいんですよ。いまは、高知でしか食べられません」