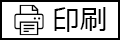深刻な高齢化が進む日本。その裏で問題視されているのが高齢単身者の増加だ。内閣府の令和6年版高齢社会白書によると、2025年における65歳以上の単独世帯は約800万を超え、今後も増加の一途をたどる。
必ず住み替えが必要になる
「単身シニアは孤立しやすく、1週間誰とも話さないなんてこともザラ。体調悪化の発見遅れや、孤独死などの問題も懸念されます。そこで注目されているのがシニアシェアハウス。
入居条件は施設によって異なりますが、自立した生活を送れる介護不要のアクティブシニアであることが絶対条件。建物内に共用スペースがあり、各個室でプライバシーを保ちつつ、入居者同士で日常的に交流を楽しめるのがウリです」
と話すのは、高齢者住宅に詳しい満田将太さん。住人同士で体調の見守りもでき、物件によっては管理人がいるところも。独りではないという、安心感が心強い。
「シニア向けの集合住宅には、費用の高いサービス付き高齢者向け住宅や、安価ですが施設色の強いケアハウスもあります。しかし、高い費用は払えない、自由に過ごしたいという人には適しません。
一方シニアシェアハウスは、自由度は高めで管理費は一般住宅より少々高くつくものの、家賃も比較的安く抑えられているのが魅力」(満田さん、以下同)
また、住居の形態に法的な縛りがないため、空き家を利用した物件や一棟まるごとのマンションなどさまざま。
「一番の特徴は、終の棲家(すみか)にできないこと。自立して生活できることが入居の条件なので、介護が必要になると施設などへの住み替えが必要になります。
介護保険でヘルパーさんの手を借りて住み続けるケースもありますが、同居人から“プライバシーが守られない”といった不満の声があがるなど、現実的ではありません」
高齢になるほど新しい環境に移るのは大変。そのため、将来的に介護が必要になった時に、移れる施設を事前に考えておく必要がある。
「よくあるのが、高齢になってからシェアハウスに入居し、住み慣れたころに体調を崩して退去になるケース。元気であれば80代からでも住めますが、できれば70代前半の早めの入居が理想」

共同生活が苦手な人はNG
共同生活に適性がないと、トラブルに発展しやすい。実際にシェアハウス生活を送る足立一郎さん(80代前半の男性・仮名)は、同居人だった老夫婦に文句を言われたそう。
「その夫婦の奥さんのほうが、軽い認知症を患っていたのですが、ご主人が“うちの妻がこのシェアハウスで仲間外れにされている”と周囲に言い出して。私たちも奥さんに話しかけてはみたものの、うまく会話ができなかったので、様子を見ていました。疎外していたわけではないのですが……。
シェアハウスに入れば周りに気を使ってもらえて、サポートまでしてもらえる。将来的には介護まで手伝ってくれるのではないか、という思惑がこちらの夫婦にはあったようですが、私たちも他人の面倒を押しつけられても困りますし。結局、退所していきました」
共同生活のいざこざは人間関係だけではない。都内に住む渡辺茂さん(70代後半の男性・仮名)の同居人だった男性は、金銭面で不満をあらわにしていたという。
「自分は毎日お茶を飲むわけではないのに、共用スペースでのお茶代の徴収には納得いかない、と。共同生活はゆずり合いや妥協の気持ちがないと難しい。
年金で暮らしている人が多いのでお金に細かくなるのもわかりますが、入居時に決められているルールがあるのですから守れないなら、最初から入ってこないでほしい」
満田さんも「管理費の使い道に文句を言う人や、金銭面の問題が退去につながるケースは珍しくない。家族で同居していたってお金の問題はシビアなのに、これが赤の他人ともなると、日々神経をすり減らしたり大問題に発展することもあります」と話す。
では、“向いている人”はどういう人なのだろう。
「これからどういう人生を送りたいのか、優先順位が決まっている人です。家賃が多少高くても利便性の高い都市部に住みたいのか、のんびり郊外なのか。郊外の場合は車がないと出かけられないことが多いので、そのあたりも物件選びにおいて必須になってきます」
あとは協調性に尽きるという。
「どんな人が同居しているのかは、見学しているときにチェックを。午後のお茶の時間を狙って様子を見に行くのもいいでしょう」
“元気だが独り暮らしは避けたいという高齢者”向けの住宅ニーズはますます高まるという。
「これまで賃貸物件でシニア世代は敬遠されてきましたが、少子高齢化でそうも言っていられません。最近ではシニアに特化してバリアフリー化された分譲シニアマンションなど、新たな形態のシニア住宅も生まれています。
納得のいく老後を実現するためにも、元気なうちに情報収集を始めて、自分に合った選択肢を用意したいものです」

満田さんに聞いたシニアシェアハウスのこぼれ話
九死に一生を得た井上智子さん(70代女性・仮名)
「今ある命はシェアハウスのおかげ」
「日課であるラジオ体操に来なかった井上さん。管理人がおかしいと思い部屋に行ったところ、倒れていて。その後は本人も回復したので安心しましたが、やはり誰かと暮らすのは命のセーフティーネットなのだと思います」
SNSで事実無根の悪評
「よりよい暮らしを実現するためにも、見学は怠らないこと」
「シェアハウスの口コミで、SNSなどに事実無根の悪評を書かれたケースがあります。情報だけを鵜呑みにするのではなく、一度、住人に生の声を聞くなど見学を怠らないこと。逆に“口コミで評価が良いから”という理由で安易に選ぶのも後悔のモト」

教えてくれた人……満田将太さん●2012年、株式会社えんカウントを設立。高齢者施設紹介業に専任で従事。2017年からは一般社団法人高齢者住まいアドバイザー協会を立ち上げ、資格検定として介護保険や高齢者住まいの知識の普及に努めている。現在資格取得者は、全国で1000人以上で、千葉県山武市にある高齢者シェアハウスむすびの家の立ち上げ支援を行い、運営に携わる。
取材・文/井上真規子