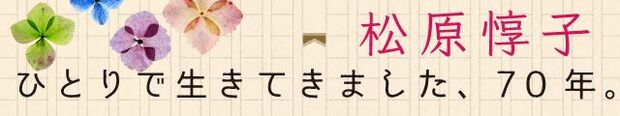1986年『女が家を買うとき』(文藝春秋)での作家デビューから、72歳に至る現在まで、一貫して「ひとりの生き方」を書き続けてきた松原惇子さんが、これから来る“老後ひとりぼっち時代”の生き方を問う不定期連載です。

第16回
フィンランド訪問で感じた“本当の幸せ”とは
今年の8月末に、フィンランド福祉施設等視察団に参加し、首都・ヘルシンキに行ってきた。このたび、ツアーに参加を決めたのは、国連が発表する2019年の世界幸福度ランキングで、フィンランドが2年連続で1位となったからだ(日本は58位)。北欧諸国は福祉国家であるのは誰もが知るところだが、その中でもフィンランドが選ばれたのはなぜなのか。国民はどんな生活を送っているのか。また、本当に幸せなのか。この目で確かめたくなった。
まず、ヘルシンキの街を歩いていて気づいたことは、服装がとても質素なことだ。男女ともに黒のパンツが基本。スカートをはいている女性がいるとしたら、たいていは観光客だ。売っているものの種類も少なく、働いている人もそんなに愛想がいいわけではない。ここは社会主義の国? それが、わたしの第一印象だった。
なんだか、ちっとも幸せそうではない。日本のほうが活気に満ちている。しかし、視察を進めるうちに、わたしの見方は変わった。
わたしたち日本人が「こうあったら素晴らしいのに」と思うことが、フィンランドにはすべてあったからだ。わたしが感銘を受けたのは、子どもに平等な教育を無償で与えている点だ。人は平等に生まれてこない。貧しい家に生まれたら、はじめから差がついてしまうというのは、人の平等に反する。
つまり、教育のスタート地点で、お金がなくて大学に行けないという不平等がないようにしているのだ。小学校から大学まで学費は無料(ちなみに保育園に通わせる場合はお金が必要だが、待機児童問題はない)。日本のように医師の子どもは医師になるのではなく、貧しい家に生まれても能力のある子どもは、医師にも宇宙飛行士にもなれる。しかも、フィンランドの教育が目指すものは、点数がとれる子どもを育てることではなく、自分自身の考えを持ち、批判的思考を持つ人間を育てることなのだ。
だから、国民が国家権力に目を光らせる、社会をよくしようとするのは、当然のことなのだ。母国の悪口は言いたくないが、自分の意見を持たず、ことなかれ主義の日本人とは真逆なのがフィンランド人なのだ。