夜の遊興は「バカだった」
その夫は今年もやはり、追悼式に参加しないのだろうか。
事件現場から徒歩圏内にある住宅街の一角に、夫は親族と住んでいた。そこは母屋と離れに分かれ、夫は後者でひとり暮らし。帰宅時間帯の夜に訪問し、ドアを開けて呼びかけると、奥の部屋から足音がした。
真っ暗な玄関に現れた夫は、髪が短く、ぱっちり目の濃い顔立ち。こちらの身分を明かし、事件から17年目の気持ちを尋ねると、落ち着き払った様子でこう言った。
「話すことはないです。今まであなたたちメディアが書いた記事を見れば、何も話したくはないね」
聞けば、当時の報道により、極度のメディア不信に陥っていた。このため何を尋ねても、
「お話ししません」
の一点張り。取材の主旨を伝え続けると、夫はぽつりぽつりと話しだし、詐欺事件と愛人関係についてポロッと漏らした。
「パソコンの件は、私はきちんと罪を償いました。まあ浮気も罪といえば罪かもしれないね。会社でお金を水増し請求し、キックバックをもらった。夜の世界で遊興し、(女性に)お金をあげていました。そういう内容の記事を読んだら、その延長線上に(放火殺人事件につながる)何かがあったと思うよね? だからもう何を言っても無駄だね」
夫の目は泳いでいない。あくまで冷静だ。夜の街に入り浸った理由については、こう説明した。
「ただ、遊びが面白かった。それだけ。ちやほやされるし。今思い返せばバカだなと思う。とことん思うね。そんときは、溺れとったね。(相手は)1人だけじゃなかったから」
その気持ちをさらに詳しく聞こうとすると、夫は苛立ったような声になった。
「私は何を言われようが、浮気の過去に触れられること自体が、『すべてあなたが悪い。だから事件が起きた。あなたわかっていますか?』というふうにしか聞こえない」
そのうえで放火殺人事件との関係性については「あるわけがない」と否定して不敵な笑みを浮かべ、皮肉交じりにこう付け加えた。
「あるわけがないとは言えないなあ。白いものも黒にできるでしょ? 権力とペンは」
犯人の早期逮捕を望むかとの問いには、小さく「うん」と頷いた。
「それはもう警察に任せるしかない。もし犯人が逮捕されてひと区切りついたら、たぶん(メディアに騒がれた)過去のことなんてどうでもよくなるんじゃないか。もう年だし、穏やかに過ごしたいね」
1時間ほどの立ち話を終え、その場を辞した。別れ際、夫は平然とこう言い放った。
「これが取材ということであれば、この場で話したことはすべて嘘です」
夫は今年の追悼式も「行きません」と言い切った。はたして命日には何を思うのだろうか。
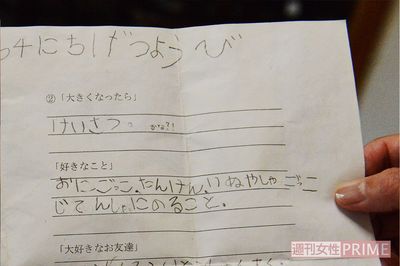
※情報提供はこちらまで 0561-39-0110(愛知警察署特別捜査本部)
取材・文/水谷竹秀
ノンフィクションライター。1975年三重県生まれ。上智大学外国語学部卒業。カメラマンや新聞記者を経てフリーに。2011年『日本を捨てた男たち フィリピンに生きる「困窮邦人」』で第9回開高健ノンフィクション賞受賞。近著に『だから、居場所が欲しかった。 バンコク、コールセンターで働く日本人』(集英社文庫)など













