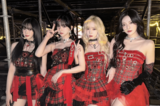県外避難で生じた罪悪感
画面越しに、わかなさん(26)は静かに呼びかけた。
「つらくても、生きていてください」
2021年12月、ある大学で開かれた、震災を経験した人から学ぶオンライン授業での最後の言葉だ。コロナ禍で学生たちは生きづらさを感じているかもしれない、とわかなさんは心配したのだろう。
モニターの向こうにいる180人の学生に向けて、その言葉が発せられるまで、わかなさんの11年の道のりは苦しみの連続だった。絞り出された言葉には、重みとやさしさがあった。
福島県伊達市で被災したわかなさんは、当時15歳。卒業式の日だった。
震度6弱の揺れに、「この世の終わりだ」と思った。空が真っ暗になって雪が降り、雷まで鳴ってカラスが飛び回る。天変地異のようだったとわかなさんは思い返している。
ラジオで原発が爆発したことを聞いたとき、ピンとこなかった。母が「このままだとチェルノブイリみたいになる」「逃げなきゃ」と言い、一方で父は「国が大丈夫だと言っているんだから大丈夫だろう」と言っていた。しかし、父が折れ、3月15日には母の実家がある山形県に避難をした。
3月16日の高校の合格発表に、山形県に避難をしていたわかなさんは行けなかった。この日の福島市の記録を見ると、一時は毎時20マイクロシーベルト(事故前の666倍)。
わかなさんは、のちに避難したことに負い目を感じるようになる。友人たちは高い放射線量の中、知らずに被ばくしてしまった。「私だけ逃げた」という思いにとらわれてしまう。
父は仕事のために福島に残り、母と弟の3人で、山形県に1か月ほど避難していた。わかなさんの高校入学と、弟の学校が始まる4月に伊達市に戻ったが、それからも家族会議は続いた。両親が喧嘩になることもあり「どっちについていくの」と母に言われた。最後の話し合いの日の、母の言葉が忘れられない。
「あなたはどうしたいの」
「私はせっかく今の高校に合格したし、行きたいよ。でも……高校3年間と私のこれからの人生を天秤にかけたら、どちらが大切か明白でしょ」
わかなさんはそう答えた。このころ、さまざまな場面で「大人もただの人間なんだ。何が正しいか大人も判断できない」と気づき、愕然としていた。
合格した高校の入学式の日には、家族会議で山形県への避難が決まっていた。
「家族で自主避難をすることになったので、編入手続きをしてください」と先生に伝えると「これを読め。安全安心と書いてある」と原発安全神話の本を差し出された。
また別の先生には「おまえが行く(避難する)と風評被害が広まる」と言われてしまう。わかなさんは唖然とした。
これまで筆者は、母子避難の母親を取材する中で「歩く風評被害と言われた」「気にしすぎなんだよと笑われた」「避難するなら離婚だと言われた」など、つらい経験をたくさん聞いた。しかしまさか子どもに向かってそんな言葉を投げかけた教師がいたとは、驚く。
一方、別の先生は、教壇で泣きだし「3月16日の合格発表で、みんなを被ばくさせてごめんなさい」と話したという。
わかなさんは、約10年間のそういった経験を克明に綴った『わかな十五歳 中学生の瞳に映った3・11』(ミツイパブリッシング)という本を出している。
「多感な時期の子どもたちは、自分たちの意見も感情も、誰にも話すことさえできず、ただ沈黙させられるという状況でした。私たちが怖いとか、嫌だとか言えば周りの大人を困らせてしまうだろうと“忖度”して、感情を押し込めて生活していました。そして、いつしか感情を閉ざすことに慣れていき、感覚が麻痺していくようでした」
そうした内面が率直に綴られている。たくさんの大人に読んでほしい1冊だ。当時、そんなふうに過ごしていた子どもたちに対して、誰もケアに回ることができなかった。