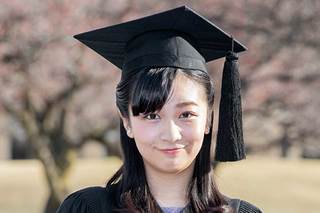吉永小百合が、ひばり児童合唱団に稽古に来たのは、1956年。彼女が小学6年生のときだったという。
「ラジオドラマの『赤胴鈴之助』に出ていたころ、ディレクターに紹介されて来られたのが最初です。その後、伯母が松竹に小百合さんを紹介したことから、映画女優として活躍されることになりました。それ以来、小百合さんはずっと、伯母を恩人だと言って慕ってくださって、現在まで何度も稽古場に足を運んでくださっているんですよ」
昨年の和子さんの葬儀のとき、彼女は映画『ふしぎな岬の物語』の撮影中にもかかわらず、真っ先に駆けつけて、涙ながらに無言で皆川氏の手を握ってくれたのだという。
戦中戦後を駆け抜けてきたひばりの歴史は、そのまま、児童合唱団に生涯をかけてきた、和子さん自身の歴史そのものでもある。
先日、和子さんの一周忌を終えたばかりの皆川氏に、その心境を聞いてみると。
「1年間があっという間でしたね。本人が存在しなくなっただけで、まだ実感が湧かないんですよ。私の気持ちの整理がついていないので、納骨もしていないんです。お墓は近いんですけど、なんだか家から離れてしまう気がして決断できないんですよね」
それほど、彼にとっても和子さんの存在は大きいものだった。検査などで病院に行くときはずっと付き添っていた皆川氏だが、最後に下咽頭がんで入院し、亡くなってしまったときは合唱団の定例の合宿に引率していて、その死に立ち会うことができなかった。
「伯母の最期を看取れなかったために、まだ亡くなった実感を持てないんじゃないでしょうか……」
現在は、和子さんが主宰していたころとは子どもたちの事情も大きく変わってきた。
「塾やお稽古ごとが詰まっていたり、受験のために小学校高学年で休団してしまったり。今は、伯母と同じやり方でというのは時代的にも難しいと思うので、私は私なりのやり方で、子どもたちの学校や活動を優先しつつも、面白いことができたらいいなと思っています。5年後には、再び東京五輪がありますよね。前回の五輪ではひばりも歌わせていただいてるので、半世紀を経てもう1度、子どもたちをオリンピックの舞台に立たせてあげたいですね」