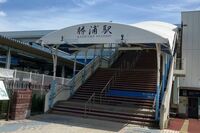遺児と同じ立場だからこそ、できるサポートがある。『あしなが育英会』の取り組みだ。阪神・淡路大震災や東日本大震災では、遺児や孤児が多く出たため、支援のための施設『レインボーハウス』を作った。
仙台レインボーハウス所長の西田正弘さん(58)は、父親を交通事故で亡くした経験がある。遺児は経済的に進学が難しく奨学金が必要だと思い、阪神・淡路大震災の被災地へ遺児仲間とともに出向いた。
「死者が増えたため、遺された子どもたちがいると思い、探し歩いたのです。それまで接していた子どもたちは、自分と同じ交通事故の遺児だったのですが、親が亡くなる現場を見ていません。
しかし震災遺児・孤児の場合、その現場を見ていたり、自分も死ぬ思いをしています。大学生のボランティアと遊んでいるときのリアクションがただごとではありませんでした」(西田さん、以下同)
当時「あしなが」は心のケアについては手探り状態だった。自分史を語るための「つどい」は行われていたが、対象は高校生以上に限定。それを中学生以下にも広げたのは阪神・淡路大震災以降だ。そんな中で出会った小学生は描いた虹を自ら黒で塗りつぶしていた。
「黒い虹を元の虹に戻そうとの発想から、支援施設の名前はレインボーハウスになりました。私たちは専門家ではありません。遺児としての体験があり、当事者として放っておけなかった」
2〜3月になると落ち着かなくなる子も
阪神・淡路大震災後、震災遺児・孤児へのサポートを本格化。アメリカにある、愛する人を亡くした子どもや家族のための『ダギーセンター』で研修も受けた。
「気持ちを吐き出させればいいという考えもありましたがダギーセンターで学んだ手法を取り入れました。深い悲しみやトラウマについて話すのを決めるのは子ども自身。主導権は子どもにあります」
このときのノウハウが、その後の自死遺児支援につながり、東日本大震災の震災遺児・孤児へのサポートにも結びついていく。
宮城県では'04年、『仙台グリーフケア研究会』が立ち上がった。自死遺族のための「わかちあいの会」を作り、'10年には地域自殺対策緊急強化基金の支援を受けて、子どもを対象に「ワイデイプログラム」も立ち上げている。そんな時期に東日本大震災が起きる。
「東日本大震災の前には、仙台で、自殺対策でつながった人たちがいました。'11年5月にはワンデイプログラムの対象を津波遺児・孤児にも拡大。日常的なケアが広がっていた時期だからこそ、突発的な災害があっても受け入れることができたのです」
震災から8年。いまだからこそ体験を話せるという人がいる一方で、2~3月になると落ち着かなくなる子も少なくない。卒業式や入学式といった節目に、亡くなった友人を思い出すなど気分が落ち込むこともある。スタッフの中村優一さん(27)は課題をあげる。
「震災当時、まだ生まれていなかった胎児の場合、いまは小学生になっています。3月11日は月曜日、親とは別々に過ごすことになる。どう過ごすか、揺れている場合もあります」
置かれた状況によって子どもたちはさまざまな不安を抱える。息の長いケアやサポートが求められている。
(取材・文/渋井哲也)
《PROFILE》
しぶい・てつや ◎ジャーナリスト。長野日報を経てフリー。東日本大震災以後、被災地で継続して取材を重ねている。『命を救えなかった―釜石・鵜住居防災センターの悲劇』(第三書館)ほか著書多数。