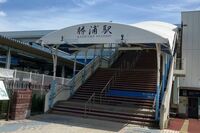また、燃料の問題で避難がままならなかった住民も少なくない。ガソリンがなく、数時間歩いて避難所を目指した人、車を置いて町役場が手配したバスで避難をした人もいる。放射性物質の拡散と、自分たち一家が逃げるスピードのどちらが速いか、恐ろしかったと話す人もいる。
焦りは募っても思うようには動けない。しかし、容赦なく危機は迫る。事故から3年後に明らかになった双葉町上羽鳥のモニタリングポスト(原発から5・6キロ)のデータでは、福島第一原発が最初の爆発を起こす直前の12日午後2時40分40秒に、空間放射線量が毎時4・6ミリシーベルト(事故前の約11・57万倍)に上昇している。
前述のとおり、近隣の4つの町には12日朝に避難指示が出ていた。だが、渋滞に巻き込まれ、昼過ぎから夕方近くまで避難指示区域の外にたどり着けなかったと話す住民も多い。
甲状腺被ばくを抑える安定ヨウ素剤は、避難の混乱の中、かろうじて大熊、双葉、富岡、三春町にのみ配布された。川内村のある避難所では「小さな子どもには砕いて年齢に応じた量を飲ませる」との指示に対し、「そんなことできるか」「なんでこんなものを飲ませなくてはいけないのか」と怒号が飛んだ。
ほとんどの住民が安定ヨウ素剤の存在も、その意味も知らなかった。ひらた中央病院(平田村)ら研究チームによる調査では、ヨウ素剤を配布された三春町の子どもが服用したケースは、約6割にとどまる。0〜2歳の小児では、安全性への不安から、3歳以上と比べて内服していない傾向もあった。
双葉消防本部次長・渡邉敏行さん(59)も、事故当時を振り返り、「消防は避難支援が必要な人、取り残された人の対応をしたが、住民への対応をする町村も相当、厳しい現場だった」と指摘する。避難計画はあったものの、複合災害を想定した規模ではなく、現場では難しい判断を迫られ戸惑うばかりだった。
「私たちの経験が教訓になってほしい」と渡邉さんは言う。前出の渡部さんも、自身の経験から断言する。「原子力災害は、想定どおり、教科書どおりにはならないんです」と。
進む再稼働に懸念大
政府は、'18年7月の「第5次エネルギー基本計画」で、原発を「重要なベースロード電源」と位置づけており、次々と再稼働を進めている。現在、稼働している原発は全国で8基。2月22日には、茨城県東海村の東海第二原発について、日本原電の村松衛社長が再稼働を目指す方針を伝えるため、東海村、水戸市を訪問した。
それに対し、茨城県の大井川和彦知事は「(安全対策を検証中の)県の対応を軽視している」と不快感を示している。
'18年3月、日本原電は東海村をはじめ、茨城県内にある日立市、ひたちなか市、那珂市、常盤太田市、水戸市と『新安全協定』を締結。これは再稼働の「実質的な事前了解」の権限を都道府県と立地市町村から周辺6市町村にまで拡大したもので、納得しない自治体があれば、話を進めることはできない。
また今年2月には、常陸大宮市など8市町村とも協定を結んだが、こちらは安全確保に向けた現地確認や、再稼働や施設の新増設などの安全対策について意見を述べる権限にとどまっている。