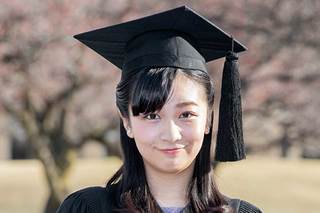自分がいけないのだと責め続けた。自分の人生は終わったという思いに支配された。
「朝方、そろそろ寝ようと思ってベランダでタバコを吸っていると、近所の年下の男の子が5時ごろ家を出るんです。あの子は一部上場企業に就職したんだっけ、ああいう人が世の中を作っているんだなあ。キャリアを積んで一人前になっていく。僕は26歳で何のスキルもない、とまた落ち込んでいく。本当は社会で先頭を走りたいタイプだったのに」
大学時代、文芸の同人誌を作っていたことがある。それが「そこそこ売れた」ので、編集者として活躍したいという思いが強かった。なのに結局は家にこもっているだけ。
理想と現実とのギャップに苦しむと同時に、彼はやはり「頑張れなかった自分」を否定し続けていたのだろう。
2年ほどひきこもっているうちに体力も減退していく。歩いて5分のコンビニへも筋肉痛が激しくて行かれない。
身体が弱ってくると眠ることもできなくなる。ちょっとうとうとすると、映画『エルム街の悪夢』のような悪夢を見る。「寝逃げ」ができなくなったと彼は感じた。
やはり親より先に死ぬことはできない
「寝ても起きても悪夢が追いかけてくる感じ。背中が痛くて寝ても座ってもいられない。薬だけが増えていきました」
ある日、とうとう薬と酒を同時に大量に飲み、トイレで気絶してしまう。弟に発見され、病院に救急搬送された。
「胃洗浄で助かったんですが、弟に発見されたことが情けなくてたまらない。家に帰ると家族に薬を捨てられていました。薬が恋しくてたまらない。頭を麻痺(まひ)させる薬がなくなり、冷静になる過程で、“死ぬべきだ”と神の声を聞いたような希死念慮(きしねんりょ)を経験しました」
ところが、その土壇場で再度、石崎さんの理性が働く。高校の同級生が自殺した当時を思い出したのだ。母親が抜け殻のようになったことを。
「うちの親も兄弟も悲しむだろうなと。たとえ親子関係がよくないとしても、やはり親より先に死ぬことはできない。なぜかそう思ったんですよ」
底をついた、という実感があった。それを彼は「絶望の限界が見えた」と表現した。絶望の限界が見えたら、あとは浮上するしかない。ひきこもりと「事件」とが取りざたされる昨今だが、ひきこもる人の多くは犯罪など起こさない。むしろ、どんどん沈んでいくのだ。だが、石崎さんのように底打ち感を体験した瞬間が浮上のきっかけになりうる。