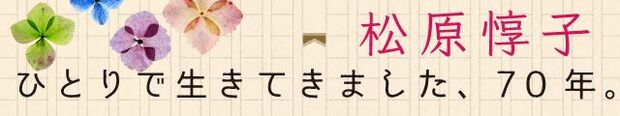現在63歳のAさんは、数年前に母親をがんで亡くした。母親はまだ79歳だったということだ。母親は58歳のときに胃がんが見つかり、胃の5分の4を切除した。Aさんは、必要な手術だったのか、今もって疑問を感じているが、当時は知識のない自分だったので医者の言いなりだったと自分を責めている。
この手術をきっかけに母親の身体は弱り始めたというのだが、その当時、Aさんの母親の実父は存命で、同じ町内に息子夫婦と暮らしていた。Aさんからみて祖父にあたるその人は、100歳を過ぎていたにもかかわらず、普通に家で生活できたというのだから、驚く。
しかも、日課のように毎日、Aさんの家に通ってきたというのだ。
祖父の口癖は「死にたい」
「歩いてですか」とわたしがびっくりして聞くと、Aさんは笑いながら頷いた。しかも、朝9時に来て、お昼を娘(Aさんの母親)と食べて、16時半に帰るというのだから、まるで、デイサービスだ。胃がほとんどない母親は、70代に入ると「暑い、疲れた」を連発するようになったが、父親が毎日来ることを拒まなかった優しい人だった。
そのころ104歳だったというおじいさんはどんなふうに毎日を送っていたのか。その心境について、Aさんに聞くと、Aさんは苦笑いしながら答えた。
「祖父は“死にたい、死にたい”ってしょっちゅう言っていましたよ」
本当にその言葉しか記憶がないほど、言っていたという。
どう答えていいかわからなかった彼女は、「おじいさん、なんで、そんなに死にたいの?」と聞いたところ、祖父は「長生きしても意味がないよ」と答えたという。人により違いはあるだろうが、100歳を超えれば身体を動かすのも大変だろう。日常生活も苦痛を伴い、何かをやる意欲もなくなり……。
いくら元気に見えても、その年を生きるというのは、それだけ大変なことに違いない。老いるというのは過酷だ。しかも、死ぬまで老いつづけなくてはならない。ただ食べて出して寝るだけの生活だと思ってしまえば、「生きていても意味がない」ことになる。
120歳まで生きたい人もいるが、わたしにはAさんの祖父の「早く死にたい」という気持ちがとてもよく理解できる。健康だろうが、優しい家族がいようが、そういう条件の問題ではないのだ。
「死にたい! 死にたい!」それを毎日聞いていたAさんの母親も大変な心労だっただろう。
その祖父は自宅で105歳のときに倒れたが、息子の家より娘の家のほうがよかったようで「ここから出してくれ!」と叫びまくり、自宅を出てAさんの家に来たという。結局、最後はAさんの母親が面倒をみることになった。祖父が希望の死を迎えることができたのは106歳だった。
<プロフィール>
松原惇子(まつばら・じゅんこ)
1947年、埼玉県生まれ。昭和女子大学卒業後、ニューヨーク市立クイーンズカレッジ大学院にてカウンセリングで修士課程修了。39歳のとき『女が家を買うとき』(文藝春秋)で作家デビュー。3作目の『クロワッサン症候群』はベストセラーとなり流行語に。一貫して「女性ひとりの生き方」をテーマに執筆、講演活動を行っている。NPO法人SSS(スリーエス)ネットワーク代表理事。著書に『老後ひとりぼっち』、『長生き地獄』、『孤独こそ最高の老後』(以上、SBクリエイティブ)、『母の老い方観察記録』(海竜社)など。最新刊は『老後はひとりがいちばん』(海竜社)。