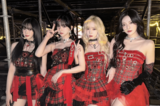ポジティブ思考でプロの役者の世界へー
プロになるため、アマチュア劇団に退団を告げると大反対された。引き留めではない。「神谷は背が低いからプロの役者はムリだ」と、努力ではカバーできない欠点を指摘されたのである。しかし、
「そういうハンデを抱えているけど頑張れ!という意味に僕は受け取ったの(笑)」
『劇団俳優小劇場』の入所案内を取り寄せると、月謝が高くて払えそうにない。演劇雑誌でほかを探していると劇団テアトル・エコーの記事に目が留まった。月謝もなんとか払えそうだし、募集要項を読むと若い役者を育てようという愛が感じられた。気がかりだったのは自分が支えるべき家族。だが、母に打ち明けると「自分で選んだ道なら頑張りなさい」と背中を押された。テアトル・エコーの入所試験のとき、劇団が発行している広報新聞を見て驚いた。
「熊倉一雄さん主演で『カチカチ山』をやっていたんです。絶対ここに入れてもらわなければと思いましたね」
ところが、筆記は散々だった。緞帳が読めずに「だんちょう」と書いた。それでも合格通知が届いたのは、実地試験と面接で評価された結果だろう。'70年、テアトル・エコーの研究生となった神谷は、23歳8か月でプロの役者としての一歩を踏み出した。
「稽古場には熊倉さん、山田康雄さん、納谷悟朗さんといった素晴らしい先輩たちがいた。山田さんはよくエチュード(即興劇)の指導をしてくれて、中途半端に上っ面だけなぞっていると、“おまえら、浅草に売るぞ!”って叱咤されましたよ」
まだアマチュアに毛が生えた程度の実力。しかし、初めて受けた声の仕事のオーディションで神谷は最終選考まで残った。使えるかもしれない─と考えたマネージャーが、慌てて仕事を見つけてくる。アニメ『魔法のマコちゃん』のその他大勢の役。この作品が神谷の声優デビューになった。
「アフレコの現場では右も左もわからず、後ろのほうでしゃべっていたら、“何やってんだ!”って先輩たちにマイクの前まで突き飛ばされてね。セリフを言ってから反省していると、“終わったら早くどけ!”とド突かれた。こんなんじゃ使ってもらえないなと落ち込んだのが声優デビューの思い出ですよ」
それでも仕事は次々に入ってきた。脇役ながら『いなかっぺ大将』('70年)、『赤き血のイレブン』('70年)、『科学忍者隊ガッチャマン』('72年)等々。
そして'73年、『バビル2世』や『荒野の少年イサム』で主役に抜擢。
「“下手だなー”って自分では思っていましたよ。陰のある役をカッコよく演じる小林清志さんや井上真樹夫さんの芝居を指をくわえて横目で見ていた」
“叫びの神谷”の異名で唯一無二の存在へと
現場で間近に見る先輩たちの演技は、生きたお手本だった。表現力を貪欲に吸収し、“自分らしさ”を追求した。そして『ゲッターロボ』('74年)や『勇者ライディーン』('75年)で主役を務めると、神谷は一気に存在感を示す。クライマックスでの渾身のかけ声。“叫びの神谷”という異名とともに、アニメ業界では「ロボット作品なら神谷明を使え」という気運が生まれた。前出の古川は言う。
「僕も『未来ロボ ダルタニアス』という作品で主役をいただいたとき、登場シーンで“ダルタニアス!”と叫んでみたんです。そしたらある人から“石焼き芋~”に聞こえると言われましてね(笑)。そんなとき、神谷さんから、そこは語尾を上げればいいんだよと、かけ声のコツをレクチャーしてもらったことがある。
そういう表現方法は声優にとっては企業秘密みたいなものなんですが、それを同業者に惜しげもなく教えてくれるところが神谷さんにはあるんです」
声優として売れっ子になり始めた神谷と、電車の中で十数年ぶりにばったり再会した高校時代の同級生がいる。演劇部で部長も務めていた佐藤正治である。
「僕は劇団で芝居を続けていて、“食えるか?”って聞かれたから“食えないよ”と正直に答えると、“声優やってみないか?”って神谷が誘ってくれたんです。で、アフレコの現場をいくつか見学させてくれて、神谷が里中智役で出ていた『ドカベン』では、後半に少しだけ出演させてもらったりもしました」
声優の道に入った佐藤は、『銀河鉄道999』('78年)などの作品で活躍。一方、神谷は第2次声優ブームを牽引する人気絶頂の中で、実は悩んでいた。二枚目の主役を張りながら、自分がお手本としてきた先輩たちのレベルにはまだまだ達していない……。
「自分自身に納得できない毎日が続いていましたね。自分のやりたい演技が、頭の中ではできるんです。的は見えている、でも投げると当たらない。そんな感覚でした」