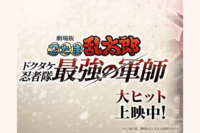そして、ポケベルやPHSなどの通信手段が浸透し始めると、女子高生同士が学校を越えて連絡を取り合って、放課後に渋谷などに集うように。なかにはサークル活動を始める女子も。いわゆるギャルサー(ギャルサークル)だ。
「2001年ごろ盛り上がっていたギャルサー開催のイベントのパンフレットに、最初に“盛る”という言葉が出てきたようです」
彼女たちが目指していたのはプリクラ映え。多くの学校では校則が厳しく、髪は染められない。どのようなメイクや髪型なら当時のプリクラ機で実物よりよく写るかを試行錯誤しながら、「盛れる」「盛れてる」などと使い始めたのだ。
携帯ブログでの発信も始まる
一方、渋谷に憧れていた地方在住者はネットを使い、携帯ブログで発信し始めた。
「『デコログ』をはじめとした女の子向けの携帯ブログコミュニティーで、全国の女子がつながっていました。知り合いに囲まれた環境で暮らす地方の子は特に派手で目立ちすぎるメイクなどができないので、白い肌で茶髪をくるりと巻き、デカ目を強調するスタイルが流行った。
アイメイクのプロセスやつけまつげのカスタマイズ法などを詳しく紹介し、自撮り写真をつけて公開しているブログが人気ランキング上位でした」
'12年にはスマートフォンの世帯普及率が49・5%にまで上昇。女子文化の舞台は、渋谷という街から、携帯ブログを経て、ツイッターやインスタグラムなどのSNS上に場を移す。
「もはやデカ目の時代も終わりました。今のヘアメイクはアプリを活用した“ナチュラル盛り”が主流。最近では顔を盛ることよりも、伏せた顔や横顔だけを写し、ファッションを含めた全身と、自分のいるシーン、つまり世界観ごと盛る“トータル盛り”なのです」
ただ、トータル盛りの写真は自撮りができないのが難点。今後はうまく“自撮りで他撮り”をする技術が大いに待たれているという。
ここまで平成の女子文化を彩った“盛り”を振り返ってきた。異性へのモテを意識したものもなかにはあるが、基本的には女子による、女子のための盛り。「モテるためにすることではなく女子同士のコミュニケーションのためにあるもの」と久保さんは言い切る。
「盛りは、そのコミュニティーのメンバーであることを証す暗号。どんどん更新される暗号がわかってこそ仲間なんです」
平成女子の盛り文化の根底にあったのは、自分の好きなものを大切にできる仲間づくりなのかもしれない。