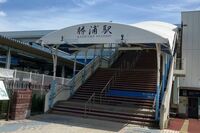ふるさとを取り戻すために
視察者にはまず、東電の担当者が経緯と進行状況を説明する。それによれば、事故後8か月くらいは不安定な状況にあったが、注水がうまくできるようになってから、危機が次第に収束していった。さらに構内の地表面をモルタルで覆う「フェーシング」の進んだ2015年を境に、空間放射線量が少しずつ減り、作業員の装備が徐々に軽くなっていく。一方、燃料取り出し装置のトラブルで延期を繰り返すなど、廃炉に向け、一進一退を繰り返しているわけだ。
大和田が決まって学生たちと作業員向けの社員食堂で食事をするのも、現状を知ってもらうためだ。
「作業員の方々は地面に座って冷たいお弁当を食べていると思っている学生が多いのですが、2015年にこの社食ができて、温かな食事ができるようになりました。毎日5種類から選べ、これがとてもおいしいんですよ。環境が改善され、作業員のケガや事故が激減しました。視察の感想を自分の言葉で書くように言っていますが、“廃炉に向けて大事なのは作業環境ですね”などと、作業員の笑顔が見られる食堂のことに触れる学生が多いんです」
栃木県出身の川島史奈さん(21)が進学先に福島大学を選んだのは、福島の現実を学びたいとの一心からだった。
「東電は住民の方々をひどい目にあわせたとずっと考え、敵愾心さえもっていました。しかし、いま第一原発で働く4000人あまりの作業員のうち、6割近くが地元の方だと知り、意識を改めました。みなさん、ふるさとを取り戻そうと必死なんだと気づかされたのです」
こうして原発を視察した学生に対して、「いつまでも見てきたと言うな。同じことをずっと言っていては事実ではなくなる」と大和田は必ず釘を刺す。何度も入構してきて、状況が一変するのを目の当たりにしてきたからだ。
視察の窓口を務めるのは東京電力福島復興本社の広報部長・岡崎誠さん(52)。さまざまな目的をもつ学生を受け入れる背景には、大和田との深い信頼関係がうかがえる。
2016年の人事異動で福島に来た岡崎さんは、ここで何をすべきか、大和田に教わったと話す。
「震災から5年過ぎていましたので、遅れを取り戻したい気持ちもあって、大和田さんの話をよく聞いたり、あるいは大和田さんとご縁のある方と付き合うようになりました。会社の机に座って仕事をしているだけではわからないたくさんのことを、大和田さんがハブのようなかたちになって、教えてくれたんではないかなと思います。
復興で肝心なのは、東京電力で働く者が浜通りに居続けること。単身赴任が多いので人の入れ替わりもあるのですが、累々と思いをつないでいくことで、人の営みとしてなにかが生まれ、はじめて新しい街ができていくのではないでしょうか」
大和田は被災者を数ではなく、ひとりひとりの声として伝えてきた。東日本大震災ではなく、「東日本・津波・原発事故大震災」と呼ぶべきだとも提唱してきた。当然、東電に対する激しい怒りも番組で何度もぶつけた。
2018年に東京電力本社でおこなった社員向けの講演では、東電内の温度差を強く批判した。
「東京の東電と、福島の東電はまったくの別会社だ。東京の社員にとって福島なんて、他人事でしょ? でも、現場に携わる東電の社員はみなさん、命がけですよ」
事故を起こした責任から、福島を忘れずに仕事をしているつもりでいた社員は大和田の語る福島の状況を知り、「びっくりした」「想像もつかなかった」と感想を綴った。そこに温度差を見いだし、「東電にはいま2つ会社がある。1つにならなければならない」と放送で指摘した。