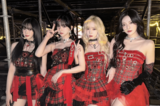不登校の息子を変えた母の言葉
中学に入ると、魂が抜けたように天井を眺め続ける吉藤さんを見かね、母が言った。
「いい成績をとってくれとは言わない。学校にも行かなくていい。毎日楽しそうに目を輝かせてくれたら十分だから」
それ以来、母は吉藤さんに何も言わなくなった。
「父も母も、私を見捨てなかった。過度に関わるわけでもなく、向き合い続けてくれました。好きなことを見つけられるようにといろいろなことをやらせてくれた。それは感謝しています」
ピアノ、ミニバスケット、絵の教室、どれも長くは続かない。指示されたことはやりたくない。父がボーイスカウトの隊長で、キャンプやバードウォッチング、きのこ採集にもよく行った。でも、鳥もきのこも興味は持てなかった。
ある夏、10連泊のキャンプに参加すると、ロープワークを褒められた。メンバーに「すごい」と重宝され、小さな居場所を得ることができた。
「工作もロープワークもそうだけど、必要性や機能性を発揮することで私は居場所を確保できた。それは、誰かの役に立つこと。喜んでもらえること。何もないところから人との関係性をつくるのは難しいけど、役割があって居場所を確保することで、関係性が生まれていくんだってわかった。これは、カフェの大きなヒントになっています」
不登校の時期によく出かけて楽しかった場所は、奈良県の橿原市立かしはら万葉ホールだった。大きな図書館があり、地下にあるこども科学館では、光の三原色の仕組みや音の伝わりを実験できた。
中1の夏、そこで開催されたロボット大会に母のすすめで参加。迷路をロボットで進み、2回ゴールをしてタイムを競い合う。ところが、2回ともゴールできたのは吉藤さんだけ。結果は優勝だった。
「ほかの人はみんな頭がよさそうだった。頭の中でとことん考えてから作る。私はプログラミングを1行書いては走らせ、失敗してはまたその場で書き直して調整した。自分は勉強もできないし頭も悪いと思っていたから、とにかく、トライ&エラーで試行回数を増やしたんです。これは、今の私にも続く研究スタイル。このときに手応えをつかんだんだと思います」
翌年、大阪で開催された『ロボフェスタ関西2001』の最終日、「虫型ロボット競技大会グランドチャンピオンシップ」大会では準優勝した。
「頑張ったことは報われると思ったし、それでも1位になれなかった悔しさを味わった。でも、そのことよりも、自分で憧れの対象を見つけることができたことが大きかったと思う」
展示されていた中でも、ひときわ大きな“一輪車で自走するロボット”がいた。そのロボットを作った久保田憲司先生に興味を持った。
「本田(HONDA)さんが8億円かけて作ったアシモ(ロボット)は1歳児でもできる二足歩行や。俺は工業高校の生徒と一緒に一輪車に乗れるロボットを作った。一輪車乗るほうが歩くより大変やろ。俺らのほうがすごいぞ」
そう言って笑っていた久保田先生は、奈良県立王寺工業高校の先生だった。
この工業高校に行こう。吉藤さんに目標ができた。