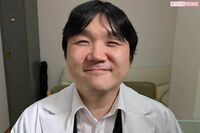外科医として多くの手術を行い、現在は愛知県でクリニックを開業している小林正学先生(48)。実はがんサバイバーであり、“がんになったがん治療医”としてさまざまな情報発信を行ってきた。がんを宣告された医師は、いったい何を思い、どんな行動を選択したのか。
自分で見つけた甲状腺のがん
「2019年3月に系列のクリニックが閉院し、行き場を失った超音波診断装置を名古屋にある私の前職のクリニックが引き取ることになりました。
到着後、きちんと動くか動作確認のため自分の首に検査器を当てると、白く石灰化した病変が見え、外科医のころに見慣れた甲状腺がんだとすぐにわかりました」(小林先生、以下同)
さらに検査器を当てると、周囲にはたくさんのリンパ節への転移があり、肺の間の縦隔にまで達していることもわかった。短期間にできたがんではないようだった。
「まさか自分ががんになるなんて……と絶句しました。キーンと耳鳴りがして目の前が真っ白になり、崩れ落ちそうになりました。夢であってほしいと頬を叩きましたが目が覚めるわけもなく、現実を受け入れて死を覚悟しました。
正直、ああ、終わったな……と思いました。まるで人生の敗北者のように思えて、絶望したんです。
でも、それまで仕事がかなり忙しかったこともあり、これでようやく休めるんだ、という安堵に似た感情が湧き上がってきたことも覚えています」
その日のうちに甲状腺を専門とする診療所を受診すると、自分の見立てどおりに甲状腺がんと宣告された。
甲状腺がんの多くは進行が遅いため、手術のために紹介された大学病院で、「ここまで進行しているケースは珍しい、手術も厳しいものになる」と告げられたという。
「手術の時間は12時間で、2~3割の確率で声が出なくなること、甲状腺の近くを走っている反回神経という神経を巻き込んでいた場合は、がんを切除せずに気管切開だけで手術を終えると説明を受けました。これには言葉を失いましたね……」
結果、手術は予定より早く8時間で済んだが、リンパ節転移は35個もあり、高い確率で再発すると告げられた。首の傷痕は20cmに及び、術後はICU(集中治療室)で2日間過ごした。
「麻酔から覚めて執刀医の話を聞き、繊細な手術をしてもらったことがわかって本当にありがたかったです。現在は切除した甲状腺の機能を補うためのホルモン剤を飲んでいます。一生飲み続けないといけませんが、幸い、定期検診で再発は見つかっていません」
小林先生は自分ががんになって初めて、がん患者さんの心の奥には医師が知らないたくさんの思いがあることに気づいたという。
「患者さんは、主治医の前では平気そうにしていることも多いですが、本当は自宅で悩み苦しんでいて、不安で眠れない夜を過ごしていること、また、家族も必死に支えているんだということを知りました」