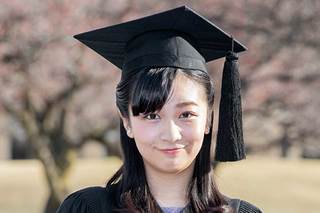多才な人である。同時に、何でもやってみる人である。
この春、人気長寿番組『笑点』(日本テレビ系)を卒業した落語家の林家木久扇(86)から受けるのは、そんなバリエーション=変奏だ。
落語家・林家木久扇、これまでの歩み

「自分の中に7、8人が住んでいるような感じがしますね」
とは本人の弁。
あくまでも木久扇の人生の主題になったのは「落語」である。とはいえ、落語をしゃべっていれば自分の人生に納得するタイプではなく、落語家であると同時に、イラストを描き、俳句を詠み、現在へと続くラーメンブームの火つけ役でもあり、レコード『いやんばか~ん』(1978年発売)を10万枚以上セールスした歌い手であり、という具合に、木久扇という素材を多方面に展開してきた。そのどれもが一定の成功を収めるという、ラッキーに守護された人生。
「人生のすみずみに、指針を言ってくれた人がいたんです」というこれまでの歩み。漫画家の清水崑先生のすすめに乗って落語家へ転身し、立川談志師匠のひと言で『笑点』の立ち位置を決め、『笑点』卒業に当たってはおかみさん(木久扇夫人の豊田武津子さん)のひと言が背中を押した。
指針を示す人に導かれつつの落語家生活は64年目。『笑点』でのイメージは、黄色い着物のおじさん、面白いことを言う与太郎キャラ、だが、それはあくまでも一面に過ぎない。'00年の胃がん、'14年の喉頭がんを乗り越え、落語家として生き延びた多才=多彩な人生を、ご本人や弟子、息子、『笑点』プロデューサーの証言から読み解く。
絵の才能と仕事に目覚めた少年時代

木久扇のイメージカラーでもある黄色の着物。そこにも込められた戦略があった。
「テレビって若い方は知らないと思いますが、昔はモノクロ、白黒でした。それがカラーになったとき、好きな色を選べたんです。
子どものころから絵を描いていたので、最初に目につく色が黄色だと知っていた。通学の児童の帽子も黄色、ランドセルのカバーも黄色、注意を促す交通標識も黄色が多いでしょう」
子どものころから身についていた絵心が功を奏した。
1937(昭和12)年、日本が戦争へと突入するきな臭い時代、東京は日本橋久松町に豊田洋少年は生を享けた。下町の、粋な風景に暮らしは包まれていた。
「近所には三味線の音色がいつも流れていて、明治座がそばにあって、役者さんもたくさん住んでいました」という界隈。通学路で目にした明治座の看板に絵心が芽生えた。
「明治座の脇を通ると、大きな絵看板が路上で毛布の上に置かれていました。これから掲げられる前でしたが、子ども心に目を見張りましたね。国定忠治や弁慶と義経などにワクワクしました。
その驚きを家に持ち帰って、雑貨問屋をやっていた家業の伝票の裏紙に描いて、おばあちゃんに『これやってるよ』って見せたことがきっかけ。『弁慶かい、(尾上)菊五郎かい』って感心しながら、たまごボーロ(お菓子)やおこし、金平糖をくれた。絵を描くとギャラ(=お礼)をもらえるんだって、初めてわかった瞬間でした」
最初の成功体験。洋少年はお菓子をもらえる商いを、すぐさま周辺に拡大した。
「近所のおばさんのところに持っていくと『ひろちゃん、あんたが描いたんかい?』と感心しながら煎餅をくれました。それで気をよくして、どんどん描いて上達していった。
明治座の看板の絵を覚えて、クレヨンで色づけする。見た人に、この役者だね、ってわかってもらえるという喜びも覚えましたね」
仕事で稼ぐ才覚、人を喜ばせる快楽。2つの愉悦を成立させた背景には、洋少年の絵を見て記憶し、そして再現する能力があった。
その才を裏づける証言として、弟子の林家彦いち(54)の師匠評が的を射ている。
「絵を再現することでわかるように、全体のスキャニングがうまいんです。どんな店かを説明する際も的確。師匠とはよく本の話をしますが、本の要約もうまいです。この本のポイントはこことここで、ここが面白いという話がどんぴしゃりで、私も自分の弟子に、全体を掌握する訓練をさせています」
洋少年のスキャニング能力によって生み出された、近所の人を喜ばせる絵。大人になった豊田洋が、落語家の前に選んだ職業は漫画家だった。