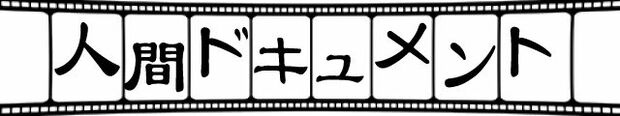新婚生活の傍らでバプテスト神学校で勉強
そして'85年3月、結婚。久米小百合としての新たな生活がスタートした。新米主婦として最初の数か月は苦労の連続。曜日に関係なく動く業界にいたので、ゴミ出しの曜日を覚えるのが苦手だった。
特に大変だったのは料理。
「母が調理師免許を取ったり教室を開くくらい、料理が上手だったんです。なので、実家では私が手間をかけて料理することがなくて。結婚後、しばらくは、おみそ汁を作るのでも『え、こんなに時間がかかるの?』と主人が言うくらい。ワカメをもどしたらすごい量になっちゃったり、恥ずかしい話です(笑)」(久米さん、以下同)
普通の主婦として淡々と生きていければそれで十分。そう考えていたが、教会音楽の仲間たちとの縁で、結婚した年に大作さんとともにアルバム『歌う旅人』に参加。'87年には初ソロアルバム『テヒリーム33』を発表した。
また、教会やミッションスクールからの誘いで、ミニコンサート開催などの活動も増えていく。そんなある日、ミッションスクールで質疑応答の時間が設けられた。自身のことについてはこれまでも話してきたが、そこで出てきた質問は「聖書に出てくる三位一体って、何ですか?」。
「当時はまだ全然、聖書の勉強をしていなくて、高校の世界史レベルの知識しかなかったんです。もう、赤っ恥どころじゃないレベル。教会のお手伝いをするには聖書の基礎くらいは知っていないとダメだったと感じて、神学校に入ることにしたんです」
こうして'88年、最初は聴講生として東京バプテスト神学校での勉強がスタートする。その後、大作さんから「せっかく入ったんだから、卒業を目指したら?」との言葉に背中を押され、本科に入学し直し'94年に卒業。聖書や歴史、ギリシャ語やヘブライ語の基礎、そしてキリスト教の根底にある“愛”について。一心不乱に吸収した日々を「今の私があるのは、この神学校のおかげ」と久米さんは言う。
そして、神学校に通うなかで、音楽宣教師としての道を考えるようになる。小坂忠さんをはじめ、素晴らしい先輩たちを間近で見て共に活動するうちに、芽生えた思い。それは卒業後に「フォートス」(ギリシャ語で光の意)と名づけたミニストリー(伝道団体)の設立につながっていく。音、絵画、音楽を軸に、チャペルコンサートやクリスマスブック、エッセイ本、そしてオリジナルアルバムなど活動は多彩。“集った人たちとともに神の大きさや深さを感じられるようなミニストリーにしたい”という思いが根底に流れている。
主婦として充実した日々39歳で子どもを授かり─
その間、大作さんとの結婚生活はどうだったかというと、イギリス〜ヨーロッパを1か月旅行したり、聖地を巡るツアーに参加したり、音楽制作をしたりと、夫婦ふたりでの充実した日々を過ごしていた。そして結婚から12年後、新しい命が誕生する。
それまで子どもをつくることは特に考えていなかった久米さん。妊娠を告げられたのも、体調不良で更年期障害かと思い病院に行った先でのことだった。
出産直前は回旋異常で大きな病院へ急きょ搬送され大変だったが、無事にかわいい男の子を出産。'97年、39歳の秋に久米さんはお母さんになった。
「子どものころは私に似てるってよく言われたんですけど、(息子も)四捨五入すると三十歳なので、そのころの主人に似てきました。あんなに可愛くてむにむにしてたチビちゃんが、もうこんなに大きくなっちゃったのかって、びっくりですよ」
そう語る表情は、優しい母の顔だ。呼ばれ方は“お父さん、お母さん”。
「でも何か頼み事をするとき、“すいません、久米小百合さん”と言ってきたり。外を歩いていて“小百合さん”と呼ばれて振り返ると息子だった、なんてこともあるんですよ」
驚くのが、幼稚園から高校まで毎日お弁当を作っていたというお話。小中高一貫の私立で給食がなかったのだ。好物の高野豆腐の煮物と卵焼きを欠かさず入れていたという。高校3年生のお弁当最終日にサンキューレターのようなものは受け取ったのだろうか。
「いえ、何もなかったですね。でも、一度も残したことがなかったんです。いつもお腹をすかせて早弁しちゃうくらいだから、当たり前なのかもしれないですけど(笑)。でもそのことが、私にとってはサンキューレターなのかなと思うんですよね」
今では料理好きの息子さん。オリーブオイルでチャーハンを作ってくれたりするという。それをニコニコ食す久米さんと大作さん。ほのぼのした光景が目に浮かぶようだ。
また大作さんに、ご夫婦の関係を何かに例えるなら?と尋ねると、ユニークな答えが返ってきた。
「クラスメート夫婦、でしょうか。出会ったのは20代前半ですが、小学校からずっと隣同士で机を並べていたふたりのような。あるときはどちらかが学級委員、あるときはどちらかが生徒会長。どちらかが落第でどちらかが満点のときもあったり。そんなクラスメートのような関係です」(大作さん)