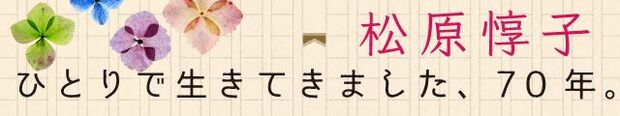1986年『女が家を買うとき』(文藝春秋)での作家デビューから、70代に至る現在まで、一貫して「ひとりの生き方」を書き続けてきた松原惇子さんが、これから来る“老後ひとりぼっち時代”の生き方を問う不定期連載です。

第19回
孤独死はそんなに悲惨ですか
高齢化社会の波の中で、ひとり暮らしの高齢者が増えている。
内閣府の「令和元年版高齢社会白書(全体版)」によると、2017年は65歳以上の者がいる世帯数は全世帯数の47.2%で、そのうちひとり暮らしの割合は26.4%、夫婦のみの世帯は32.5%だという。65歳以上のひとり暮らしは男女ともに増加傾向で、2015年は65歳以上のひとり暮らしの男性は約192万人、女性は約400万人にのぼる。
今後、ひとりで老後を生き、ひとりで亡くなるのが普通になるのは、時間の問題だろう。この統計から最後はひとりになる可能性が誰にでもありうることがわかる。
昭和の時代までは、長男は親と同居するのが当たり前だった。なので、親は家族の中で亡くなることができた。しかし、現代は、そういうわけにはいかない。親も子も同居は望まず、伴侶が死んだら、限りなくひとり暮らしにならざるをえない。
そこで、頭をよぎるのが、「孤独死」ではないだろうか。何か月も発見されずに腐敗した遺体や汚れた部屋の状況など、メディアが好んで悲惨な孤独死を多く取り上げることも起因しているが、孤独死のニュースを聞いて、気持ちのいい人はいないはずだ。
先の「令和元年版高齢社会白書」では、60歳以上の人に、万一、治る見込みがない病気になった場合、最期を迎えたい場所はどこかを聞いた結果、51.0%の人が「自宅」と回答している。また、60歳以上の人に「孤立死(孤独死)」を身近に感じるかどうかを聞いたところ、34.1%の人が身近に感じると答えたという。
遺体の腐敗による臭いなどで、隣人や周りの人に迷惑がかかる孤独死だけは避けたいと恐れる人は多い。孤独死は“みじめ”だと決めつける人もたくさんいる。
実は、わたしも以前は、孤独死を嫌うひとりだったが、今は違う。なぜなら、ひとり暮らしの私にとり、孤独死は自分の将来の姿でもあるからだ。