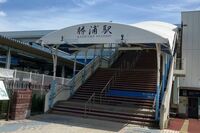ある日突然、家族が事件に巻き込まれて、自分が“遺族”になったらーー。加害者に謝罪を求めて会おうとしても、簡単には叶わないという現実。一方で、加害者になってしまった場合もまた、直接謝罪したくても“制約上”できないという「高い壁」が立ちはだかっていた。NPO法人『World Open Heart』理事長で、犯罪加害者と被害者、双方の支援団体『Inter7』の発起人でもある阿部恭子さんが伝える。
事件に奪われた日常
もし、家族が他人に殺害されたとしたら、犯人に求めるべきは死刑なのか。死刑を求めない家族は、被害者とはいえないのだろうか。
被害者遺族を経験しながら死刑廃止の立場を表明し、被害者と加害者の対話の意義を訴えてきた原田正治さんは、一部の人々からは「理想的な被害者」として注目され、また一部の人々からは「理想的な被害者ではない」と、時に批判を浴びてきた。
事件後、原田さんが歩んできた遺族としての道のりは過酷である。当時、助けてくれる人も、相談に乗ってくれる機関もなく、次々と降りかかる試練に、すべて家族だけで対応しなければならなかった。
1983年、原田さんの弟・明男さんが30歳のとき、突然、仕事中に亡くなり、居眠り運転による自損事故と判断された。ところが1年3か月後、雇用者による保険金殺人だった事実が判明。当時、36歳だった原田さんの人生も一変する。
犯人逮捕に伴い、報道陣が自宅付近を取り囲むようになり家族はしばらく外出ができなくなった。原田さんがようやく仕事に出られるようになると、帰宅を待ち構えていた記者がいきなり物陰から飛び出してきたこともあった。地域は騒然となり、周囲の人々の態度は明らかによそよそしく感じ、これまで親しかった人たちとも次第に疎遠になっていった。穏やかな日々は、緊張と不安に変わってしまった。
対応に苦慮したのが、事故として支払われていた保険金の返還請求だった。葬儀代、墓代等、弟が亡くなったことに要する出費としてすでに使用していたからである。「返還しないと不当利得です」と書かれた保険会社からの手紙は、まるで家族が騙し取ったと責められているように感じた。行政や弁護士に相談しても取り合ってもらえず、借金をして支払うほかなかった。
マスコミ対応や検察庁からの呼び出し、裁判など、会社を休まなければならない日も出てくるが、原田さんが勤務していた会社の対応は、ひどく冷淡だった。
不条理な出来事ばかりが続く中、家族の間でも徐々に精神的な距離が生まれ、家庭も壊れていった。
一度は求めた死刑
弟を殺害した加害者は、通夜や葬儀にも訪れ、事件が発覚するまで、何食わぬ顔で家族に接していたのである。人として、なぜそんな惨いことができるのか、直接会って問い質したい感情が日に日に強くなっていた。
そこで唯一、加害者に直接感情をぶつけられる機会は、刑事裁判だった。被害者への公的支援が一切ない時代、ある日突然被害者になった原田さんに、裁判の仕組みを説明してくれる人もなく、付き添いもないまま報道陣が詰めかける法廷にひとりで向かわなければならなかった。
どんな処分を望むかという検察官からの質問に、原田さんは
「極刑以外に考えられない」
と答える。
つまり、死刑である。加害者は塀の中で食事も睡眠も保証され、守られているにもかかわらず、被害者はさまざまな対応に時間を取られ、経済的にも精神的にも追い詰められていく。その原因を作った相手に、最も厳しい罰を求めたとしても不思議ではない。