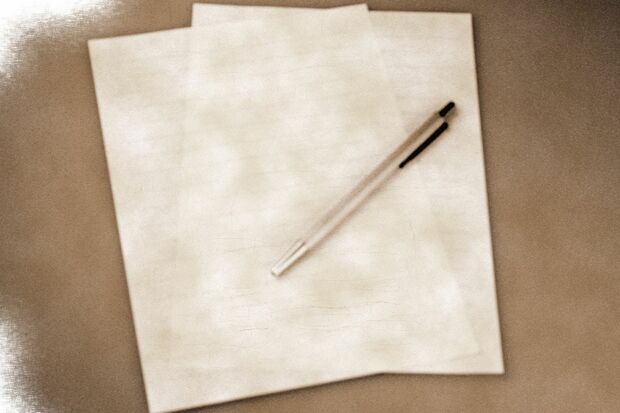
『かあちゃんの涙』
かあちゃんがぼくに初めて見せた涙は、痛かった。小学5年生のころの話だ。
戦後20年、それでもぼくたちの暮らしは貧しくて、ジュースやサイダーを飲むことなど、とてもできなかった。せいぜい粉のジュースの素を水にとかして、その甘さを味わうのが関の山。甘さに飢えていた子ども時代だ。 ぼくと兄ちゃんは、思いあまって、町の酒屋の倉庫に盗みに入ることにした。倉庫の中には、新品のサイダーが山積みされているはずだったからなあ。
けれど、倉庫にはなにもなかった。ぼくたちの心に残ったのは、倉庫を襲ったという恐ろしい事実だけだった。ぼくは、こわくなって、翌日かあちゃんに事実を打ち明けたよね。その夜、ぼくたちは、とうちゃんかあちゃんの前で正座させられ、きつくしかられた。かあちゃんは、なにも言わずに泣いていた。ぼくは、まともにかあちゃんの顔を見ることができなかったよ。
なあ、かあちゃん。あのときのかあちゃんの涙が、ぼくにはきつくこたえたんだ。歪んだ道を歩いてはいけないと強く教えられたんだ。あれから、50有余年。ぼくは、真っ直ぐに生きることのつらさや難しさを感じながらも、教員の仕事を続けてきたつもりだ。かあちゃんの涙の痛さが、ぼくの人生の土台を築いてくれたと今更ながらに感謝している。
かあちゃん、ありがとう。
かずさん(男性 65歳・京都府)
『かあちゃんの涙』の向こう側
少年時代、貧しさゆえに年子の兄とともに犯した『倉庫を襲った』という過ち。それを知って、子どもの前で流した『かあちゃんの涙』をふと思い返し、綴った1通の手紙。
かずさんは大学進学で故郷を離れてから、その後30年間、お盆や正月にたまに会うことはあっても、母と一緒に暮らすことはなかったそうです。「でも、いくつになっても、母は甘えられる存在だった」と振り返ります。
そんな母は晩年、認知症を患い、「このままではお父さんも倒れてしまうから、病院に行きます」と自らすすんで入院を決意。すると、その1か月後に母の危篤を知らせる電話があり、急いで駆けつけると、今まさに静かに息を引き取ろうとしていました。「父が「おーい、おーい」と声をかける中、『かあちゃん』は人生の幕を閉じました」と、かずさんは話してくれました。
それから16年の歳月がたち、教師をしていた父の姿を見て、「絶対、教師にはなりたくない」と思ったかずさんでしたが、気がつくと自分も同じ教師の道を歩むことに。教え子たちからいろいろ教えられ、支えられて教師生活が全うできたとしながら、こうも語ります。
「今思うと、母はあのとき『痛い涙』を流すことで凛(りん)とした正義を示唆してくれた。結局、それが自分を教師の道に導くことにもつながったのでしょう」
自身も年齢を重ねるうちにそうした母との思い出がだんだんと薄れ、「残念でしょうがないが、年老いていくということは、そうした記憶からも解放されることなのだろうか」と自問します。
ただ、こうして手紙を書くことで、薄れていく母の記憶をひとつの形に残せたことに「手紙を書きあげてみて、ほっとしています」と、かずさんは語りました。
亡き人への伝えられなかった感謝の気持ち。直接は伝えられない想いを、手書きの手紙にのせて伝えてみるのはどうだろうか。
コンクールを主催した
『母の日参り』パートナーシップとは……
戦後70余年にわたり、わが国の家庭文化に深く根を下ろした「母の日」。近年、GWから母の日(5月の第2日曜日)にかけてお墓参りを行い、亡き母をしのぶとともに家族の絆を確認することが、中高年を中心に広がっています。
「母の日参りパートナーシップ」は、「母の日」が実は「亡き母をしのぶ一人の女性の呼びかけで始まった」という由来を知り、長寿社会の今後にも色あせることなく、人々の心に豊かさをもたらす記念日であるように、ソーシャル・キャンペーンを展開している13団体が集結しています。
















