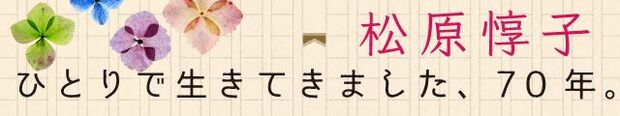1986年『女が家を買うとき』(文藝春秋)での作家デビューから、72歳に至る現在まで、一貫して「ひとりの生き方」を書き続けてきた松原惇子さんが、これから来る“老後ひとりぼっち時代”の生き方を問う不定期連載です。

第15回
URに住むという賢明な選択
昔は、その狭さから「うさぎ小屋」と呼ばれた日本の住宅だが、今でも日本の住宅は狭いうえに高い。大都市・東京はなおさらだ。ときどき、わたしたちは住宅費を払うために、働かされているのかと、うんざりすることがある。収入に対して住宅費の占める割合は高すぎる気がする。
新婚さんがまず考えなくてはならないことのひとつは、マイホームの購入をするか否かだろう。憧れのウエディングドレスの余韻を味わう暇もなく、多くの新婚さんが、マイホーム探しを始める。自分の城を持つって夢ですよね。そのためなら、なんでも頑張れる。パートにも行く。節約もする。しかし、マイホームの先に、35年ローンという恐ろしい借金生活が待っていることを、想像しないようだ。
マイホームの夢を砕く話はしたくないが、右肩下がりになった時代において、35年先まで会社が雇用してくれるとは考えにくい。現在、景気がいいIT企業も一過性のものかもしれない。35年といえば、30歳の人は65歳まで、40歳の人は75歳まで借金を払い続けることになる。つまり、人生の大半を借金の支払いに追われることになる。
それほどまでの大きな賭けをしてまで持ち家にこだわる必要がはたしてあるのか、正直言って疑問だ。
今から35年前、わたしが37歳で中古マンションを買ったとき、フリーランスにもかかわらず13年で完済できたのは、バブル景気のおかげだ。今でも、ローンを完済した日に「終わった!!」と叫んだ気持ちよさをよく覚えている。東大を受験したことはないが、東大合格のときと同じ気持ちかな。
一生、住むはずと購入して完済したマンションだが、思いがけない不幸に見舞われたことから、わたしは65歳のときにそのマンションを手放した。人生、ほんとうに先は読めないものだ。避難のつもりで実家の2階に住んで、93歳の母とまるで『大家さんと僕』(※カラテカ矢部太郎=著)の関係で暮らして5年以上になるが、45年ぶりの母親との同居に、想像以上の苦痛を感じ、発狂しそうになった。
友達もそうだが、肉親も距離が大事ですね。近すぎるのはトラブルとストレスのもとだ。よく「スープの冷めない距離」が親子のいい関係を示す代名詞に使われるが、いえ違います。「スープの冷める距離」だとわたしは言いたい。
ついに今年の夏、同居に耐えられなくなったわたしは実家を出ることにしたが、新たに住まいを探さなければならなくなった。新たなマンション購入も頭にあったが、なぜかいまさら、再び所有する気になれずにいた。ひとり身なので、賃貸でもいいのではないか。
しかし、ご存じのように、民間の賃貸住宅を借りるのは、年齢で断られるのは目に見えていた。また、いまさら、保証人を友達に頼むのも気が引ける。そこで浮上したのが公団住宅、今で言うUR賃貸住宅だ(以下、UR)。