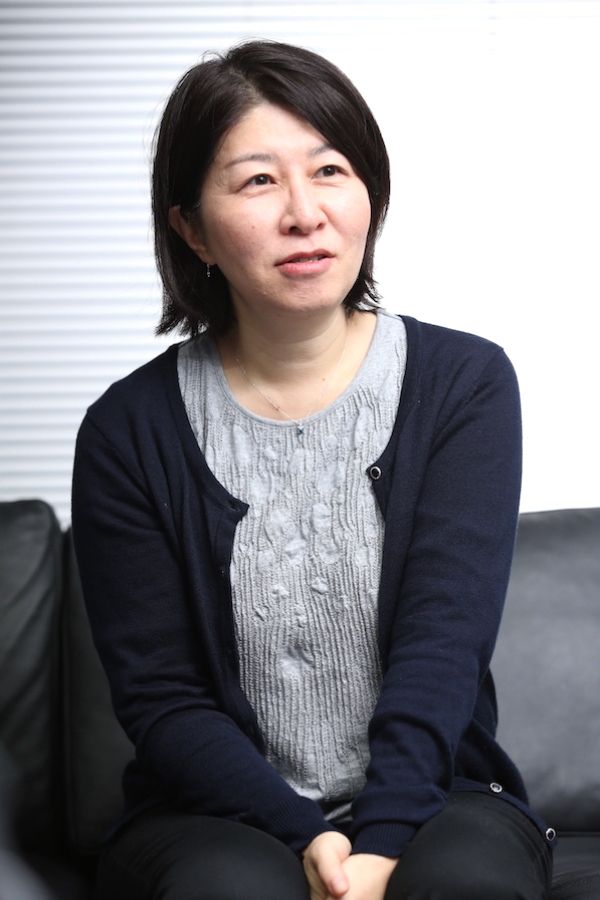■オタクとイケメン、そして足だけの幽霊
表向きは善人、実は裏稼業を持つ曲者ばかりが住む江戸の長屋。そこへ根っからの善人で、人助けが生きがいの加助が越してきたことで次々と面倒が起こり、住人たちは渋々助けることに……という人情時代小説『善人長屋』シリーズで人気の作家、西條奈加さん。
新作の『秋葉原先留交番 ゆうれい付き』は得意の時代物から趣向を変え、現代の秋葉原を舞台にした5つの話がつながる連作ミステリーです!
「最初に依頼があったのが7、8年前だったんです。それで秋葉原へ取材へ行ったりしたんですが、'08年に秋葉原通り魔事件が起こってしまって……事件をどう扱えばいいのか困ってしまいまして。ちょうどそのころに依頼してくれた担当さんが異動になり、そのままになっていたんですが、それから何年かして今の担当さんが声をかけてくれたんです。ただ書き上げるまで2、3年かかりましたね。締め切りがないとつい遅れがちになってしまって……。すみません(笑い)」
物語は、東京の奥多摩のさらに奥にあるという稲香村から始まります。ふと眠りから覚めた渡井季穂は、自分が足だけしか見えない幽霊になっていたことに愕然とします。ほかの誰にも気づかれない中、女たらしでボンクラ、世渡りだけで生きているという残念なイケメンの向谷弦という駐在所の警官だけが季穂の存在を認識してくれます。村長の妻に手を出して謹慎となり、自分が昔、勤務していた秋葉原にある交番へ行くことにした弦。記憶がなくなる直前まで秋葉原のメイドカフェで働いていた季穂は、こんな姿になった理由がわかるかもしれないと、一緒に行くことにする。
向かった先の「先留交番」にいたのは弦の先輩で、見た目は太ったメガネのオタク、中身は東大卒で頭脳明晰な権田利夫という警官だった。しかもそこは駐在所で、住人である権田の部屋には5台のパソコンに、アニメの本やDVDなどが山積み状態! そんな凸凹警官と足子(口がきけないため勝手に命名されてしまう)のトリオは、秋葉原で起こる事件を解決しながら、なぜ季穂が足だけの幽霊になってしまったのかを探っていくことに。
■舞台を秋葉原にした理由とは?
「友人に霊感の強い人がいて、その人が職場から家まで霊を連れて帰ってしまった、と聞いた話から思いついたんです。普通の幽霊だとひねりがないので、足だけっていうことにしたんですけど、いざ小説を書き始めてみると、手がないから文字も書けないし、顔もないので表情もない、物質を動かせず、スーッと通り抜けてしまうので足で地面に字も書けない、これは困ったなと(笑い)。それで足だけでコミュニケーションをとる方法を考えました」
そして、この交番のモデルになったのは、実際に秋葉原にあった「末広交番」(現在は、地域安全センターになっています)。
「以前、前を通りかかったときに古い外観の建物だったので印象に残っていたんです。それで交番ものにしようと考えた時にそこが浮かんできて、“末広”の反対の意味で“先留”という名前にしたんです。しかも駐在所って、東京23区内に60か所もあるそうなんですよ。そして舞台が秋葉原なのは、私自身がアニオタという理由もあります(笑い)。秋葉原へ通うほどではないですが、ほかの街よりは親しみを感じます。でも、取材で行ったメイドカフェは、正直恥ずかしかったです。お嬢様って言われるのも抵抗ありましたし、手でハートを作るハートビームもやられて、コスプレのできる店ではCAの衣装をすすめられたりして、どういう顔をしていいのかわからなくて(笑い)。でも、最近ではコスプレってメジャーになりましたし、こういうことを自由にできる風潮っていいなと思いますね。ストレス解消にもなるでしょうし。私もあと10か20歳若ければ楽しめたかな、と思います(笑い)」
また「秋葉原は街自体が不思議な場所という印象があります」と西條さん。
「昔は電気街で一種独特な街だったのが、今はアニメやオタク文化の街になった。そういうところって珍しいと思うんです。また、そんな街の表側の部分は派手でちょっと行くのが怖いような感じもありますけど、裏へ行くと小さな住宅や会社がたくさんあったりして、昭和っぽい感じが残ってるんですよ。そういうギャップも面白いんです」
凸凹トリオが秋葉原ならではの事件を解決していくたびに意外な謎が解け、足だけの幽霊になった秘密に少しずつ迫っていくのですが、実は事件がどうなるかわからないまま執筆し、ストーリーの真ん中を過ぎたあたりで、ようやく着地点を見つけたそうです。
「最初は企業とか裏社会とかを絡めて、ハードボイルド系に持っていくつもりだったんですけど、書いているうちに合わないなと思って、ラスト間際になってから、あえて悪人を作らないような方向でやろうかな、と。そして、この作品はミステリーなので、読者の方が読んで、スッキリしてくれればいいなと思います」
最後に事件解決でスッキリ&涙しつつも、続きがありそうなほんわりとした結末の本書。次作の可能性を伺うと「それは売り上げ次第です」と笑う西條さん。続編、期待しています!