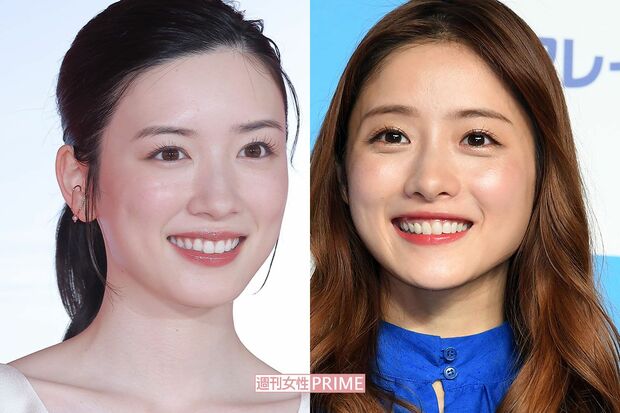もうすぐデビュー10周年を迎える窪美澄さん。最新作『トリニティ』は、1960年代に、とある雑誌の編集部で出会った3人の女性の人生を描いた物語だ。
女性の一代記を描いてみたかった
若くしてデビューしたイラストレーターの妙子は時代の寵児となり、ライターの登紀子は週刊誌やファッション誌で活躍しつつエッセイストとしても名を知られ、事務職の鈴子は結婚退職し平穏な家庭を築いている。彼女たちが人生で求め続けていたものとは──。物語は、妙子の葬儀で老齢の登紀子と鈴子が再会するところからはじまる。
「以前から女の一代記を書きたいと思っており、あるとき、伝説の女性ライターさんの存在を知ったんです。彼女が活躍していたのが'60年代の女性誌だったので、その雑誌を舞台に女性3人の人生を長いスパンで追っていくような物語を書こうと思いました」
流行りの映画や東京五輪、東大安田講堂事件など、彼女たちの人生は当時の文化や事件とともに描かれる。
「私は1965年生まれなので、当時の空気感はなんとなくわかっていたんです。実際の出来事の資料を読んだりしながら、その感覚をたどっていきました。ただ、私は年表を作るのがすごく下手なので、登場人物たちの年齢や行動と実際の事件をピタッと合わせるのが大変で……。『小説新潮』の連載中は、毎回、直されていたんです(苦笑)」
現実の事柄が登場する場面の中でも特に印象的なのは、のちに新宿騒乱の夜と呼ばれる国際反戦デーの日の出来事だ。その様子を見に行った3人は騒動に便乗し、「お茶くみなんか誰でもできるって馬鹿にしないで!」など、本音を叫びながら石を投げる。
「一般的には、女同士の友情って難しいといわれていますよね。たしかに、女性は結婚とか出産とか、人生のトピックによってつかず離れずの関係になったりしますから。でも私は、あの日、あの時、あの人といたことを忘れないと思ったなら、それは友情なんじゃないかなと思っているんです」
物語の中で登紀子は、フリーランスという仕事について、こう言及している。
《フリーライターだ、イラストレーターだ、デザイナーだなんて、横文字の職業が輝いているのはほんの一時期のことですよ。(中略)実際のところ、そのとき働ける人が働く。だけど、その代わりはいくらだっている……》
「私自身、小説家になる前はライターだったので、代替可能な仕事だという意識は常にどこかにあるんです。もし、私が明日、脳梗塞で倒れたとしたら生活は立ち行かなくなってしまいますし、“じゃあ、この連載はほかの作家で”ということもありえます。小説家もライターと同じで、常にピンと張ったロープの上を歩いているんです」