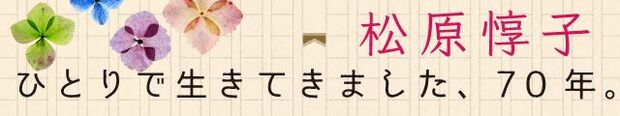1986年『女が家を買うとき』(文藝春秋)での作家デビューから、72歳に至る現在まで、一貫して「ひとりの生き方」を書き続けてきた松原惇子さんが、これから来る“老後ひとりぼっち時代”の生き方を問う不定期連載です。

第14回
身元保証人問題
日本は、ひとり身では生きてはいけないのかと思われるあしき習慣が社会にはびこっている。それが、入院・手術や家を借りるときに、身内の保証人を要求されることだ。自分が若くて親が生きているときは気づかなかったこの問題が、高齢になるにつれ、重くのしかかってくるのを感じる。
実際に、わたしの周りで起こったケースをあげてみよう。
■50代のシングル女性のケース
彼女は駅の改札口で転び骨折し、救急車で病院に搬送された。そこで、お決まりの「身内の保証人」を要求された。親も子どももいないので、たったひとりの身内である兄が関西にいると話したところ、すぐに来てもらいサインするように言われる。兄の到着を5時間待っての手術だった。
■60代のシングル女性のケース
50代で手術したときは、親が生きていたので親に保証人になってもらえたが、現在は他界している。今度、また入院手術となったらと思うと不安だ。兄弟はいるが疎遠で頼む気にもなれない。もし、重い病気になったら、治療しないかもしれない。
■64歳の既婚女性のケース
30代から甲状腺機能低下症で病院通い。昨年、大腸がんの手術をする。そのとき身内の保証人を求められた。彼女が「息子はいるが海外なので」と言うと、友人でもいいことになり、保証人になってもらったが、いくら親しくても頼むのは気がひけた。
2017年度、厚生労働省の研究班が医療機関約1300施設から回答を得た調査によれば、「身元保証人を求める」との回答が65%にのぼり、ベッド数が20床以上の病院では約90%に。保証人を求める医療機関のうち8・2%は、保証人がいないと「入院を認めない」とした。