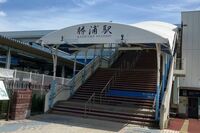7月23日、静まり返った会場に無数の花火が打ち上がる──。新国立競技場で幕を開けたオリンピック開会式は、これまで見たことがないような異様な雰囲気に包まれていた。一般観客の姿がないスタジアム、喜色満面の作り笑いを浮かべた各国要人や五輪関係者が、入場行進をする選手団に拍手をおくる。盛り上がり以上にむなしさを感じさせるオリンピックが幕を開けた。
大会直前になっても、世論は賛成と反対に揺れていた。その理由のひとつが、政府、東京都、組織委員会の変わらない危機管理意識の低さだ。入国後、五輪関係者などにPCR検査を繰り返すことなどを条件にする一方、選手に対しては2週間の待機を免除する特別措置をとっていた。
つまり、選手は入国直後から練習することも可能で、運営上必要な関係者(技術スタッフ含む)も必要な感染予防を行えば隔離されず、ホテルと会場などの往復をすることができるのだ。
2月に行われたテニスの全豪オープンでは、選手をチャーター機で入国させ、その後、2週間のホテルでの隔離生活(毎日PCR検査を実施)を命じた。万全の対策を講じたが、それでも選手や関係者から感染者が発生してしまった。
ところが東京五輪は、各国選手団がそれぞれのスケジュールで来日する統一性のなさに加え、隔離生活を免除。案の定、感染者が発生してしまい、その杜撰な管理体制に対して、各国メディアが一斉に糾弾する事態に発展した。政府は、水際対策を怠ったホストタウンに非があると責任を回避し、さらにアンチ五輪の声は高まっていった。
「五輪が始まれば一転する」──。関係者の折伏が連日響き渡るも、競技が始まってからも旗色はよくならない。ワクチンの副反応を怖がり、接種を拒否した日本人選手に対する世間の誹謗中傷に加え、直前に2回目の接種を完了したことで副反応による体調不良を訴えるアスリートも散見されるように。
海外の報告によれば、ワクチンの副反応で多いのは、打った筋肉部位の痛み(75%)、倦怠感(50%)、頭痛(44%)などだが、いずれも通常は1~2日で治まる。仮に、急激な血圧低下で意識を失うアナフィラキシーショックが生じても、ボスミンなどのアドレナリン注射で症状は治まるのだが、国民に対してワクチンについての説明が不足しているのが現状だ。