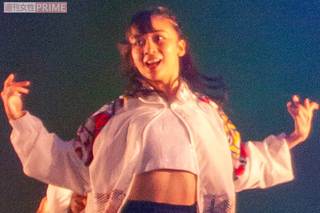年をとると不調や病気に悩まされ、のみ薬の量も増えていく。しかも女性は月経、更年期、婦人病など特有の症状や病気が起こりやすく、若いころから薬が手放せないことも少なくない。
ところが、「漫然とのみ続けると危険な副作用のリスクがある薬に要注意です」と内科医でアクアメディカルクリニック院長の寺田武史医師は言う。
女性ホルモンの薬に要注意
「まず気をつけたいのが、女性ホルモンをコントロールする薬。日本では低用量ピルやホルモン剤、排卵誘発剤などが普及していますが、それぞれ副作用やリスクがあり、長期間の服用には慎重な判断が必要です」
低用量ピルは、排卵を防いで月経の症状を緩和する効果があり、月経前症候群などさまざまな婦人病の予防、治療に有効な薬だ。
「低用量ピルに含まれるエストロゲンには血液を固まりやすくしてしまう凝固作用があるため、脳梗塞や心筋梗塞を起こす血栓症のリスクを高めます。
とはいえ基礎疾患のある人や喫煙者以外の発症リスクは低いので、医師の指示に従っていれば過剰に心配する必要はありません」

一方、更年期障害の症状緩和に有効なホルモン剤は、長期服用で高いリスクを招く。
「閉経が近づくと卵巣の機能が低下して女性ホルモンの分泌が減少します。するとホルモンバランスが崩れて不調を引き起こします。こうした更年期の症状にはホルモン剤によるホルモン補充療法が有効ですが、5年以上の長期服用で乳がんのリスクが高まるという報告も」
更年期の症状を緩和するにはホルモン補充療法以外にも、食生活や運動、生活習慣の改善が有効。服用の継続は、主治医と相談しながら慎重に行いたい。
また不妊治療で使う排卵誘発剤にも卵巣過剰刺激症候群という重い副作用が報告されている。
「不妊治療では1度に複数の卵子を採取するために排卵誘発剤を使って卵巣を刺激します。しかし刺激が過剰になると卵巣が腫れ、下腹部に激しい腹痛を引き起こす場合も」
不妊治療では主治医に不安や症状をこまめに伝えて、管理してもらうことが大切だ。