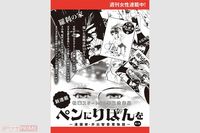1月からNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺〜』が始まった。江戸時代中期、多くの出版物を出した蔦重こと蔦屋重三郎の人生を横浜流星が演じる。曲亭馬琴に葛飾北斎、山東京伝……江戸で活躍した戯作者や浮世絵師は有名だが、彼らを売り出した立役者が“江戸時代のメディア王”蔦重だ。
牧之の雪国の話『北越雪譜』は出版までに40年
木内昇さんの新著『雪夢往来』は、江戸時代に1冊の本が刊行されるまでの紆余曲折を書いた長編歴史小説。蔦重亡き後の人間関係や出版事情もうかがえて、興味深い。
江戸期に出版が盛んになっても、遠く離れた雪国のことなど、江戸者は知る由もなし。越後から縮織物の商いに来た鈴木儀三治と江戸っ子との間で、こんな会話が交わされる。
「(雪が)一番積もる時季には、高さが一丈(約3メートル)ほどになりましょうか」
「おいおい、からかっちゃいけねぇよ。いっくら俺たちが江戸から出たことがねぇと言っても、そんな法螺にゃあ引っかからねぇよ」
一年の半分近くを雪に閉ざされるなど江戸では想像もできない。儀三治の住む村の女たちの冬仕事は縮を織ること。男はそれを売り歩く。俳句は村人の冬の楽しみでもあり、儀三治は牧之という俳号を持ち、文学と絵の素養もあった。
牧之(儀三治)は《江戸の者に、越後の話を書いて見せたら面白がってもらえんじゃろうか》《越後の風俗はきっと江戸者には新鮮なものばかりだろう。それに、古くからこの地に伝わる綺談は、きっと彼らの耳目を驚かすだろう》と考え、本にすることを思いつく。しかし、ここからが困難続き。木内さんは言う。
「牧之の雪国の話『北越雪譜』は、好きでよく読んでいたのですが、調べてみると、出版までに40年もかかったというのに驚きました。戯作者などと交流しているのも面白く、書きたいと思ったんです」
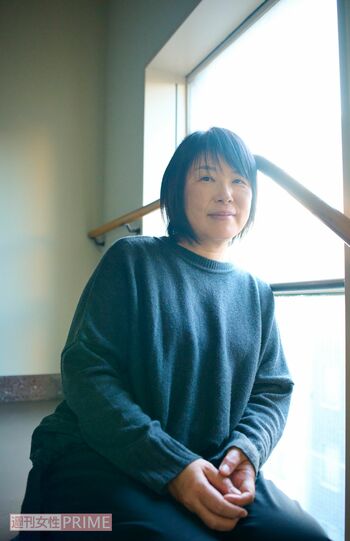
かんじきを履いて雪の上を歩く村人、反物を雪の上に広げる雪ざらし、雪男の姿など、牧之はイラストつきで越後の風俗や綺談を書いていった。それを、江戸に行ったときに書を習った師に託す。そこから山東京伝に相談がいく。
京伝は二代目蔦重に出版を持ちかけるが、無名の人は出せないと難色を示される。さらに二代目は出版にかかるお金を牧之が出すように要求。二十両で家が建つ時代に、五十両の大金! 家業の縮仲買も質屋も順調だが、道楽のためにそんなお金は出せない。
あきらめたはずの牧之だが、出版への思いはくすぶっていた。大阪での出版を請け負ってくれる人を見つけたが、相手が死亡し……。
期待し、待たされ、ダメになりを繰り返し、読みながら胸が締めつけられる。